
「こうえん」と入力して変換すると、「公演」と「講演」の2つが表示されて、どちらを使えばいいか迷ったことはありませんか?
同じ読み方なのに意味が全く異なるこの2つの言葉は、使い分けを間違えると相手に誤解を与えたり、失礼になってしまう可能性があります。
「公演」は演劇・音楽などの芸術的パフォーマンスを披露すること。
「講演」は専門知識を話して伝えること。
エンターテイメントなら「公演」、教育的な内容なら「講演」を使えばOKです。
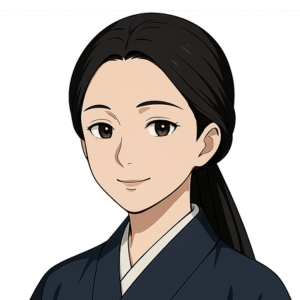
梅子殿、「こうえん」という言葉、武家の宴でも文書でも使うが、いつも迷うのじゃ。
歌舞伎を観に行くのも、学者の話を聴くのも、同じ「こうえん」と申すではないか?

政子様、それは大変な誤解ですわ!
舞台で舞うのは「公演」、教壇で話すのは「講演」。
漢字が違えば意味も違います。
私の教え子たちも、この使い分けで試験によく間違えますのよ。
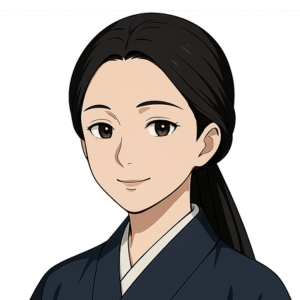
なるほど!
では、武芸の演武を披露するのは「公演」で、戦の策を説くのは「講演」という訳じゃな?
言葉一つで相手への敬意も変わるとは、まさに武士の礼儀と同じよ!

その通りです!
ビジネスの場でも間違えると大変失礼になりますから、この記事でしっかり学んでおきましょう。
例文もたくさんご用意していますわよ!
✅ この記事でわかること
- 「公演」と「講演」の基本的な意味の違い
- エンターテイメントと教育での使い分け方
- 実際の使用例と豊富な例文20選
- ビジネスシーンで間違えやすいポイント
- 「上演」「口演」など関連語との違い
この記事では、比較表やクイズ、具体的な例文を使って、誰でも簡単に理解できるように解説しています。
ビジネス文書やメールで自信を持って使い分けられるよう、ぜひ最後までご覧ください。
【比較表】「公演」と「講演」の違い
「公演」と「講演」は、どちらも「こうえん」と読む同音異義語です。
発音は同じでも、内容や目的がまったく異なります。
簡単にいえば、「公演」は演劇や音楽などの芸術的なパフォーマンスを披露すること、「講演」は専門知識や情報を聴衆に伝えることを指します。
「公演」の意味とは
「公演」とは、演劇・音楽・舞踊・演芸などを、公の場で大勢の観客に向けて披露することを意味します。
「公演」の特徴:
🎭 エンターテイメント性が中心
🎭 芸術的・娯楽的なパフォーマンス
🎭 観客を楽しませることが主な目的
🎭 劇場、ホール、コンサート会場などで行われる
たとえば、「宝塚歌劇団の公演」「ミュージカルの公演」「オーケストラの公演」といった使い方をします。
演者が舞台上で演技や演奏を披露し、観客がそれを鑑賞するという関係性が特徴です。
公演という言葉には「公(おおやけ)に演じる」という意味が込められており、不特定多数の観客に向けて芸術作品を発表する行為全般を指します。
チケットを販売して行われることが多く、エンターテイメント業界でよく使われる言葉です。
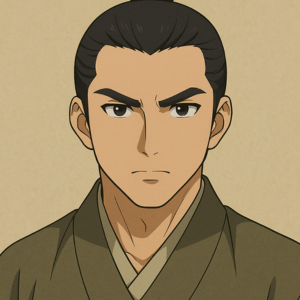
ワシの時代にも能や狂言があったが、これも立派な「公演」じゃったのじゃな!
天下を治めるには、民に楽しみを与える文化も大切じゃぞ。
まあ、当時はチケット制ではなかったがのう!
「講演」の意味とは
「講演」とは、特定のテーマについて、専門家や有識者が聴衆の前で話をすることを意味します。
「講演」の特徴:
📢 知識や情報の伝達が中心
📢 教育的・啓発的な内容
📢 聴衆に学びや気づきを与えることが目的
📢 講演会場、セミナールーム、学校などで行われる
たとえば、「経営者による講演」「環境問題についての講演」「著名人の講演会」といった使い方をします。
講演者が壇上で話をし、聴衆がそれを聴いて学ぶという関係性が特徴です。
講演という言葉には「講義して演説する」という意味があり、ビジネスシーン、学術分野、地域のイベントなど幅広い場面で使われます。
私の友人が大学で開催された起業家の講演会に参加したところ、具体的な経営ノウハウを学べて非常に刺激を受けたと話していました。

「講演」とは知識を伝えることか!
ワシも農民から天下人に上り詰めた経験を「秀吉流・立身出世の極意」として講演してみたいもんじゃ!
きっと参加費は大盛況で完売じゃろうて!
ガハハ!
「公演」と「講演」の比較表
「公演」と「講演」の違いを表で整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 公演 | 講演 |
|---|---|---|
| 読み方 | こうえん | こうえん |
| 意味 | 演劇・音楽などを披露すること | 専門知識を話して伝えること |
| 目的 | 観客を楽しませる(娯楽) | 聴衆に学びを提供する(教育) |
| 内容 | 芸術的パフォーマンス | 知識・情報の伝達 |
| 実施者 | 俳優、歌手、演奏家など | 専門家、有識者、講師など |
| 場所 | 劇場、ホール、舞台 | 講演会場、セミナールーム |
| 例 | 歌舞伎の公演、バレエ公演 | 経営戦略の講演、環境講演 |
この表を見れば、「公演」は見て楽しむもの、「講演」は聴いて学ぶものという違いが明確になります。
✓ 公演 = 演劇・音楽・舞踊などの芸術的パフォーマンスを披露すること
✓ 講演 = 専門知識や情報を話して伝えること
✓ 公演は「見て楽しむ」、講演は「聴いて学ぶ」
✓ 目的:公演は娯楽、講演は教育・啓発
「公演」と「講演」の使い分け
「公演」と「講演」を正しく使い分けるには、その活動の本質を見極めることが重要です。
内容がエンターテイメント性を持つか教育的かで判断し、さらに目的が何かを考えれば、迷うことなく適切な言葉を選べるようになります。
ここでは、実践的な使い分けのポイントを3つの視点から詳しく解説していきます。
エンターテイメントか教育かで判断する
最もシンプルな使い分け方法は、その活動が「エンターテイメント」なのか「教育」なのかで判断することです。
エンターテイメント → 「公演」
芸術性や娯楽性が中心となる活動には「公演」を使います。
観客が視覚や聴覚で楽しむことを目的とした演劇、音楽、舞踊、お笑いなどが該当します。
✅ 正しい例:
- 「劇団四季のミュージカル公演を観に行った」
- 「ピアノリサイタルの公演チケットを購入した」
- 「落語家による単独公演が大盛況だった」
教育・啓発 → 「講演」
知識の伝達や啓発が中心となる活動には「講演」を使います。
聴衆が耳で聴いて学ぶことを目的とした話や説明が該当します。
✅ 正しい例:
- 「大学教授による環境問題の講演を聴いた」
- 「企業の代表取締役が経営戦略について講演した」
- 「医師による健康セミナーで講演が行われた」
私の同僚が以前、「著名な俳優の公演を聴きに行く」と言って周囲に笑われたことがありました。
俳優が舞台で演じるのは「公演」ですが、その俳優が講師として話をする場合は「講演」になります。
内容の性質で判断することが大切です。
目的(楽しませる/知識を伝える)で区別する
使い分けの第二のポイントは、その活動の「目的」に注目することです。
楽しませる目的 → 「公演」
観客や聴衆を楽しませること、感動させることが主な目的であれば「公演」を使います。
🎯 公演の目的:
- 芸術作品を鑑賞してもらう
- 観客に感動や喜びを提供する
- エンターテイメントとして楽しんでもらう
- 文化的・芸術的価値を共有する
例:「今回の歌舞伎公演は、伝統芸能の素晴らしさを若い世代に伝えることを目的としている」
知識を伝える目的 → 「講演」
聴衆に知識や情報を提供すること、学びや気づきを与えることが主な目的であれば「講演」を使います。
🎯 講演の目的:
- 専門知識や経験を共有する
- 聴衆の理解を深める
- 新しい視点や考え方を提示する
- 行動変容や意識改革を促す
例:「経営コンサルタントの講演では、中小企業の生き残り戦略について具体的なノウハウが語られた」
目的が複合的な場合もありますが、主たる目的が何かを考えれば判断できます。
たとえば、著名人のトークショーは娯楽要素が強ければ「公演」、教育的な内容が中心なら「講演」となります。
間違えやすいケースと正しい表現
実際の使用場面では、判断に迷うケースもあります。
ここでは間違えやすい具体例を紹介します。
ケース1:音楽家が話をする場合
❌ 間違い:「ピアニストが音楽教育について公演した」
⭕ 正しい:「ピアニストが音楽教育について講演した」
演奏するなら「公演」ですが、話をするだけなら「講演」です。
ケース2:TED Talksやプレゼンテーション
❌ 間違い:「TED Talksで起業家が公演を行った」
⭕ 正しい:「TED Talksで起業家が講演を行った」
ステージ上でのプレゼンテーションでも、知識や経験を語る場合は「講演」が適切です。
ケース3:朗読会や読み聞かせ
これは内容次第で変わります:
- 文学作品を芸術的に朗読 → 「公演」(例:詩人による朗読公演)
- 教育目的の読み聞かせ → 「講演」や「読み聞かせ会」
ケース4:学校の文化祭や発表会
- 演劇部の舞台 → 「公演」
- 卒業生による進路の話 → 「講演」
私の知人が勤める会社で、社員向けに著名な落語家を招いたイベントがありました。
落語を披露する場合は「落語公演」となりますが、その落語家が「話芸の極意」について話をする場合は「講演」になります。
同じ人物でも、何をするかによって使い分けが変わる好例です。
判断に迷ったときのチェックポイント:
- 舞台や演技があるか → あれば「公演」
- 主に話だけか → そうなら「講演」
- チケット代が「鑑賞料」か「参加費」か → 前者なら「公演」、後者なら「講演」の可能性が高い
✓ 内容で判断: エンターテイメント性があるか、教育的内容か
✓ 目的で判断: 楽しませるためか、知識を伝えるためか
✓ 迷ったとき: 舞台や演技があれば「公演」、主に話だけなら「講演」
「公演」の使い方と例文10選
「公演」は、演劇・音楽・舞踊などの芸術的なパフォーマンスを公の場で披露する際に使います。
日常会話からビジネスシーン、広報活動まで幅広く使われる言葉です。
ここでは、実際の使用場面を想定した例文を10個紹介します。
日常的な使い方の例文
日常生活で「公演」を使う場面は意外と多くあります。
友人との会話やSNSでの投稿、チケット予約など、エンターテイメントに関わる場面で自然に使えます。
例文1:演劇鑑賞 「週末に劇団の新作公演を観に行く予定だ」
例文2:音楽コンサート 「人気バンドの全国ツアー公演が地元でも開催される」
例文3:伝統芸能 「歌舞伎座で行われる六月公演のチケットを入手した」
例文4:バレエやダンス 「ロシアのバレエ団による来日公演は毎回満席になる」
例文5:お笑いライブ 「お気に入りの芸人の単独公演を初めて生で観た」
私の友人は演劇が好きで、月に2〜3回は小劇場の公演に足を運んでいます。
「公演後に俳優さんとロビーで話せるのが楽しい」と言っていましたが、小規模な劇場ならではの醍醐味だそうです。
このように、「公演」という言葉は演劇ファンやエンターテイメント好きにとって日常的に使う言葉といえます。
ビジネスシーンでの使い方
ビジネスの場面では、イベント企画、広報活動、文化事業などで「公演」が頻繁に使われます。
特に文化・エンターテイメント業界や自治体の文化振興部門では必須の用語です。
例文6:イベント企画 「今年度の文化祭では、プロの劇団による特別公演を企画している」
例文7:広報・告知 「オーケストラの定期公演について、ウェブサイトで詳細を告知する」
例文8:中止や延期の案内 「悪天候のため、野外音楽公演は翌週に延期となった」
例文9:契約や交渉 「海外アーティストの公演実現に向けて、事務所と交渉を進めている」
例文10:実績報告 「当ホールでは年間100回以上の公演を開催し、地域文化の発展に貢献している」
同僚が市の文化振興課で働いているのですが、「公演の企画から実施まで、想像以上に細かい調整が必要」と話していました。
会場の手配、出演者との契約、チケット販売、広報活動、当日の運営まで、一つの公演を成功させるには多くの関係者の協力が不可欠だそうです。
ビジネス文書では、「公演を開催する」「公演が中止になる」「公演に出演する」といった表現がよく使われます。
「講演」の使い方と例文10選
「講演」は、専門家や有識者が特定のテーマについて話をする際に使います。
ビジネス、教育、地域イベントなど、知識や情報を伝える場面で広く使われる言葉です。
ここでは、一般的な使い方からフォーマルな場面まで、実践的な例文を10個紹介します。
一般的な使い方の例文
日常生活やカジュアルな場面でも「講演」を使う機会は多くあります。
セミナーへの参加、学校行事、地域のイベントなど、身近な場面での使い方を見ていきましょう。
例文1:セミナー参加 「起業家による講演を聴いて、ビジネスのヒントを得た」
例文2:学校行事 「卒業生が母校で進路選択についての講演を行った」
例文3:地域イベント 「市民講座で、郷土史研究家による地域の歴史についての講演があった」
例文4:オンライン配信 「著名な心理学者の講演がオンラインで視聴できる」
例文5:招待や依頼 「PTAから依頼されて、子育てについての講演を引き受けた」
私の知人が地域の図書館で開催された作家の講演会に参加したところ、創作の裏話や執筆のコツを直接聞けて非常に有意義だったと喜んでいました。
「本を読むだけでは分からない作家の人柄や想いが伝わってきた」とのことで、講演には書籍やネット記事では得られない価値があるようです。
フォーマルな場面での使い方
ビジネスや公的な場面では、より丁寧な表現で「講演」が使われます。
企業研修、学会、公式イベントなどで頻繁に登場する言葉です。
例文6:企業研修 「社員研修として、外部から経営コンサルタントを招いて講演していただいた」
例文7:学会や学術会議 「国際会議において、最新の研究成果について講演する機会を得た」
例文8:式典での挨拶 「創立記念式典では、理事長による記念講演が予定されている」
例文9:依頼や打診 「貴殿には当フォーラムにおいて、環境政策についてご講演いただきたく存じます」
例文10:報告や実績 「昨年度は全国の大学や企業で計50回の講演を行い、延べ5,000名の方々にお話しする機会をいただいた」
同僚が勤める企業では、四半期ごとに外部講師を招いて講演会を開催しているそうです。
「業界の第一人者から直接話を聞けるのは貴重な機会で、社員のモチベーション向上にもつながっている」と話していました。
特にビジネスシーンでは、「ご講演いただく」「講演を賜る」といった敬語表現を使うことで、講師への敬意を示すことができます。
また、「講演依頼」「講演料」「講演内容」など、講演に関連する言葉も業務上よく使われます。
【クイズ】「公演」と「講演」どっち?
ここまで学んだ知識を活かして、実際に使い分けができるかクイズで確認してみましょう。
3つの問題に挑戦して、あなたの理解度をチェックしてください。
クイズ1:「著名な作家による○○会が開催された」
【問題】
「著名な作家による○○会が開催された」の○○に入るのはどちらでしょうか?
A. 公演
B. 講演
✅【正解】
B. 講演
【解説】
作家が自身の創作活動や文学について「話をする」場合は「講演」が正解です。
作家が知識や経験を語り、聴衆がそれを聴いて学ぶという関係性だからです。
ただし、作家が自作の朗読を芸術的に披露する場合は「朗読公演」となることもあります。
しかし一般的に「作家による○○会」といえば、作家が話をするイベントを指すため「講演会」が適切です。
💡 使用例:
「ノーベル賞作家による講演会には、全国から文学ファンが集まった」
クイズ2:「バレエ団の○○を鑑賞した」
【問題】
「バレエ団の○○を鑑賞した」の○○に入るのはどちらでしょうか?
A. 公演
B. 講演
✅【正解】A. 公演
【解説】
バレエは舞踊という芸術的パフォーマンスです。
観客が視覚的に「鑑賞する」ものであり、エンターテイメント性が中心となるため「公演」が正解です。
「鑑賞した」という動詞もヒントになります。
芸術作品を見て楽しむ場合は「鑑賞」、話を聴いて学ぶ場合は「聴講」という言葉を使い分けます。
💡 使用例:
「ロシアのバレエ団による白鳥の湖の公演は圧巻だった」
クイズ3:「経営戦略についての○○を聴いた」
【問題】
「経営戦略についての○○を聴いた」の○○に入るのはどちらでしょうか?
A. 公演
B. 講演
✅【正解】
B. 講演
【解説】
経営戦略という専門的な知識について「話を聴く」わけですから、「講演」が正解です。ビジネスに関する知識や情報を伝達する行為は、教育的・啓発的な内容に該当します。
経営者やコンサルタントがビジネスについて語る場合は、必ず「講演」を使います。
「経営戦略の公演」とは言いません。
💡 使用例:
「有名経営者による経営戦略の講演で、新しいビジネスモデルのヒントを得た」
🎯 クイズのポイント整理:
✅ 芸術的パフォーマンス(演劇・音楽・舞踊など) → 公演
✅ 知識や情報を話す(ビジネス・学術・教育など) → 講演
✅ 「鑑賞する」なら公演、「聴講する」なら講演
これらのクイズを通じて、実際の使用場面での判断力が身についたはずです。
迷ったときは、「エンターテイメントか教育か」という基本原則に立ち返って考えましょう。
「公演」と「講演」に関するQ&A
「公演」と「講演」の使い分けについて、よくある疑問や質問をQ&A形式でまとめました。
実際の使用場面で迷いやすいポイントを5つ取り上げて、わかりやすく解説します。
Q1. 学校の発表会は「公演」と「講演」どちらを使う?
A. 内容によって使い分けます
学校の発表会では、何を発表するかによって使い分けが変わります。
「公演」を使う場合:
🎭 演劇部による劇の発表 → 「演劇公演」
🎵 吹奏楽部による演奏会 → 「演奏公演」
💃 ダンス部による発表 → 「ダンス公演」
芸術的なパフォーマンスを披露する場合は「公演」を使います。
「講演」を使う場合:
📢 卒業生による進路の話 → 「進路講演会」
📚 専門家による教育講話 → 「教育講演」
💼 起業家による体験談 → 「キャリア講演」
知識や経験を話で伝える場合は「講演」を使います。
「発表会」でOKな場合:
多くの学校行事では、単に「学習発表会」「文化発表会」と呼ぶことも多く、無理に「公演」「講演」を使う必要はありません。
研究発表やプレゼンテーションは「発表」で十分です。
Q2. ビジネス文書で間違えて使うと失礼になる?
A. 場合によっては失礼になる可能性があります
ビジネス文書やメールで「公演」と「講演」を間違えると、相手に誤解を与えたり、失礼になることがあります。
失礼になる典型例:
❌ 「先生の素晴らしい公演を拝聴させていただきました」 → 講演を「公演」と書くと、まるでショーを見たかのような印象になり、専門家への敬意が欠けます。
⭕ 「先生の素晴らしい講演を拝聴させていただきました」 → 正しい表現です。
注意すべき場面:
📧 講演依頼のメール → 「ご講演いただきたく」
📄 イベント告知文 → 内容に応じて正確に
🎫 チケット販売 → 「公演チケット」「講演会参加費」
私の同僚が以前、大学教授への講演依頼メールで「公演のお願い」と書いてしまい、上司から指摘を受けたことがありました。
幸い送信前に気づいて修正できましたが、「一文字違いでも印象が大きく変わる」と学んだそうです。
特に依頼文書や正式な案内では、正確な用語を使うことが信頼につながります。
Q3. 「上演」「口演」との違いは?
A. 「上演」は演劇・映画、「口演」は口頭での演じ方です
「公演」「講演」に似た言葉として「上演」「口演」があります。
それぞれ使う場面が異なります。
上演(じょうえん):
演劇や映画を舞台・劇場で上映することを指します。
- 例:「シェイクスピア劇を上演する」
- 例:「映画の上演時間は2時間です」
- 「公演」との違い:「上演」は作品を演じること自体に焦点があり、「公演」はイベント全体を指す傾向があります。
口演(こうえん):
講談や落語などを口頭で演じることを指します。
あまり一般的には使われません。
- 例:「講談師による口演」
- 例:「古典落語の口演」
- 使用頻度は低く、専門的な場面で使われます。
使い分けの整理:
- 公演 = 芸術的パフォーマンス全般のイベント
- 講演 = 知識を話で伝える行為
- 上演 = 演劇・映画作品を演じること
- 口演 = 講談・落語を口頭で演じること
日常会話では「公演」と「講演」を正しく使い分けられれば十分です。
Q4. 英語ではどのように表現する?
A. 「公演」と「講演」は異なる英単語を使います
英語では「公演」と「講演」を明確に区別した表現があります。
「公演」の英語表現:
🎭 performance(パフォーマンス)
- 例:"I went to a theater performance."
(演劇公演を観に行った) - 例:"The ballet performance was amazing."
(バレエ公演は素晴らしかった)
🎵 concert(コンサート)
※音楽の場合
- 例:"a rock concert"
(ロックコンサート)
🎪 show(ショー)
※総称的に
- 例:"a Broadway show"
(ブロードウェイショー)
「講演」の英語表現:
📢 lecture(レクチャー)
- 例:"He gave a lecture on economics."
(彼は経済学について講演した)
📢 speech(スピーチ)
- 例:"The CEO delivered a speech."
(CEOがスピーチをした)
📢 talk(トーク)
※カジュアル
- 例:"TED Talk"
(TEDトーク)
📢 presentation(プレゼンテーション)
- 例:"a business presentation"
(ビジネスプレゼンテーション)
英語でも日本語と同様に、エンターテイメント系と教育系で明確に言葉を使い分けています。
Q5. TED Talksは「公演」「講演」どちら?
A. 「講演」が正しい表現です
TED Talksは「講演」に分類されます。
理由を詳しく見ていきましょう。
TED Talksが「講演」である理由:
✅ スピーカーが知識や経験を「話して」伝える
✅ 聴衆が学びや気づきを得ることが目的
✅ 教育的・啓発的な内容が中心
✅ 英語では"TED Talk"や"TED lecture"と呼ばれる
TED Talksはステージ上でプレゼンテーションを行いますが、その本質は「アイデアを広める」ための知識共有です。
そのため、エンターテイメントである「公演」ではなく、教育的な「講演」に該当します。
使用例:
⭕ 「TEDで環境問題についての講演を視聴した」
❌ 「TEDで環境問題についての公演を視聴した」
同様に「講演」となるもの:
📊 ビジネスカンファレンスでのプレゼン
🎓 大学での特別講義
💡 イノベーションサミットでのスピーチ
友人がTEDxイベントに登壇した際、「緊張したけど、自分の経験が誰かの役に立てばと思って話した」と言っていました。
TEDは確かにステージパフォーマンスの要素もありますが、目的は「価値ある知識の共有」であり、まさに講演の本質を体現しています。
✓ 「公演」の「公」= 公(おおやけ)に芸術を演じる → パフォーマンス
✓ 「講演」の「講」= 講義して演説する → 知識の伝達
✓ チケットを買って「鑑賞」するなら公演
✓ 参加費を払って「聴講」するなら講演
✓ ビジネス文書では特に注意!間違えると失礼になる場合も
まとめ
「公演」と「講演」は同じ「こうえん」と読みますが、意味と使い方はまったく異なります。
「公演」は演劇・音楽・舞踊などの芸術的パフォーマンスを公の場で披露することで、観客を楽しませるのが目的です。
一方、「講演」は専門家が知識や情報を話して伝えることで、聴衆に学びを提供するのが目的です。
使い分けのポイントは、エンターテイメントか教育かで判断することです。
「見て楽しむ」なら公演、「聴いて学ぶ」なら講演と覚えておきましょう。
ビジネス文書やメールでは、間違えると相手に失礼になる場合もあるため、正確な使い分けが大切です。
この記事で紹介した例文やクイズを参考に、日常生活やビジネスシーンで自信を持って使い分けてください。



















