
「そうぞう」と入力して変換すると、「想像」と「創造」の2つが表示されて、どちらを使えばいいか迷ったことはありませんか?
同じ読み方なのに意味が全く異なるこの2つの言葉は、使い分けを間違えると相手に誤解を与えてしまう可能性があります。

わしも手紙を書くとき、「天下を『そうぞう』する」って書こうとしたら迷ったぞ!
想像か創造か、どっちじゃ!?
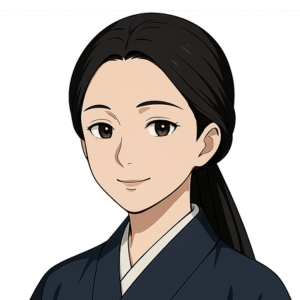
信長さん、それはね、頭で描くだけなら「想像」、実際に作り上げるなら「創造」よ。
あなたの場合は天下を実際に築いたんだから「創造」が正解ね!
これから、私のお仲間が登場しますので、どんな話しをされるのか楽しみにしてね♪
「想像」は頭の中で思い描くこと(imagination)。
「創造」は新しいものを実際に生み出すこと(creation)。
行動を伴わないなら「想像」、形になるなら「創造」を使えばOKです。
✅ この記事でわかること
- 「想像」と「創造」の基本的な意味の違い
- 実際の使い分け方と具体的な例文
- 「想像力」と「創造力」の違い
- 迷いやすいシーン別の正しい使い方
- 類義語・対義語とよくある疑問への回答
この記事では、比較表や豊富な例文を使って、誰でも簡単に理解できるように解説しています。
ビジネスメールや文章作成で自信を持って使い分けられるよう、ぜひ最後までご覧ください。
「想像」と「創造」の違いを簡単に解説
「そうぞう」という同じ読み方をする「想像」と「創造」。日常会話では音で聞き分けることができないため、メールや文章を書くときに「あれ、どっちだったかな?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この2つの言葉には明確な違いがあり、使い分けを間違えると相手に誤解を与えてしまうこともあります。
「想像」の意味とは
「想像」は、実際には存在しないものや目に見えないものを、心の中で思い描くことを意味します。
英語では「imagination(イマジネーション)」と表現されます。
具体的には、以下のような場面で使われます:
🔹 未来や過去の出来事を頭の中でイメージする
🔹 他人の気持ちや立場を推測する
🔹 物語やストーリーを頭の中で描く
🔹 まだ見ぬ景色や状況を思い浮かべる
たとえば、友人から「北海道旅行に行ってきた」と聞いたときに、雪景色や海鮮料理を頭の中で思い浮かべるのが「想像」です。
また、会社の同僚が元気がないときに「何か悩みがあるのかな」と相手の気持ちを推し量るのも想像の一種といえます。
想像は「頭の中だけで完結する」のが特徴で、実際に何かを作り出したり行動したりする必要はありません。

わしも「新しい日本」を想像しちょった時は、頭の中だけじゃったが…
気づいたら船に乗って日本中を駆け回っちょったぜよ!
想像は行動のスタート地点っちゅうことじゃな!
「想像」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「創造」の意味とは
「創造」は、今まで存在しなかった新しいものを作り出すことを意味します。
英語では「creation(クリエーション)」と表現されます。
具体的には、以下のような場面で使われます:
🔹 新しい商品やサービスを開発する
🔹 芸術作品(絵画・音楽・小説など)を生み出す
🔹 新しいアイデアやシステムを構築する
🔹 これまでにないデザインや技術を発明する
たとえば、デザイナーが新しいファッションブランドを立ち上げる、プログラマーが画期的なアプリを開発する、料理人がオリジナルレシピを考案するといった行為が「創造」にあたります。
私の職場の後輩が新しい業務マニュアルを一から作成したとき、上司から「素晴らしい創造だね」と褒められていました。
これは単に既存のものを真似たのではなく、独自の工夫を加えて新しい価値を生み出したからです。
創造は「実際に形にする・行動する」ことが前提となるのが特徴です。
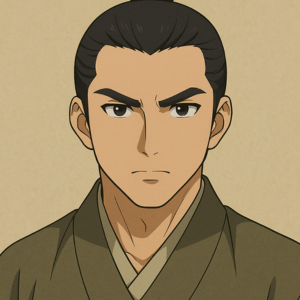
わしも江戸幕府という新しい仕組みを創造したが、想像だけなら一瞬じゃ。
実際に形にするには何十年もかかったぞ!
天下を取るまで70年待ったわしが言うんじゃ、創造には忍耐が必要ってことじゃな!
「創造」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
【比較表】「想像」と「創造」の違い一覧
「想像」と「創造」の違いを表にまとめると、以下のようになります:
| 比較項目 | 想像 | 創造 |
|---|---|---|
| 意味 | 心の中で思い描くこと | 新しいものを作り出すこと |
| 英語表現 | imagination | creation |
| 行動の有無 | 頭の中だけで完結 | 実際に形にする・行動する |
| 具体例 | 未来を想像する 相手の気持ちを想像する |
新商品を創造する 芸術作品を創造する |
| 結果 | 目に見えない(頭の中のイメージ) | 目に見える(具体的な成果物) |
この表を見れば、「想像は思い描くこと、創造は作り出すこと」という根本的な違いが一目で分かります。
✓ 想像 = 頭の中で思い描くこと(imagination)
✓ 創造 = 新しいものを作り出すこと(creation)
✓ 想像は行動不要、創造は実際に形にする
✓ 迷ったら「イマジンかクリエイトか」で判断
「想像」の使い方と例文
「想像」は頭の中で思い描く行為を表すため、実際に目に見えないものや未来の出来事、他者の感情などをイメージする場面で使われます。
ここでは「想像」を使う具体的なシーンと、実際の例文をご紹介します。
「想像」を使う場面
「想像」は主に以下のような場面で使用されます:
🔹 未来や過去の出来事を思い描くとき
まだ起きていないことや、すでに終わったことを頭の中でイメージする場面です。
「10年後の自分を想像する」「昔の風景を想像する」といった使い方をします。
🔹 相手の気持ちや状況を推測するとき
目の前にいない人の感情や置かれている状況を考える場面です。
「彼の気持ちを想像する」「被災地の様子を想像する」のように使います。
🔹 架空のストーリーや世界を思い浮かべるとき
小説や映画の世界、ファンタジーの設定などを頭の中で描く場面です。
「ドラゴンがいる世界を想像する」「主人公の冒険を想像する」という形で使われます。
🔹 まだ見ぬものをイメージするとき
行ったことのない場所や、経験したことのないことを思い描く場面です。
「海外の生活を想像する」「新しい趣味を始めたときのことを想像する」といった表現になります。
友人のデザイナーが「クライアントの要望を聞いて、完成形を想像してからラフスケッチを描く」と話していました。
この場合、まだ実際には存在しない作品を頭の中で思い描いているため、「想像」が適切です。

周りは「無理じゃろ」言うとったけど、想像せんかったら何も始まらんけぇのう!
まぁ、想像だけで終わっとったら今でも草履磨いとったかもしれんがな!
「想像」の例文5選
実際に「想像」を使った例文を見てみましょう:
例文1:未来を思い描く
✏️ 「5年後の自分を想像してみると、管理職として活躍している姿が浮かんできた。」
例文2:相手の気持ちを推測する
✏️ 「彼女が試験に落ちたと聞いて、どれほど悔しい思いをしているか想像できた。」
例文3:架空の世界を思い浮かべる
✏️ 「小説を読みながら、登場人物たちが暮らす中世ヨーロッパの街並みを想像した。」
例文4:未経験のことをイメージする
✏️ 「子どもが生まれたら、どんな毎日になるのか想像するだけでワクワクする。」
例文5:状況を推測する
✏️ 「ニュースを見て、被災地の方々の苦労を想像すると胸が痛んだ。」
これらの例文に共通しているのは、「実際には目の前にないものを頭の中で思い描いている」という点です。
どれも具体的な行動や制作活動を伴わず、心の中でイメージする場面で使われています。
「創造」の使い方と例文
「創造」は新しいものを実際に作り出す行為を表すため、芸術活動やビジネス、発明など、具体的な成果物が生まれる場面で使われます。
ここでは「創造」を使う具体的なシーンと、実際の例文をご紹介します。
「創造」を使う場面
「創造」は主に以下のような場面で使用されます:
🔹 芸術作品を生み出すとき
絵画、音楽、小説、映画など、アーティストが新しい作品を制作する場面です。
「新曲を創造する」「オリジナル作品を創造する」といった使い方をします。
🔹 新しいビジネスやサービスを開発するとき
企業が新商品を開発したり、これまでにないサービスを立ち上げたりする場面です。
「革新的なアプリを創造する」「新しいビジネスモデルを創造する」のように使います。
🔹 発明や技術革新を行うとき
科学者やエンジニアが新しい技術や製品を生み出す場面です。
「省エネ技術を創造する」「画期的な医療機器を創造する」という形で使われます。
🔹 独自のシステムや価値を構築するとき
組織の仕組みや文化、教育プログラムなど、形のあるなしに関わらず新しい価値を生み出す場面です。
「企業文化を創造する」「新しい学習メソッドを創造する」といった表現になります。
私の知人の料理人が独立して自分の店を開いたとき、「伝統的な和食と西洋料理を融合させた新しいジャンルを創造したい」と語っていました。
単に既存の料理を真似るのではなく、オリジナリティのある料理を作り出すという強い意志が「創造」という言葉に込められています。
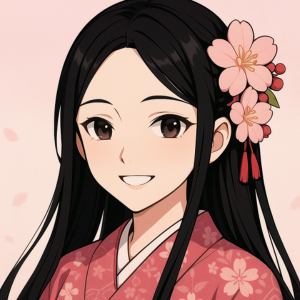
「花の色は移りにけりな」って詠んだ時も、ただ想像してただけじゃなくて実際に言葉として形にしたから創造だったのね。
でも当時は「美人が和歌詠んでる」ってだけで話題になっちゃって…
創造より顔で評価されるのって複雑だわ!
「創造」の例文5選
実際に「創造」を使った例文を見てみましょう:
例文1:芸術作品を生み出す
✏️ 「彼女は3年かけて、誰も見たことがない世界観の絵本を創造した。」
例文2:新しいサービスを開発する
✏️ 「このスタートアップは、地方と都市をつなぐ新しいマッチングサービスを創造している。」
例文3:技術革新を実現する
✏️ 「研究チームは環境に優しい次世代エネルギーの創造に成功した。」
例文4:ビジネスモデルを構築する
✏️ 「彼はゼロから独自のビジネスモデルを創造し、業界に新風を吹き込んだ。」
例文5:文化や価値を生み出す
✏️ 「このプロジェクトは、地域住民が協力し合う新しいコミュニティ文化を創造した。」
これらの例文に共通しているのは、「実際に形あるもの・価値あるものを生み出している」という点です。
どれも具体的な行動や制作活動を伴い、新しい成果物や仕組みが誕生する場面で使われています。
「想像」と「創造」の使い分け方
ここまで「想像」と「創造」の意味や使い方を見てきましたが、実際の文章では「どちらを使えばいいのか迷う」という場面が少なくありません。
特に「そうぞうりょく」「未来をそうぞうする」といったフレーズは、状況によって使い分けが変わるため注意が必要です。
ここでは、迷いやすい具体的なシーンを取り上げて、正しい使い分け方を解説します。
迷いやすいシーン①:「そうぞうりょく」はどっち?
「そうぞうりょく」という言葉は、「想像力」と「創造力」の両方が存在します。
この2つは似ているようで意味が異なるため、文脈に応じて使い分ける必要があります。
想像力を使う場合
頭の中で思い描く能力を指すときは「想像力」を使います。
✅ 「彼は想像力が豊かで、相手の気持ちをすぐに理解できる。」
✅ 「小説を読むと想像力が刺激される。」
✅ 「子どもの頃は想像力を使って、ごっこ遊びに夢中になった。」
これらは「頭の中でイメージする力」を表しているため、「想像力」が正解です。
創造力を使う場合
新しいものを生み出す能力を指すときは「創造力」を使います。
✅ 「彼女は創造力に優れ、次々と斬新なデザインを考案する。」
✅ 「ビジネスでは創造力が競争力の源となる。」
✅ 「このワークショップは子どもの創造力を育むことを目的としている。」
これらは「何かを作り出す力」を表しているため、「創造力」が正解です。
会社の先輩エンジニアが「プログラミングには想像力も創造力も両方必要だよ」と話していました。
ユーザーの使い方を想像しながら、新しい機能を創造していくということです。
このように、両方の力が求められる場面も多くあります。
迷いやすいシーン②:「未来をそうぞうする」はどっち?
「未来をそうぞうする」というフレーズは、状況によって「想像」と「創造」のどちらも使える可能性があります。
違いを理解して正しく使い分けましょう。
「未来を想像する」を使う場合
これから起こるであろうことを頭の中で思い描くときは「想像」を使います。
✅ 「10年後の自分を想像してみる。」
✅ 「彼女は結婚生活の未来を想像して、幸せな気持ちになった。」
✅ 「AIが普及した未来を想像すると、働き方が大きく変わりそうだ。」
これらは「まだ実現していない未来を頭の中でイメージしている」だけなので、「想像」が適切です。
「未来を創造する」を使う場合
自分たちの手で新しい未来を作り出していくときは「創造」を使います。
✅ 「私たちは持続可能な社会の未来を創造する使命がある。」
✅ 「この技術革新が、新しい産業の未来を創造するだろう。」
✅ 「若者たちが力を合わせて、希望に満ちた未来を創造していく。」
これらは「実際に行動して未来を作り出す」という意味が込められているため、「創造」が正解です。
単に「思い描く」だけなら想像、「自ら作り出す」なら創造と覚えておくと分かりやすいでしょう。
迷いやすいシーン③:「新しい世界をそうぞうする」はどっち?
「新しい世界をそうぞうする」も、文脈によって使い分けが変わる典型的な例です。
「新しい世界を想像する」を使う場合
架空の世界や、まだ見ぬ世界を頭の中で思い描くときは「想像」を使います。
✅ 「SF小説を読んで、宇宙に広がる新しい世界を想像した。」
✅ 「彼は目を閉じて、理想の社会という新しい世界を想像してみた。」
✅ 「ファンタジーゲームで、魔法が使える新しい世界を想像するのが好きだ。」
これらは「頭の中だけでイメージしている」ため、「想像」が適切です。
「新しい世界を創造する」を使う場合
実際に新しい価値観や仕組み、作品世界などを作り出すときは「創造」を使います。
✅ 「このゲーム開発チームは、プレイヤーを魅了する新しい世界を創造した。」
✅ 「起業家たちは、従来の常識を覆す新しいビジネスの世界を創造している。」
✅ 「アーティストは独自の感性で、誰も見たことがない新しい芸術世界を創造する。」
これらは「実際に形にして世に出している」ため、「創造」が正解です。
友人のゲームクリエイターが「まず頭の中で世界を想像して、それをゲームとして創造する」と説明してくれました。
想像が第一段階で、創造が第二段階というイメージです。
✓ 「そうぞうりょく」→ 思い描く力なら想像力、作り出す力なら創造力
✓ 「未来をそうぞう」→ イメージするだけなら想像、実現するなら創造
✓ 「新しい世界をそうぞう」→ 頭の中だけなら想像、形にするなら創造
✓ 想像は第一段階、創造は第二段階と考えるとわかりやすい
「想像力」と「創造力」の違い
「想像」と「創造」の違いを理解したところで、次は「想像力」と「創造力」という言葉の違いについて見ていきましょう。
この2つも混同されやすいですが、それぞれが指す能力には明確な違いがあります。
ビジネスシーンや教育現場でもよく使われる言葉なので、正しく理解しておくことが大切です。
「想像力」とは
「想像力」は、目に見えないものや実在しないものを、頭の中で思い描く力のことです。
英語では「imagination」と表現されます。
想像力が高い人には、以下のような特徴があります:
🔹 他人の気持ちや立場を推測するのが得意
相手の表情や言葉から感情を読み取り、「今どんな気持ちなんだろう」と考えることができます。
🔹 まだ起きていないことをイメージできる
「もしこうなったら」「あの人ならこう考えるだろう」といった仮定の状況を具体的に思い描けます。
🔹 物語や世界観を豊かに思い浮かべられる
小説を読んだり映画を見たりしたときに、登場人物の心情や背景をリアルにイメージできます。
🔹 リスクや問題を事前に予測できる
「この計画を進めたら、こんな問題が起きるかもしれない」と先回りして考えられます。
想像力はビジネスでも重要です。
営業職なら「お客様は何に困っているのか」を想像する力が必要ですし、マーケティング担当なら「消費者がどう感じるか」を想像することで効果的な施策を考えられます。
私の同僚で営業成績がトップの人がいるのですが、彼女は「お客様の立場になって想像することを大切にしている」と話していました。
相手の悩みや求めているものを想像することで、的確な提案ができるそうです。
「創造力」とは
「創造力」は、今まで存在しなかった新しいものを生み出す力のことです。
英語では「creativity」と表現されます。
創造力が高い人には、以下のような特徴があります:
🔹 独創的なアイデアを考え出せる
既存の枠にとらわれず、「こんな方法はどうだろう」と斬新な発想ができます。
🔹 異なる要素を組み合わせて新しい価値を生む
一見関係のないものを結びつけて、革新的なサービスや商品を作り出せます。
🔹 問題解決のための新しいアプローチを見つける
従来のやり方では解決できない課題に対して、まったく新しい方法を提案できます。
🔹 実際に形にして世に送り出せる
頭の中のアイデアを具体的な作品やサービスとして実現できます。
創造力はクリエイティブな職種だけでなく、あらゆる分野で求められています。
エンジニアなら新しい技術を開発する創造力、経営者なら新しいビジネスモデルを構築する創造力、教師なら効果的な教育方法を編み出す創造力が必要です。
友人のWebデザイナーが「クライアントの要望を聞いて想像を膨らませ、それを創造力で形にしていく」と表現していました。
想像力でイメージを描き、創造力でそれを実際のデザインとして作り上げるという流れです。
ビジネスではどちらが重視される?
結論から言うと、ビジネスでは「創造力」がより重視される傾向にあります。
ただし、想像力も非常に重要で、実際には両方の力が必要とされています。
創造力が重視される理由
現代のビジネス環境では、競合との差別化や新しい価値の創出が求められます。
そのため、以下のような場面で創造力が評価されます:
✓ 新商品・新サービスの開発
市場にないものを生み出す創造力が競争優位性につながります。
✓ 業務プロセスの改善
効率化や生産性向上のために、新しい仕組みを創造することが求められます。
✓ イノベーションの推進
企業の成長には、従来の枠を超えた創造的な取り組みが不可欠です。
想像力も欠かせない理由
ただし、創造力を発揮するためには、その土台として想像力が必要です:
✓ 顧客ニーズの理解
お客様が何を求めているかを想像できなければ、的外れな商品を作ってしまいます。
✓ リスク管理
新しいプロジェクトを始める前に、起こりうる問題を想像することで失敗を防げます。
✓ チームワークの向上
メンバーの気持ちや状況を想像できる人は、円滑なコミュニケーションが取れます。
職種によっても違いがあります。
営業職やカスタマーサポートでは「想像力」がより重要ですし、商品開発やマーケティング部門では「創造力」が強く求められます。
理想的なのは、想像力で未来や相手の気持ちを思い描き、創造力でそれを実現するというサイクルです。
両方をバランスよく持つことで、ビジネスパーソンとしての価値が高まります。
✓ 想像力 = 相手の気持ちや未来を思い描く力
✓ 創造力 = 新しい価値やアイデアを生み出す力
✓ ビジネスでは創造力がより重視される傾向
✓ 理想は想像力で描き、創造力で実現するサイクル
「想像」の類義語・対義語
「想像」という言葉をより深く理解するために、似た意味を持つ類義語と、反対の意味を持つ対義語を見ていきましょう。
類義語を知ることで表現の幅が広がり、対義語を知ることで言葉の本質的な意味がより明確になります。
「想像」の類義語
「想像」と似た意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります:
🔹 推測(すいそく)
ある情報をもとに、事実や結果を予想すること。
例:「彼の表情から、試験に落ちたのではないかと推測した。」
🔹 予想(よそう)
これから起こることを前もって考えること。
例:「明日の天気を予想する。」
🔹 空想(くうそう)
現実にはありえないことを自由に思い描くこと。想像よりも非現実的なニュアンスが強い。
例:「子どもの頃は、宇宙人と友達になる空想をよくしていた。」
🔹 妄想(もうそう)
根拠のない非現実的なことを思い込むこと。ネガティブな意味合いで使われることが多い。
例:「彼は自分が天才だという妄想に囚われている。」
🔹 イメージ
頭の中で思い浮かべる像や印象。カタカナ語として日常的に使われる。
例:「完成形をイメージしてから作業に取りかかる。」
🔹 思い描く(おもいえがく)
心の中で何かの姿や様子を想像すること。
例:「理想の家庭を思い描く。」
これらの類義語の中で、「想像」に最も近いのは「イメージ」や「思い描く」です。
「推測」や「予想」は論理的な思考が伴う点で少し異なり、「空想」や「妄想」は現実離れの度合いが強い点で区別されます。
「想像」の対義語
「想像」の対義語として挙げられるのは、以下のような言葉です:
🔹 現実(げんじつ)
実際に存在するもの、起きていること。
想像とは対照的に、目の前にある事実を指す。
例:「夢と現実のギャップに悩む。」
🔹 実際(じっさい)
本当のこと、事実そのもの。
想像や予想ではなく、実在するものを表す。
例:「想像していたよりも、実際の作業は大変だった。」
🔹 事実(じじつ)
本当にあったこと、真実。想像や推測とは異なり、確かな根拠がある。
例:「それは単なる想像ではなく、事実として確認されている。」
🔹 体験(たいけん)
実際に自分で経験すること。
頭の中で思い描くのではなく、身をもって感じること。
例:「想像するだけでなく、実際に海外生活を体験してみたい。」
「想像」が「頭の中だけで思い描くこと」であるのに対し、これらの対義語は「実際に存在するもの・起きていること」を表します。
「想像を現実にする」「想像と実際は違った」といった形で、対義語と組み合わせて使われることも多くあります。
私の知人が「想像だけで満足せず、実際に行動して体験することが大切だ」とよく言っています。
想像は第一歩として重要ですが、それを現実に変えていくことで人生が豊かになるという意味です。
「創造」の類義語・対義語
「創造」という言葉の理解を深めるために、似た意味を持つ類義語と、反対の意味を持つ対義語を確認しましょう。
類義語を知ることで語彙力が高まり、対義語を理解することで「創造」の本質的な意味がより鮮明になります。
「創造」の類義語
「創造」と似た意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります:
🔹 創作(そうさく)
芸術作品や文学作品などを作ること。
主に芸術分野で使われる。
例:「彼女は毎日、短編小説の創作に励んでいる。」
🔹 製作(せいさく)
物を作ること。映画や番組、工芸品などを作る場面で使われる。
例:「この映画は3年かけて製作された。」
🔹 制作(せいさく)
芸術作品やデザイン、コンテンツなどを作ること。
「製作」よりも芸術性が高い印象。
例:「Webサイトの制作を依頼する。」
🔹 生成(せいせい)
新しいものが生まれること、作り出されること。
自然発生的なニュアンスもある。
例:「AIが自動的に文章を生成する。」
🔹 産出(さんしゅつ)
物を作り出すこと、生産すること。
工業製品や資源などに使われることが多い。
例:「この地域は良質なワインを産出している。」
🔹 発明(はつめい)
今までになかった技術や道具を新しく作り出すこと。
例:「エジソンは電球を発明した。」
🔹 クリエイト
英語由来のカタカナ語で、「創造する」「作り出す」という意味。
現代的な響きがある。
例:「新しい価値をクリエイトする。」
これらの類義語の中で、「創造」に最も近いのは「創作」や「クリエイト」です。
「製作」や「制作」は具体的な物や作品を作る場面で使われ、「発明」は特に技術的な革新を指します。
「創造」の対義語
「創造」の対義語として挙げられるのは、以下のような言葉です:
🔹 模倣(もほう)
既存のものを真似ること。
オリジナリティがなく、他人の作品や方法をそのまま使うこと。
例:「独創性がなく、他社製品の模倣に過ぎない。」
🔹 模写(もしゃ)
絵や文章などを、見本通りにそのまま写すこと。
例:「美術の授業で、名画を模写した。」
🔹 複製(ふくせい)
既存のものをコピーして、同じものを作ること。
例:「この絵画は原作の複製です。」
🔹 踏襲(とうしゅう)
前例や既存の方法をそのまま受け継ぐこと。
新しいものを生み出さない姿勢。
例:「従来のやり方を踏襲するだけでは、イノベーションは生まれない。」
🔹 破壊(はかい)
既存のものを壊すこと。
創造の反対として、物理的・概念的に何かを壊す行為。
例:「古い建物を破壊して、新しいビルを建てる。」
🔹 保守(ほしゅ)
既存の状態を維持すること。
新しいものを作り出すのではなく、現状を守る姿勢。
例:「革新ではなく保守を重視する方針だ。」
「創造」が「新しいものを生み出すこと」であるのに対し、これらの対義語は「既存のものを真似る・維持する・壊す」ことを表します。
特に「模倣」は創造と対比される代表的な言葉で、「模倣ではなく創造を目指す」といった形でよく使われます。
会社の上司が新入社員に「最初は先輩の仕事を模倣して学び、慣れてきたら自分なりの創造を加えていくといい」とアドバイスしていました。
模倣から始めて創造へと発展させていくという成長のステップです。
「想像」と「創造」に関するQ&A
ここまで「想像」と「創造」の違いについて詳しく見てきましたが、まだ疑問に感じる点があるかもしれません。
ここでは、読者の方からよく寄せられる質問を5つピックアップして回答します。
言葉の使い方で迷ったときの参考にしてください。
Q1. 「想造」という漢字は存在する?
A. 「想造」という言葉は、正式な日本語としては存在しません。
「そうぞう」と入力して変換すると、多くの場合「想像」と「創造」の2つが候補として表示されます。
しかし、「想造」という漢字の組み合わせは、国語辞典や漢字辞典には載っていない造語です。
ただし、インターネット上では「想造」という表記を見かけることがあります。
これは以下のような理由が考えられます:
🔹 変換ミスや誤字
「想像」と打ちたかったのに、誤って「想造」になってしまったケース。
🔹 企業名や商品名としての造語
「想像」と「創造」を組み合わせた意味で、あえて「想造」という造語を使っている場合。
🔹 独自の概念を表現するための造語
「想像しながら創造する」という意味を込めて、新しく作られた言葉。
正式な文章や仕事のメールでは、必ず「想像」か「創造」のどちらかを使うようにしましょう。
「想造」と書いてしまうと、誤字だと思われる可能性が高いです。
私の後輩が取引先に送ったメールで「想造力を発揮して」と書いてしまい、上司から「これは誤字だから訂正メールを送りなさい」と指摘されていました。
正しくは「想像力」か「創造力」のどちらかです。
Q2. 英語では「想像」と「創造」はどう違う?
A. 英語では「想像」は「imagination」、「創造」は「creation」と明確に区別されます。
日本語では同じ「そうぞう」という音で混同しやすいですが、英語では発音も綴りもまったく異なるため、間違えることはほとんどありません。
想像 = Imagination(イマジネーション)
🔹 動詞形:imagine(想像する)
🔹 形容詞形:imaginative(想像力豊かな)
🔹 例文:「Use your imagination.(想像力を使いなさい)」
創造 = Creation(クリエーション)
🔹 動詞形:create(創造する)
🔹 形容詞形:creative(創造的な)
🔹 例文:「The creation of this artwork took three years.(この芸術作品の創造には3年かかった)」
英語圏のビジネスシーンでも、日本と同様に「creativity(創造性)」が重視されます。
一方、「imagination」は子どもの教育やストーリーテリングの文脈でよく使われます。
ちなみに、「イマジネーション」「クリエーション」「クリエイティブ」といったカタカナ語は、日本語でも頻繁に使われていますね。
英語の意味を知っておくと、カタカナ語を使う際にも正確に使い分けられるようになります。
Q3. 「想像」と「創造」を間違えやすい理由は?
A. 同音異義語であること、そして両方とも抽象的な概念であることが主な理由です。
「想像」と「創造」を間違えやすい理由は、いくつか挙げられます:
🔹 理由1:同じ読み方(同音異義語)
どちらも「そうぞう」と読むため、耳で聞いただけでは区別がつきません。
会話では問題なくても、文章にする際に迷ってしまいます。
🔹 理由2:似た漢字が含まれている
「想」も「創」も、どちらも「考える・生み出す」といった意味を持つ漢字です。
パッと見た印象が似ているため、混同しやすくなります。
🔹 理由3:関連性が深い概念
想像と創造は、実際には深く結びついた概念です。
「想像したものを創造する」というように、想像が創造の出発点になることも多いため、境界線が曖昧に感じられます。
🔹 理由4:日常であまり意識しない
普段の会話では音で判断できるため、明確に区別する必要がありません。
そのため、いざ文章を書くときに「どっちだっけ?」となってしまいます。
間違いを防ぐコツは、「頭の中だけなら想像、実際に作るなら創造」と覚えておくことです。
迷ったときは、「imagination(イマジン)かcreation(クリエイト)か」と英語で考えるのも効果的です。
友人が「想像は『心』を使う感じ、創造は『手』を使う感じでイメージすると分かりやすい」と教えてくれました。
確かに、この覚え方はシンプルで実用的です。
Q4. 子どもには「想像力」と「創造力」どちらが大切?
A. どちらも大切ですが、発達段階によって重点の置き方が変わります。
幼少期は「想像力」、成長とともに「創造力」も育てていくのが理想的です。
子どもの成長において、想像力と創造力は両方とも欠かせない能力です。
ただし、年齢や発達段階によって、どちらを優先的に伸ばすかが変わってきます。
幼少期(0〜6歳)は「想像力」を重視
この時期は、自由に想像を膨らませる力を育てることが重要です:
✓ ごっこ遊びで想像力を刺激する
✓ 絵本の読み聞かせで物語の世界を想像させる
✓ 「もし○○だったら?」という問いかけをする
学童期(7〜12歳)は「創造力」も育てる
想像したことを実際に形にする経験を積ませます:
✓ 工作や絵画で想像を作品にする
✓ 自由研究でオリジナルのテーマに取り組む
✓ 失敗を恐れず挑戦する環境を整える
青年期以降は両方をバランスよく
社会に出る準備として、想像力と創造力を統合していきます。
教育現場では、「想像力が創造力の土台になる」という考え方が主流です。
まず豊かに想像できる子どもに育て、その後で実際に形にする創造力を磨いていくのが効果的だとされています。
知人の保育士が「子どもたちには『これは何に見える?』と想像を促す質問をたくさんしている」と話していました。
想像する習慣が身につけば、将来的に創造する力も自然と育っていくそうです。
Q5. 「そうぞうをかきたてる」はどちらの漢字?
A. 「想像をかきたてる」が正しい表現です。
「創造をかきたてる」とは言いません。
「そうぞうをかきたてる」というフレーズは、必ず「想像をかきたてる」と書きます。
これは「想像力を刺激する」「イメージを膨らませる」という意味の慣用的な表現です。
正しい使い方:
✅ 「この小説は読者の想像をかきたてる描写が素晴らしい。」
✅ 「映画の予告編が、観客の想像をかきたてる演出になっている。」
✅ 「彼女の話し方は、聞き手の想像をかきたてる魅力がある。」
「創造をかきたてる」という表現は、日本語として不自然です。
なぜなら、「かきたてる(掻き立てる)」は「心の中の感情や想像を刺激する」という意味であり、「実際に作る行為」である創造とは相性が悪いからです。
もし創造について表現したい場合は、以下のような言い方になります:
✅ 「この環境は、創造意欲を刺激する。」
✅ 「新しいツールが、創造活動を後押しする。」
✅ 「彼のアイデアが、チームの創造性を引き出した。」
「想像をかきたてる」は文学作品の批評や、映画・ゲームのレビューなどでよく使われる表現です。
覚えておくと、文章表現の幅が広がります。
まとめ
「想像」と「創造」は、どちらも「そうぞう」と読む同音異義語ですが、意味は大きく異なります。
想像は頭の中で思い描くこと、創造は新しいものを実際に作り出すことです。
英語で言えば、想像はimagination、創造はcreationに相当します。
使い分けで迷ったときは、「行動を伴うかどうか」がポイントです。
頭の中だけで完結するなら「想像」、実際に形にするなら「創造」と覚えておきましょう。
また、「想像力」と「創造力」も同様に区別され、ビジネスシーンではどちらも重要な能力として求められています。
この記事で紹介した例文や比較表を参考に、正しく使い分けられるようになれば、あなたの文章表現の幅がさらに広がるはずです。
日常生活やビジネスシーンで自信を持って使いこなしてください。



















