
「戦略と戦術の違いって何?」「ビジネスでどう使い分ければいいの?」と疑問に思っていませんか?
戦略と戦術は似たような言葉ですが、実は明確な違いがあります。
戦略は「目標達成の方向性」を示すもので、戦術は「具体的な実行手段」を指します。

わしも天下統一という戦略があったからこそ、桶狭間や長篠での戦術が活きたのじゃ!
戦略なき戦術は、ただの場当たり作戦に過ぎぬぞ!
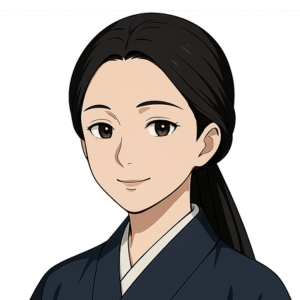
信長さん、相変わらず熱いですわね。
でも確かに、鎌倉幕府も「武士による政治」という大きな戦略があったから、承久の乱で勝てたのよ。
戦略と戦術、両方大事ってことね!
この2つを正しく理解し使い分けることで、ビジネスの成果が大きく変わります。
本記事では、戦略と戦術の違いを分かりやすく解説するとともに、経営やマーケティングにおける具体例、効果的な立て方、そしてユニクロや任天堂など成功企業の活用法まで詳しく紹介します。
戦略と戦術を正しく理解し、自社のビジネスに活かしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
「戦略」と「戦術」の違い
ビジネスシーンでよく耳にする「戦略」と「戦術」。
似たような言葉ですが、実は明確な違いがあります。
戦略は「何を目指すか」という大きな方向性を決めるもので、戦術は「どうやって実現するか」という具体的な手段です。
両者を正しく使い分けることで、目標達成への道筋が明確になります。
「戦略」とは目標達成の方向性
戦略とは、組織や企業が目指すゴールに向かうための基本的な方針や方向性のことです。
「どの市場で戦うか」「誰をターゲットにするか」「どんな価値を提供するか」といった大きな枠組みを決定します。
戦略の特徴は以下の通りです:
🔵 長期的な視点で考える(1年〜数年単位)
🔵 経営層や上層部が決定する
🔵 全体の方向性を示す羅針盤のような役割
🔵 一度決めたら頻繁に変更しない
例えば、あるカフェチェーンが「若年層をターゲットに、おしゃれで居心地の良い空間を提供する」と決めたとします。
これが戦略です。
この方向性が定まることで、次に取るべき具体的な行動(戦術)が見えてきます。
以前、マーケティング部門にいた同僚が「上司から突然『SNS広告を強化しろ』と言われたけど、そもそもうちの会社が何を目指しているのか分からない」と悩んでいました。
これは典型的な「戦略がない状態で戦術だけを実行しようとしている」パターンです。
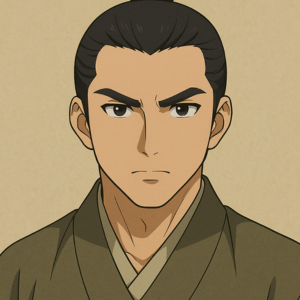
わしは天下を取るという明確な戦略があったからこそ、関ヶ原まで何十年も耐え忍べたのじゃ。
慌てて動く前に、まずは「どこを目指すのか」をしっかり決めることが肝要じゃぞ!
「戦略」は、精選版 日本国語大辞典では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「戦術」とは戦略を実現する具体的手段
戦術とは、戦略を実現するための具体的な行動や施策を指します。
「いつまでに」「誰が」「何をするか」を明確にした実行計画です。
戦術の特徴は以下の通りです:
🟢 短期的な視点で考える(数週間〜数ヶ月単位)
🟢 現場の担当者が実行する
🟢 具体的なアクションが明確
🟢 状況に応じて柔軟に変更できる
先ほどのカフェチェーンの例で言えば、「Instagram広告を月10万円の予算で配信する」「店舗内装をリニューアルする」「季節限定メニューを月1回発表する」といった具体的な施策が戦術になります。
戦術は戦略あってこそ意味を持ちます。
どんなに優れた戦術でも、明確な戦略がなければ効果は半減してしまいます。

信長様という明確な戦略があったから、わしの機転と行動力が活きたんじゃよ。
戦略が地図なら、戦術はその地図を使って実際に走る足じゃ!
どっちが欠けても天下は取れんぞ!
「戦術」は、精選版 日本国語大辞典では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「戦略」と「戦術」の関係性
戦略と戦術はピラミッド構造のような関係にあります。
一番上に「目的・ゴール」があり、その下に「戦略」、さらにその下に複数の「戦術」が位置します。
| 項目 | 戦略 | 戦術 |
|---|---|---|
| 視点 | 長期的(1年〜数年) | 短期的(数週間〜数ヶ月) |
| 内容 | 方向性・方針 | 具体的な行動 |
| 決定者 | 経営層・上層部 | 現場の担当者 |
| 柔軟性 | 頻繁には変更しない | 状況に応じて変更可能 |
| 例 | 低価格戦略で市場シェアを拡大 | 原材料の一括仕入れでコスト削減 |
戦略が「地図」だとすれば、戦術は「実際に歩く道順」です。
地図(戦略)がなければどこに向かえばいいか分かりませんし、道順(戦術)がなければ実際に目的地にたどり着けません。
両方が揃って初めて、目標達成が可能になるのです。
【ここがポイント!】
✓ 戦略 = 目標達成の方向性を決める(長期的・全体的)
✓ 戦術 = 戦略を実現する具体的手段(短期的・実行的)
✓ 戦略と戦術はピラミッド構造の関係(戦略が上、戦術が下)
経営における「戦略」と「戦術」の具体例
経営における戦略と戦術の違いを、もっと具体的に理解しましょう。
ここでは実際のビジネスシーンを想定した例を紹介します。
経営戦略は「会社全体がどの方向に進むか」を決めるもので、経営戦術は「その目標を達成するための日々の活動」です。
経営戦略の例
経営戦略では、企業全体の進むべき方向性を明確にします。
以下のような内容が経営戦略に該当します:
🔷 コストリーダーシップ戦略
業界内で最も低い価格で商品・サービスを提供することで市場シェアを拡大する戦略です。
「同業他社よりも2割安い価格で提供し、販売数量を増やす」という方針がこれに当たります。
🔷 差別化戦略
他社にはない独自の価値を提供することで、競合との差別化を図る戦略です。
「高品質・高機能な商品で、価格よりも品質を重視する顧客層を獲得する」という方針がこれに該当します。
🔷 集中戦略
特定の市場やターゲット層に経営資源を集中させる戦略です。
「30代女性に特化した商品開発とマーケティングを行う」といった方針がこれに当たります。
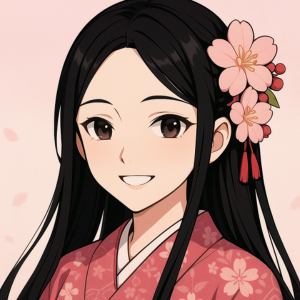
わたくしも「美貌」という差別化戦略で多くの求婚者を集めましたもの。
でも本当は和歌の才能に集中戦略を取っていたのよ。
ビジネスも恋も、自分の強みをどう活かすかが勝負の分かれ目ですわ!
友人が勤める中小企業では、以前「何でもやります」という方針で様々な業種の顧客を獲得しようとしていました。
しかし業績が伸び悩み、「BtoB向けの製造業に特化する」という集中戦略に転換したところ、専門性が評価されて売上が1.5倍になったそうです。
戦略を明確にすることで、社員全員が同じ方向を向けるようになったと話していました。
経営戦術の例
経営戦術は、戦略を実現するための具体的なアクションプランです。
先ほどの戦略ごとに、どんな戦術が考えられるか見てみましょう。
【コストリーダーシップ戦略の場合の戦術】
- 原材料を大量一括購入して仕入れコストを20%削減する
- 生産工程を自動化し、人件費を30%カットする
- 物流網を再構築し、配送コストを15%削減する
- オンライン販売に特化して店舗コストをゼロにする
【差別化戦略の場合の戦術】
- 独自技術の開発に研究開発費を年間5,000万円投資する
- デザイン性の高いパッケージに刷新する(3ヶ月以内)
- アフターサービスを24時間365日対応に拡充する
- 高級感のあるブランドイメージ構築のため、有名デザイナーとコラボする
【集中戦略の場合の戦術】
- ターゲット層が集まるSNS(Instagram)で月50本の投稿を行う
- ターゲット層向けの専門誌に毎月広告を出稿する
- ターゲット層のニーズ調査を四半期ごとに実施する
- ターゲット層向けのカスタマーサポート専門チームを設置する
このように、経営戦略が決まれば、それに沿った具体的な戦術が次々と導き出されます。
戦略という「骨組み」に、戦術という「肉付け」をしていくイメージです。

「倒幕」という大きな戦略があって、初めて「薩摩と長州を手を結ばせる」という具体的な戦術が生まれたがじゃ。
戦略だけ語って行動せん奴も、戦術ばっかりで方向性のない奴も、どっちも世の中は変えられんぜよ!
マーケティングにおける「戦略」と「戦術」の具体例
マーケティングの分野でも、戦略と戦術の使い分けは非常に重要です。
マーケティング戦略は「どの顧客に、どんな価値を、どうやって届けるか」という基本方針を決めるもので、マーケティング戦術はその方針を実現する具体的な施策です。
マーケティング戦略の例
マーケティング戦略では、市場でどのように戦うかの基本方針を定めます。
以下が代表的なマーケティング戦略です:
🔶 STP戦略(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)
市場を細分化し、狙うべきターゲット層を決定し、競合との差別化ポイントを明確にする戦略です。
「20代~30代の働く女性をターゲットに、時短と健康を両立できる商品として訴求する」という方針がこれに当たります。
🔶 認知拡大戦略
まだ商品やサービスを知らない潜在顧客に対して、ブランドや商品の存在を広く知ってもらうことを目指す戦略です。
「今後6ヶ月でブランド認知度を現在の20%から50%に引き上げる」という目標を設定します。
🔶 顧客ロイヤルティ向上戦略
既存顧客との関係を強化し、リピート購入や長期利用を促進する戦略です。
「既存顧客のリピート率を現在の30%から50%に向上させる」という方針がこれに該当します。
以前、Webマーケティング担当をしていた知人から面白い話を聞きました。
彼の会社では「とにかくSNSのフォロワーを増やせ」と指示され、毎日投稿を頑張っていたそうです。
しかし半年経ってもフォロワーは増えず、売上にも繋がりませんでした。
その後、経営陣が「40代男性のビジネスパーソンに特化する」という明確なターゲット戦略を立ててから、投稿内容もターゲットに刺さる内容に変更。
結果、3ヶ月でフォロワー数が3倍になり、問い合わせも急増したそうです。
マーケティング戦術の例
マーケティング戦術は、戦略を実現するための具体的な施策やチャネルの選択です。
それぞれの戦略に対応する戦術を見てみましょう。
【認知拡大戦略の場合の戦術】
- Google広告に月額30万円の予算を投下し、検索連動型広告を配信する
- InstagramとTikTokで毎日1本ずつ動画コンテンツを投稿する
- インフルエンサー10名とタイアップキャンペーンを実施する(3ヶ月以内)
- プレスリリースを月2本配信し、メディア露出を増やす
【顧客ロイヤルティ向上戦略の場合の戦術】
- 購入回数に応じたポイントプログラムを導入する(2ヶ月以内にシステム構築)
- 誕生日月に特別クーポンを配信する仕組みを作る
- 月1回の会員限定メルマガで新商品情報やお得情報を配信する
- カスタマーサポートの対応時間を24時間以内から12時間以内に短縮する
【STP戦略の場合の戦術】
- ターゲット層がよく見る女性向けWebメディアに記事広告を出稿する
- ターゲットの悩みを解決するハウツー記事を自社ブログで月8本公開する
- ターゲット層に人気のタレントを起用したCMを制作・放映する
- ターゲット層向けのLINE公式アカウントを開設し、週2回情報配信する
このように、戦略という「大きな地図」に基づいて、戦術という「具体的なルート」を設定していきます。
戦略なしに戦術だけを実行すると、どこに向かっているのか分からなくなり、効果も限定的になってしまいます。
効果的な戦略を立てる5つのステップ
優れた戦略は闇雲に考えても生まれません。
効果的な戦略を立てるには、体系的なプロセスを踏むことが重要です。
ここでは、実践的な戦略立案の5つのステップを紹介します。
このステップに沿って進めることで、実現可能で成果の出る戦略を構築できます。
ステップ1:目標・目的を明確にする
戦略立案の第一歩は、何を達成したいのかを明確にすることです。
曖昧な目標では、どんな戦略が適切かを判断できません。
目標設定では以下のポイントを意識しましょう:
✅ 数値で測定可能な目標にする(例:売上を1年で30%増加させる)
✅ 期限を設定する(例:2026年3月末までに達成)
✅ Why(なぜその目標なのか)を言語化する
例えば、「売上を増やしたい」という漠然とした目標ではなく、「新規顧客獲得数を月50件に増やし、年間売上を3,000万円から4,000万円に伸ばす」という具体的な目標を設定します。
目標が明確になると、それを達成するための戦略の方向性も自然と見えてきます。
「何のために戦うのか」が分かっていない状態では、どれだけ優れた戦術を実行しても成果には繋がりません。
営業部門にいた先輩から聞いた話ですが、以前の会社では「頑張って営業しろ」としか言われず、チーム全体が迷走していたそうです。
しかし新しい上司が着任し、「今期は既存顧客からのリピート率を40%から60%に上げることに集中する」という明確な目標を示したところ、チーム全員が同じ方向を向いて動けるようになり、実際に目標を達成できたとのことでした。
ステップ2:現状を分析する
目標が定まったら、次は自社の現状を正しく把握することが必要です。
現状分析なしに戦略を立てると、実現不可能な絵に描いた餅になってしまいます。
現状分析で確認すべき項目は以下の通りです:
🔍 内部環境の分析(自社の強み・弱み、リソース、技術力、人材など)
🔍 外部環境の分析(市場動向、競合状況、顧客ニーズ、法規制など)
🔍 現在の数値データ(売上、利益率、顧客数、リピート率など)
分析に役立つフレームワークとしては、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)、3C分析(顧客・競合・自社)、PEST分析(政治・経済・社会・技術)などがあります。
例えば、「年間売上を4,000万円に伸ばす」という目標に対して、現状分析で「現在の営業担当者は3名で、1人あたり月平均10件の新規商談しかできていない」という事実が判明したとします。
この場合、「営業人員を増やす」「営業効率を上げる仕組みを作る」「既存顧客からの単価を上げる」といった戦略の選択肢が見えてきます。
ステップ3:基本方針を決定する
目標と現状が明確になったら、いよいよどの道を進むかの基本方針を決定します。
これが戦略の核心部分です。
基本方針を決める際のポイント:
📌 複数の選択肢を比較検討する(A案・B案・C案など)
📌 自社の強みを活かせる方針を選ぶ
📌 実現可能性とリスクを天秤にかける
例えば、「年間売上を3,000万円から4,000万円に増やす」という目標に対して、以下のような戦略の選択肢が考えられます:
- 方針A: 新規顧客の獲得数を増やす(月30件→50件)
- 方針B: 既存顧客の単価を上げる(平均10万円→15万円)
- 方針C: 新商品を開発して売上の柱を増やす
現状分析の結果、「営業人員を増やすのは難しいが、既存顧客との関係は良好で満足度が高い」という状況であれば、方針Bの「既存顧客の単価を上げる」戦略が最も実現可能性が高いと判断できます。
ステップ4:具体的な行動計画を策定する
基本方針が決まったら、それを実現するための具体的なアクションプランに落とし込みます。
ここから戦術レベルの話になります。
行動計画では以下を明確にします:
🎯 誰が担当するか(責任者と実行者)
🎯 何をするか(具体的な施策内容)
🎯 いつまでにやるか(期限・スケジュール)
🎯 どのくらいの予算・リソースが必要か
例えば、「既存顧客の単価を上げる」という戦略に対して、以下のような行動計画を策定します:
- 上位プランの新商品を開発(担当:商品企画部、期限:3ヶ月、予算:500万円)
- 既存顧客向けアップセル提案マニュアルを作成(担当:営業部長、期限:1ヶ月)
- 営業担当者向けアップセル研修を実施(担当:人事部、期限:2ヶ月、費用:50万円)
- 顧客満足度調査を実施しニーズを把握(担当:マーケ部、期限:1ヶ月、費用:30万円)
ステップ5:検証基準を設定する
最後に、戦略が機能しているかを判断するための指標(KPI)を設定します。
検証なしでは、戦略が正しかったのか、修正が必要なのかが分かりません。
検証基準の設定ポイント:
📊 定量的な指標を設定する(数値で測定可能に)
📊 複数の指標を用意する(1つだけでは判断できない)
📊 測定のタイミングを決める(毎月、四半期ごとなど)
例えば、「既存顧客の単価を上げる」戦略に対する検証基準:
| 指標 | 現状 | 目標値 | 測定頻度 |
|---|---|---|---|
| 顧客単価 | 10万円 | 15万円 | 毎月 |
| アップセル成約率 | 15% | 35% | 毎月 |
| 既存顧客満足度 | 75点 | 80点以上 | 四半期ごと |
| 顧客離脱率 | 10% | 5%以下 | 毎月 |
定期的に数値をチェックし、目標に届いていない場合は戦術の見直しや修正を行います。
このPDCAサイクルを回すことで、戦略の精度が高まっていきます。
✓ ステップ1: 目標・目的を数値で明確にする
✓ ステップ2: 現状を正しく分析する(内部環境・外部環境)
✓ ステップ3: 複数の選択肢から基本方針を決定する
✓ ステップ4: 具体的な行動計画(誰が・何を・いつまでに)を策定
✓ ステップ5: KPIを設定し定期的に検証する
「戦略」を実現する戦術の立て方
戦略が決まったら、次はそれを実現するための戦術を立てる段階です。
戦術は戦略という大きな方向性を、日々の具体的な行動に変換する重要なステップです。
ここでは、効果的な戦術を立てるための3つのポイントを解説します。
戦略に沿った戦術を選択する
戦術を立てる際に最も重要なのは、戦略との整合性です。
どんなに優れた施策でも、戦略とズレていれば意味がありません。
戦術選択のチェックポイント:
☑️ この戦術は戦略の実現に直結しているか
☑️ 複数の戦術候補の中で、最も効果が高いものはどれか
☑️ 自社のリソース(予算・人材・時間)で実行可能か
例えば、「既存顧客の単価を上げる」という戦略に対して、以下のような戦術候補が考えられます:
- 候補A: 新規顧客獲得のためのテレビCMを打つ → ❌ 戦略とズレている
- 候補B: 既存顧客向けの上位プラン商品を開発する → ⭕ 戦略に合致
- 候補C: 既存顧客に定期的にフォローアップ連絡を入れる → ⭕ 戦略に合致
- 候補D: Webサイトのデザインを全面リニューアルする → △ 優先度は低い
このように、戦略に直結する戦術を優先的に選択します。
複数の戦術を組み合わせることで、相乗効果も期待できます。
営業企画をしていた同僚の話ですが、上司から「売上を伸ばすために新規開拓を強化しろ」という戦術を指示されたものの、会社全体の戦略は「既存顧客との深い関係構築」だったため、現場が混乱したそうです。
戦略と戦術がバラバラでは、組織全体の力を結集できません。戦術は必ず戦略に紐づけて選ぶことが大切です。
短期目標を設定する
戦術には必ず短期的な数値目標を設定します。
長期的な戦略目標だけでは、日々の進捗が見えず、モチベーションも維持しにくくなります。
短期目標設定のポイント:
🎯 1ヶ月〜3ヶ月程度の期間で達成可能な目標にする
🎯 数値で測定できる形にする
🎯 戦略目標との関連性を明確にする
例えば、「年間で既存顧客の平均単価を10万円から15万円に上げる」という戦略目標に対して、以下のような短期目標を設定します:
| 期間 | 短期目標 | 具体的な戦術 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 上位プラン商品の設計完了 | 商品企画チームで仕様を確定 |
| 2ヶ月目 | 既存顧客20社に提案実施 | 営業チームがアップセル提案 |
| 3ヶ月目 | アップセル成約5件達成 | 提案内容をブラッシュアップ |
| 6ヶ月目 | 平均単価を12.5万円に到達 | 提案対象を全顧客に拡大 |
短期目標を設定することで、チーム全体が「今月何を達成すべきか」が明確になり、モチベーションも維持しやすくなります。
また、目標未達の場合も早期に対策を打つことができます。
期限を明確にする
戦術には必ず明確な期限を設定します。
期限がない戦術は「いつかやる」となり、結局実行されないまま終わってしまいます。
期限設定のルール:
⏰ 開始日と完了日の両方を決める
⏰ マイルストーン(中間地点)も設定する
⏰ 担当者に裁量を持たせつつ、報告タイミングを決める
例えば、「既存顧客向け上位プラン商品を開発する」という戦術に対して:
- 開始日: 2025年12月1日
- マイルストーン1: 商品仕様確定(12月20日まで)
- マイルストーン2: プロトタイプ完成(1月15日まで)
- マイルストーン3: テスト販売開始(1月31日まで)
- 完了日: 本格販売開始(2026年2月1日)
期限を明確にすることで、逆算してスケジュールを組むことができ、無駄な時間のロスを防げます。
また、定期的な進捗確認のタイミングも自然と決まります。
期限のない戦術は、他の業務に押されて後回しになりがちです。
「いつまでに何を達成するか」を明文化することで、戦術の実行力が格段に高まります。
「戦略」と「戦術」で成功した企業事例
戦略と戦術を明確に使い分け、大きな成果を上げている企業の実例を見てみましょう。
理論だけでなく、実際のビジネスでどのように活用されているかを知ることで、自社への応用イメージが湧きやすくなります。
ここでは3社の成功事例を紹介します。
ユニクロの戦略と戦術
ユニクロは「高品質な衣料品を手頃な価格で提供する」というコストリーダーシップと差別化を組み合わせた独自の戦略で成功しています。
【ユニクロの戦略】
- 品質とデザインにこだわりながら、低価格を実現するSPA(製造小売業)モデルの確立
- 世界中の誰もが着られるベーシックな服を提供する「LifeWear」というコンセプト
- グローバル市場での展開を前提とした大量生産・大量販売
【ユニクロの戦術】
- 素材開発から生産まで一貫して管理し、中間マージンを排除
- ヒートテックやエアリズムなど、独自の機能性素材を開発
- 海外工場と長期的なパートナーシップを結び、大量発注で単価を下げる
- 店舗の大型化により、在庫効率と売場効率を最大化
- 週単位で売れ筋商品を分析し、素早く生産調整
ユニクロの成功の鍵は、「高品質・低価格」という一見矛盾する戦略を、SPAモデルという仕組みと、素材開発や生産管理といった具体的な戦術で実現したことにあります。
戦略と戦術が一体となって機能している好例です。
任天堂の戦略と戦術
任天堂は、ゲーム業界で独自のポジションを確立している企業です。
高性能競争に巻き込まれず、「誰でも楽しめるゲーム体験」を追求する戦略で成功しています。
【任天堂の戦略】
- 高性能競争から距離を置き、「遊びの革新」で差別化する
- ゲームをしない層(ライトユーザー・ファミリー層)も取り込む市場拡大戦略
- 自社IPキャラクター(マリオ、ポケモンなど)を活用したブランド戦略
【任天堂の戦術】
- Wiiでは体感型コントローラーを開発し、家族で楽しめる新しいゲーム体験を創出
- Nintendo Switchでは据え置き型と携帯型のハイブリッド機として、新しい価値を提供
- 「あつまれ どうぶつの森」など、ゲーム初心者でも楽しめるタイトルを開発
- 定期的に人気IPの新作を投入し、ブランド価値を維持
- オンラインサービスを拡充し、継続的な収益源を確保
任天堂は「高性能路線」という業界のトレンドに追随せず、独自の戦略を貫きました。
その結果、PlayStation や Xbox とは異なる顧客層を獲得し、安定した成長を実現しています。
明確な戦略があったからこそ、ブレない戦術を実行できたのです。
サイゼリヤの戦略と戦術
サイゼリヤは、外食産業で徹底したコストリーダーシップ戦略により、圧倒的な低価格を実現している企業です。
【サイゼリヤの戦略】
- 業界最安値レベルの価格で本格的なイタリアンを提供するコストリーダーシップ戦略
- 若年層や学生、ファミリー層をターゲットとした市場戦略
- 「美味しいものを安く提供する」というシンプルな価値提案
【サイゼリヤの戦術】
- オーストラリアに自社農場を持ち、原材料を直接調達してコストを削減
- メニュー数を絞り込み、食材ロスを最小化
- セントラルキッチン方式で調理工程を標準化し、店舗オペレーションを効率化
- 店舗デザインをシンプルにし、内装コストを抑える
- 24時間営業や長時間営業で、店舗の稼働率を最大化
サイゼリヤの事例で特筆すべきは、「低価格」という戦略を実現するために、あらゆる戦術が徹底的に最適化されている点です。
原材料調達から店舗運営まで、すべてが戦略に紐づいています。
戦略と戦術の一貫性が、競合他社には真似できない強みを生み出しているのです。
「戦略」と「戦術」に関するQ&A
戦略と戦術について、よくある疑問や質問にお答えします。
実際にビジネスで活用する際に迷いやすいポイントを中心に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
戦略がないとどうなる?
戦略がない状態でビジネスを進めると、組織全体が迷走してしまいます。
具体的には以下のような問題が発生します:
❌ 場当たり的な施策ばかりで、一貫性がない
❌ リソースが分散し、どの施策も中途半端になる
❌ 優先順位が決められず、緊急性の高いことばかり対応する
❌ 成果の判断基準が曖昧で、何が成功か分からない
❌ 社員の方向性がバラバラで、チームワークが機能しない
例えば、「売上を伸ばしたい」という目標だけがあって戦略がない場合、ある担当者は新規顧客開拓に注力し、別の担当者は既存顧客のフォローに力を入れ、さらに別の担当者は商品開発に時間を使う、といった状況になります。
それぞれは頑張っているのに、組織全体としての力が発揮できません。
戦略は組織の「共通言語」です。
明確な戦略があることで、全員が同じ目標に向かって進むことができ、最大の成果を生み出せるのです。
戦術だけではダメなの?
戦術だけで戦略がない状態は、地図なしで歩いているようなものです。
一生懸命歩いても、目的地にたどり着けません。
戦術だけの状態で起こる問題:
⚠️ 目的と手段が逆転し、戦術の実行自体が目的になる
⚠️ 効果測定ができず、その戦術が正しいのか判断できない
⚠️ 短期的な成果にばかり目が行き、長期的な成長が見込めない
⚠️ 競合との差別化ができず、価格競争に巻き込まれる
例えば、「SNS投稿を毎日する」「メルマガを週1回送る」「広告費を月50万円使う」といった戦術を実行しても、「誰に、何を、なぜ届けるのか」という戦略がなければ、成果は限定的です。
投稿数やメール配信数といった「活動量」は増えますが、売上や顧客満足度といった「成果」には繋がりにくいのです。
戦術は戦略を実現する手段です。
戦略という土台があって初めて、戦術が本来の力を発揮します。
戦略と戦術はどちらを先に考えるべき?
必ず戦略を先に考えるべきです。これは絶対的なルールと言えます。
戦略→戦術の順序が重要な理由:
1️⃣ 方向性が定まってから、具体的な行動を決める方が効率的
2️⃣ 限られたリソースを最も効果的な戦術に集中投下できる
3️⃣ 戦術の優先順位が明確になり、取捨選択ができる
4️⃣ 状況変化に応じた戦術の変更がしやすくなる
先に戦術から考えてしまうと、「できること」や「やりたいこと」ベースで施策を選んでしまい、本来の目的から外れてしまいます。
また、流行りの戦術に飛びついて失敗するパターンも多く見られます。
実際の手順としては、「目標設定→現状分析→戦略決定→戦術選択→実行→検証」という流れになります。
この順序を守ることで、一貫性のある施策展開が可能になります。
ただし、戦術を実行しながら戦略を微調整することは必要です。
完全に固定するのではなく、柔軟性を持たせることも大切です。
中小企業でも戦略は必要?
結論から言うと、中小企業こそ戦略が必要です。
むしろ大企業より重要と言えるかもしれません。
中小企業に戦略が必要な理由:
💡 限られたリソースを最大限に活用する必要がある
💡 大企業との競争で勝つには、独自のポジショニングが必須
💡 意思決定のスピードが速いため、戦略の効果が出やすい
💡 組織がコンパクトなので、戦略の浸透がしやすい
「うちは小さい会社だから戦略なんて大げさ」と考える経営者もいますが、それは誤解です。
中小企業は人材も資金も限られているからこそ、「どこで戦うか」「何で勝負するか」を明確にする必要があります。
例えば、地方の小さな工務店が「地域密着」「自然素材」「リフォーム専門」という明確な戦略を打ち出すことで、大手ハウスメーカーとは異なる顧客層を獲得できます。
戦略がなければ、大手と同じ土俵で価格競争に巻き込まれ、消耗してしまうでしょう。
規模の大小に関わらず、ビジネスを成功させるには戦略が不可欠です。
戦略と戦術のバランスはどう取る?
戦略と戦術の理想的なバランスは、戦略3割、戦術7割の時間配分と言われています。
バランスを取るためのポイント:
⚖️ 戦略は定期的に見直す(年1回〜半年に1回)
⚖️ 戦術は柔軟に変更する(月1回〜週1回)
⚖️ 戦略会議と戦術会議を分ける
⚖️ 戦略担当者と戦術実行者の役割を明確にする
よくある失敗パターンは、戦略ばかり議論して実行が伴わないケース、または逆に戦術の実行に追われて戦略の見直しをしないケースです。
実務では、経営層が戦略を決定し、現場の管理職が戦術に落とし込み、担当者が実行するという役割分担が効果的です。
ただし、現場からのフィードバックを戦略に反映させる仕組みも重要です。
マーケティング部門にいた知人の会社では、月初に戦略の進捗確認会議(30分)、週次で戦術の実行状況確認会議(1時間)を行っているそうです。
この定期的な確認サイクルにより、戦略と戦術のズレが生じにくくなり、成果も安定して出ているとのことでした。
✓ 必ず戦略→戦術の順序で考える
✓ 中小企業こそ明確な戦略が必要
✓ 戦略3割、戦術7割の時間配分が理想的
✓ 定期的に戦略を見直し、戦術は柔軟に変更する
まとめ
戦略と戦術は、ビジネスを成功に導くための両輪です。
戦略は「何を目指すか」という方向性を示し、戦術は「どうやって実現するか」という具体的な手段を表します。
両者を明確に使い分けることで、組織全体が同じゴールに向かって効率的に進むことができます。
戦略立案では、目標設定→現状分析→基本方針の決定という順序を守り、戦術では短期目標と期限を明確にすることが重要です。
ユニクロや任天堂、サイゼリヤといった成功企業の事例からも分かるように、明確な戦略と、それを実現する一貫した戦術があってこそ、持続的な成長が可能になります。
まずは自社の現状を見直し、「どこで戦うか」という戦略を明確にすることから始めてみましょう。
戦略が定まれば、取るべき戦術も自然と見えてきます。



















