
「フリーター」と「ニート」という言葉は、どちらも正社員ではない若者を指す言葉としてよく使われますが、実は明確な違いがあることをご存知ですか?
同じように思われがちなこの2つの言葉ですが、働いているかどうか、収入があるかどうか、そして企業からの評価も大きく異なります。
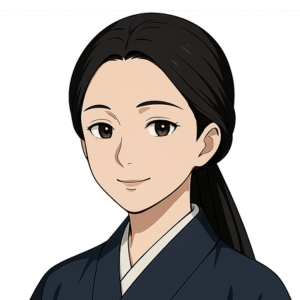
梅子殿、最近の若者は「フリーター」だの「ニート」だの言われておるが、わしにはどちらも同じに見えるのじゃが…一体何が違うのじゃ?

政子様、それは大きな誤解ですわ!
フリーターは「働いている」のに対し、ニートは「働いていない」という決定的な違いがあるのです。
企業からの評価も天と地ほど違いますのよ。
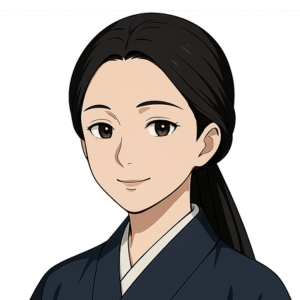
ほほう!働いておるか否かが肝要か。
わしも源氏の棟梁として働いてきた身じゃ。
働かぬ者は食うべからずとはよく言ったものよ!

その通りです!
ただし、どちらも正社員を目指すべき状態であることに変わりはありません。
この記事を読めば、自分がどちらに該当するか、そしてどう行動すべきかが分かりますわ。
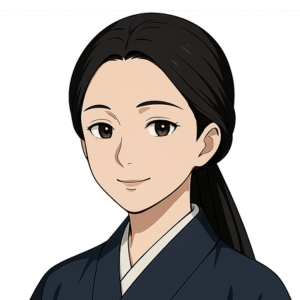
なるほど!
では、この記事をしっかり読んで学ばねばならぬな!
特に将来のリスクとやらが気になるぞ!
自分がどちらに該当するのか、また就職活動でどう見られるのかを正しく理解することは、今後のキャリアを考える上でとても重要です。
フリーターは「アルバイトとして働いている人」、ニートは「働いておらず、求職活動もしていない15〜34歳の人」です。
最大の違いは「働く意思」と「収入の有無」にあります。
✅ この記事でわかること
- フリーターとニートの厚生労働省による正式な定義
- 5つの観点から見た具体的な違い(経済面・就職活動・世間体など)
- それぞれのメリット・デメリットと将来のリスク
- 35歳以上の呼び方や無職・引きこもりとの違い
- 正社員を目指すための支援機関と就職方法
この記事では、比較表やクイズ、具体例を使って、誰でも簡単に理解できるように解説しています。
自分の現状を正しく把握し、次のステップへ進むために、ぜひ最後までご覧ください。
「フリーター」と「ニート」の違いとは?
「フリーター」と「ニート」という言葉は、どちらも正社員ではない若者を指す言葉としてよく使われます。
しかし、この2つには明確な違いがあるのをご存知でしょうか。
実は、働いているかどうかだけでなく、企業や社会からの評価も大きく異なるんです。
ここでは、両者の本質的な違いを分かりやすく解説していきます。
最大の違いは「働く意思」と「収入の有無」
フリーターとニートの最も大きな違いは、働く意思があるか、そして実際に収入を得ているかという点です。
フリーターは、アルバイトやパートタイムとして実際に働いており、自分で収入を得ています。
たとえ正社員ではなくても、仕事を通じて社会と関わり、お金を稼いでいるわけですね。
朝起きて職場に行き、決められた時間働いて給料をもらう。この基本的な働くサイクルが成立しています。
一方、ニートは「Not in Education, Employment or Training」の略で、学校にも通っておらず、仕事もしておらず、職業訓練も受けていない状態を指します。
つまり、働く意思がない、または働いていないということ。
収入源は親の支援や貯金に頼っているケースがほとんどです。
私の知人に、大学卒業後に「やりたいことが見つからない」という理由で半年間何もせず過ごした人がいました。
その期間、彼はまさにニート状態だったわけです。
しかし、短期のアルバイトを始めた瞬間、たとえ週3日の勤務であっても「フリーター」に分類が変わります。
働いているかどうか、この一線が両者を分ける決定的な境界線なんですね。
企業や社会から見た評価の違い
では、企業や社会は、フリーターとニートをどう見ているのでしょうか?
実は、両者には歴然とした評価の差があります。
フリーターに対しては、「正社員ではないものの、働く意欲はある」「最低限の社会経験は積んでいる」という見方をされることが多いです。
アルバイトであっても、接客スキルやコミュニケーション能力、時間管理能力などは身につきます。
採用面接でも、アルバイト経験を通じて学んだことをアピールできる余地があります。
一方、ニートに対する評価は、残念ながら厳しいのが現実です。
「働く意欲がない」「社会性に欠ける」「生活リズムが乱れている可能性がある」といったネガティブな印象を持たれがちです。
特に空白期間が長くなるほど、「なぜ働いていなかったのか」という質問に説得力のある答えを用意するのが難しくなります。
ある人材紹介会社の採用担当者に話を聞いたところ、「フリーター期間が長くても、その間にアルバイトで何を学んだかを語れる人は評価できる。でもニート期間については、よほど明確な理由がない限り、マイナス評価になってしまう」と率直に語っていました。
ただし、これは一般的な傾向であって、ニートだった過去があっても正社員として活躍している人は大勢います。
大切なのは、現状を変えようとする意志と行動なんですよ。
フリーターとニートの違い比較表
ここまでの内容を、より分かりやすく表にまとめました。
一目で違いが分かるので、ぜひチェックしてみてください。
| 比較項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 定義 | アルバイト・パートで働く15〜34歳 | 学校・仕事・職業訓練のいずれもしていない15〜34歳 |
| 働く意思 | ✅ ある | ❌ ない、または不明確 |
| 収入の有無 | ✅ あり(時給・日給で稼ぐ) | ❌ なし(親の支援・貯金頼み) |
| 労働時間 | 週20〜40時間程度が一般的 | 0時間 |
| 社会との関わり | ✅ 職場でのコミュニケーションあり | ❌ 限定的または孤立しがち |
| 企業からの評価 | △ 正社員ではないが、働く意欲はある | ❌ 厳しい評価を受けやすい |
| 就職活動の難易度 | △ やや難しいが、経験をアピール可能 | ✖ 空白期間の説明が必須で難易度高い |
| 将来の不安度 | ⚠ 中〜高(収入不安定・スキル不足) | ⚠⚠ 高(経済的困窮・社会復帰困難) |
この表を見ると、フリーターとニートでは働いているかどうかという点が、その後の人生に大きな影響を与えることが分かりますね。
どちらも正社員を目指すべき状況ではありますが、フリーターの方が「すでに働いている」という実績がある分、一歩有利な立場にあると言えます。
別の知人で、5年間フリーターを続けていた人がいました。
彼は飲食店でのアルバイト経験を活かして、最終的に未経験OKの営業職に就職することができました。
「アルバイトでも、接客で培ったコミュニケーション力が評価された」と嬉しそうに話していたのが印象的です。
一方で、ニート期間が長かった人でも、職業訓練校に通ったり資格を取得したりして、見事に正社員になったケースもたくさんあります。
大切なのは、今からでも行動を起こすこと。
次のステップに進む意志があれば、道は必ず開けますよ。
フリーターとニートの最大の違いは「働く意思」と「収入の有無」です。
フリーターは働いているため社会経験を積めますが、ニートは空白期間の説明が必要になり就職活動で不利になります。
「フリーター」の定義と特徴
ここでは、「フリーター」という言葉の正確な定義と、実際にフリーターとして働いている人たちの特徴について詳しく見ていきましょう。
実は、フリーターには厚生労働省や総務省による明確な定義があり、単に「アルバイトで生計を立てている人」というだけではないんです。
厚生労働省によるフリーターの定義
フリーターという言葉は日常的によく使われますが、実は厚生労働省と総務省統計局が統計調査のために明確な定義を定めています。
📊 厚生労働省・総務省統計局によるフリーターの定義
🔹 年齢: 15歳〜34歳
🔹 対象: 男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者
🔹 条件: 以下のいずれかに該当する者
① 雇用者のうち、勤め先における呼称が「アルバイト」または「パート」である者
現在、アルバイトやパートとして実際に働いている人が該当します。
コンビニ、飲食店、倉庫作業など、時給制や日給制で「アルバイト」「パート」という呼び名で雇われている人たちです。
② 完全失業者のうち、探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
現在は無職だが、正社員ではなくアルバイト・パートの仕事を探している人も含まれます。
「働く意思がある」という点が重要なポイントで、これがニートとの大きな違いになります。
③ 非労働力人口のうち、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定もしていない者
学生でも主婦でもなく、就職内定もない状態で、アルバイト・パートを希望している人も対象です。
【出典】
ちなみに、女性については「未婚」という条件がついているのは、結婚後にパート・アルバイトで働く主婦層と区別するためです。
統計上、主婦パートは別のカテゴリーとして扱われているんですね。
私の高校時代の同級生に、卒業後すぐに正社員にならず、いくつかのアルバイトを掛け持ちしながら音楽活動を続けていた人がいました。
彼は「夢を追いながら生活費を稼ぐ」というスタイルで、まさに典型的なフリーターでした。
夢が叶わなかった後も、アルバイト経験を活かしてイベント会社に正社員として就職できたそうです。
フリーターの年齢層と人口
フリーターは、日本にどのくらいいるのでしょうか?
総務省統計局の労働力調査によると、2023年時点でフリーターの数は約134万人と推計されています。
【出典】
年齢層別に見ると、以下のような傾向があります。
| 年齢層 | フリーター人口の割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 15〜24歳 | 約50% | 高校・大学卒業後、夢を追う人や就職活動中の人が多い |
| 25〜29歳 | 約30% | 正社員になりたいが機会に恵まれない、またはスキル不足を感じている層 |
| 30〜34歳 | 約20% | 長期フリーター化が進み、正社員就職のハードルが高くなる層 |
注目すべきは、年齢が上がるにつれてフリーター人口の割合が減るという点です。
これは、多くの人が20代のうちに正社員への転換を果たしている証拠でもあります。
逆に言えば、30代に入るとフリーターから正社員になるハードルが一気に高くなるということ。
だからこそ、できるだけ早い段階で行動を起こすことが大切なんですね。
また、フリーター人口の推移を見ると、2003年の217万人をピークに減少傾向にあります。
これは、企業の採用活動が活発化したことや、フリーター支援策が充実してきたことが影響していると考えられます。
男女比で見ると、男性が約45%、女性が約55%という比率になっています。
女性の場合、結婚や出産を機に一度退職し、その後パート・アルバイトとして復帰するケースも多いのですが、既婚女性は定義から除外されるため、この数字には含まれていません。
フリーターになる主な理由
では、なぜ人はフリーターという働き方を選ぶのでしょうか?
実は、その理由は人それぞれで、決して「怠けている」「やる気がない」とは限らないんです。
🔷 やりたいことを追求するため
俳優、ミュージシャン、作家、YouTuberなど、夢を追いかけながら生活費を稼ぐためにフリーターを選ぶ人は多いです。
正社員になると時間的拘束が大きくなるため、あえてアルバイトで柔軟に働くという選択をしています。
シフトを調整しながら、オーディションやライブ活動に時間を割けるのがメリットですね。
🔷 就職活動に失敗した・内定が取れなかった
新卒での就職活動がうまくいかず、「とりあえずアルバイトで生活しながら次のチャンスを待とう」と考える人も少なくありません。
リーマンショックやコロナ禍など、経済状況によって新卒採用が減った時期には、こうしたケースが急増しました。
「正社員になりたいけど、今はフリーターとして働いている」という人たちです。
🔷 正社員として働く自信がない
「責任の重い仕事はプレッシャーに感じる」「人間関係が苦手」「長時間労働に耐えられない」といった理由で、正社員ではなくフリーターを選ぶ人もいます。
精神的な負担を軽くするための選択として、フリーターという働き方を選んでいるわけです。
働く時間や日数を自分でコントロールできる点に魅力を感じている人も多いようです。
🔷 自由な時間が欲しい
趣味や旅行、家族との時間を優先したいという理由で、フルタイムの正社員ではなく、シフト制のアルバイトを選ぶ人もいます。
「人生は仕事だけじゃない」という価値観を持つ人にとっては、フリーターは合理的な選択肢なんですね。
週3〜4日働いて、残りの時間は好きなことに使うというライフスタイルです。
🔷 やむを得ない事情がある
家族の介護や自身の病気療養などの理由で、フルタイムの正社員として働けない人もいます。
短時間勤務が可能なアルバイトという選択肢は、こうした事情を抱える人にとって現実的な働き方なんです。
別の知人で、正社員として3年間働いた後、心身の疲労から退職し、しばらくフリーターとして働いていた人がいました。
彼は「一度リセットして、自分が本当にやりたいことを見つめ直す時間が必要だった」と話していました。
その後、職業訓練校でプログラミングスキルを身につけ、IT業界に正社員として再就職できたそうです。
フリーターになる理由は多様ですが、大切なのは「この状態をいつまで続けるのか」「次のステップはどうするのか」を考えることです。
フリーターは決して悪い選択ではありませんが、将来を見据えた計画を持つことが重要ですよ。
「ニート」の定義と特徴
ここでは、「ニート」という言葉の正確な定義と、ニート状態にある人たちの特徴について詳しく解説します。
ニートという言葉は、実はイギリス発祥の概念で、日本では2000年代に入ってから社会問題として注目されるようになりました。
厚生労働省によるニートの定義
ニート(NEET)とは、「Not in Education, Employment or Training」の頭文字を取った言葉で、元々はイギリスの労働政策で使われていた概念です。
日本語に訳すと「就学、就業、職業訓練のいずれもしていない人」という意味になります。
📊 厚生労働省によるニートの定義
🔹 年齢: 15歳〜34歳
🔹 状態: 非労働力人口(仕事をしていない、かつ求職活動もしていない)
🔹 除外対象: 家事をしている人、通学している人
つまり、ニートとは「15〜34歳で、働いておらず、働くための活動(求職活動・職業訓練)もしておらず、学校にも通っておらず、家事もしていない人」を指します。
【出典】
ニートとフリーターの決定的な違いは、働く意思があるかどうかという点です。
フリーターは「アルバイトとして働いている」または「アルバイトを探している」という点で、明確に働く意思がありますが、ニートは求職活動すらしていない状態を指します。
また、ニートには「求職型」「非求職型」「非希望型」の3つのタイプがあると言われています。
① 求職型ニート
働きたい気持ちはあるが、何らかの理由で求職活動ができていない状態。
「どうやって仕事を探せばいいか分からない」「面接が怖い」といった不安を抱えている人が多いです。
② 非求職型ニート
働きたい気持ちはあるものの、現在は求職活動をしていない状態。
「もう少し準備してから就職活動を始めたい」「資格を取ってから動きたい」と考えている人が該当します。
③ 非希望型ニート
働く意思そのものがない状態。家族の支援に頼って生活しており、就職する必要性を感じていないケースが多いです。
私の友人の弟さんは、大学卒業後に就職活動がうまくいかず、半年ほどニート状態になっていました。
彼は「求職型ニート」で、働きたい気持ちはあったのですが、何度も面接で落ちたことで自信を失い、動けなくなっていたそうです。
最終的には地域若者サポートステーションの支援を受けて、無事に就職できたと聞きました。
ニートの年齢層と人口
日本には、どのくらいのニートがいるのでしょうか?
総務省統計局の労働力調査によると、2022年時点でニートの数は約57万人と推計されています。
【出典】
年齢層別に見ると、以下のような傾向があります。
| 年齢層 | ニート人口の割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 15〜19歳 | 約15% | 高校中退や進路未決定の若者が多い |
| 20〜24歳 | 約30% | 大学卒業後の就職失敗、または就職活動の挫折が多い |
| 25〜29歳 | 約30% | ニート期間が長期化し、社会復帰が難しくなり始める層 |
| 30〜34歳 | 約25% | 長期ニート化が進み、就職のハードルが非常に高くなる層 |
注目すべきは、20代がニート人口の約60%を占めるという点です。
この時期にニート状態から抜け出せるかどうかが、その後の人生に大きな影響を与えます。
また、ニート人口の推移を見ると、2020年に新型コロナウイルスの影響で一時的に69万人まで増加しましたが、その後は減少傾向にあります。
ただし、依然として50万人以上のニートが存在しているのが現状です。
さらに、35歳以上の無業者は「中年無業者」と呼ばれることがあります。
厚生労働省の定義では34歳までをニートとしていますが、35歳以上でも同様の状態にある人は多く、2022年時点で約36万人の中年無業者がいると報告されています。
35歳を過ぎると、ニートという呼び方は使われなくなりますが、状況はより深刻になる傾向があります。
ニートになる主な原因
では、なぜ若者はニート状態になってしまうのでしょうか?
厚生労働省の調査によると、ニートになる原因は多岐にわたります。
【出典】
🔷 就職活動での挫折
新卒の就職活動で何社も落ち続けたことで、自信を失い、働くこと自体に恐怖を感じるようになるケースです。
「また落ちるのではないか」という不安から、求職活動ができなくなってしまいます。
🔷 職場での失敗やトラウマ
一度就職したものの、職場の人間関係や業務内容が合わず、退職した後にニート状態になるパターンです。
「また同じ失敗をするのではないか」という恐怖から、次の一歩が踏み出せなくなります。
🔷 学校でのいじめや不登校の経験
学生時代にいじめや不登校を経験したことで、社会に対する不信感や恐怖心を持ち、就職する意欲が湧かないケースです。
人間関係を築くこと自体に強い抵抗を感じている人も多いです。
🔷 メンタルヘルスの問題
うつ病、適応障害、社交不安障害など、精神的な不調が原因でニート状態になることもあります。
働きたい気持ちはあっても、心身の状態がそれを許さないという状況です。
🔷 コミュニケーション能力への不安
「自分は人とうまく話せない」「職場でやっていける自信がない」といった、コミュニケーション能力に対する強い不安から、働くことを避けてしまうケースです。
🔷 家庭環境の影響
経済的に余裕のある家庭で育ち、働かなくても生活できる環境にあるため、就職する必要性を感じないという人もいます。
親が「働かなくてもいい」と容認してしまっているケースも少なくありません。
🔷 進路への迷いや目標の喪失
「やりたいことが見つからない」「どんな仕事が自分に合っているか分からない」という理由で、就職活動を先延ばしにしているうちにニート状態になってしまうパターンです。
別の知人は、新卒で入社した会社でパワハラを受けて退職した後、しばらくニート状態になっていました。
彼は「また同じ目に遭うのではないか」という恐怖から、求職活動ができなくなっていたそうです。
しかし、地域若者サポートステーションでカウンセリングを受け、少しずつ自信を取り戻して、最終的には自分に合った職場を見つけることができました。
ニートになる原因は人それぞれですが、大切なのは「今の状態を変えたい」という気持ちを持つこと。
そして、一人で抱え込まずに、支援機関や家族、友人に相談することです。
ニートから抜け出すことは決して不可能ではありません。
小さな一歩から始めることが、大きな変化につながりますよ。
「フリーター」と「ニート」を5つの観点で徹底比較
ここまで、フリーターとニートそれぞれの定義と特徴を見てきました。
では、実際に両者を具体的に比較すると、どのような違いがあるのでしょうか?
ここでは、経済面、就職活動、世間体、将来性、スキル習得という5つの観点から、フリーターとニートを徹底的に比較していきます。
① 経済面の違い
フリーターとニートの最も分かりやすい違いは、収入があるかどうかという点です。
フリーターの経済状況
フリーターは、アルバイトやパートとして働いているため、毎月一定の収入を得ています。
時給や日給で給料をもらい、自分の力で生活費を稼いでいるわけですね。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、フリーターの平均月収は約14〜18万円程度とされています。
週5日フルタイムで働けば、月収20万円前後を稼ぐことも可能です。
ただし、ボーナスや昇給がほとんどないため、年収は正社員に比べて大幅に低くなります。
それでも、自分の収入で生活費を賄い、多少の貯金ができる人もいます。
ニートの経済状況
一方、ニートには収入がありません。
働いていないため、生活費はすべて親や家族の支援に頼っているケースがほとんどです。
自分でお金を稼いでいないため、経済的に自立できておらず、親に依存した生活を送っています。
中には、親の年金や貯金で生活しているニートもいますが、親が高齢になったり、亡くなったりすると、生活が一気に困窮するリスクがあります。
収入がないということは、将来への貯蓄もできないため、長期的に見ると非常に危険な状態と言えます。
経済面での比較表
| 項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 月収 | 約14〜20万円 | 0円 |
| 年収 | 約170〜240万円 | 0円 |
| 生活費の出所 | 自分の収入 | 親・家族の支援 |
| 貯金の可能性 | △ 可能だが少額 | ❌ 不可能 |
| 経済的自立 | △ 一部可能 | ❌ 不可能 |
私の知人で、フリーターとして5年間働いていた人がいました。
彼は月収18万円ほどでしたが、実家暮らしだったため、毎月3〜5万円ほど貯金していたそうです。
「正社員に比べれば少ないけど、自分で稼いだお金で好きなものが買えるのは嬉しい」と話していました。
一方、ニートの状態にある人は、親に頼らざるを得ず、経済的な自由がほとんどないのが現実です。
② 就職活動上の違い
フリーターとニートでは、正社員への就職活動において、企業からの評価に大きな差があります。
フリーターの就職活動上の立場
フリーターは、アルバイトであっても「働いた経験がある」という点が評価されます。
接客業であれば、コミュニケーション能力や顧客対応スキル、倉庫作業であれば、体力や正確性など、何らかのスキルを身につけているはずです。
履歴書にも「職歴」として記載できるため、面接では「アルバイトで何を学んだか」「どんな工夫をしたか」をアピールできます。
もちろん、正社員経験がないことはマイナスですが、「働く意欲がある」「社会経験がある」という点で、ニートよりも有利な立場にあります。
ただし、フリーター期間が長すぎる(5年以上)と、「なぜ正社員にならなかったのか」という疑問を持たれやすくなります。
それでも、アルバイト経験を通じて得たスキルや成果を具体的に説明できれば、十分に正社員への道は開けます。
ニートの就職活動上の立場
ニートの場合、最も大きな問題は「空白期間の説明」です。
履歴書に何年もの空白期間があると、企業の採用担当者は必ず「この期間、何をしていたのか?」と質問します。
働いていない期間が長いほど、「働く意欲がない」「社会性に欠ける」「生活リズムが乱れている」といったネガティブな印象を持たれやすくなります。
特に、空白期間が2年以上になると、説得力のある理由を用意するのが非常に難しくなります。
また、ニートには「職歴」がないため、履歴書に書ける内容が限られます。
学生時代のアルバイト経験やボランティア活動があれば、それをアピールできますが、何もない場合は自己PRが難しくなります。
ただし、ニートだからといって就職が不可能なわけではありません。
空白期間中に「資格取得に励んでいた」「職業訓練を受けていた」「家族の介護をしていた」など、具体的な理由を説明できれば、理解してくれる企業もあります。
就職活動上の比較表
| 項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 職歴の有無 | ✅ あり(アルバイト経験) | ❌ なし |
| 企業からの評価 | △ やや不利だが評価される点もある | ✖ 厳しい評価を受けやすい |
| 面接でのアピール | ✅ 働いた経験を話せる | ❌ 空白期間の説明が必須 |
| 正社員就職の難易度 | △ やや難しいが可能性は高い | ✖ 難易度が高い |
ある採用担当者に話を聞いたところ、「フリーター経験がある人は、少なくとも『働く』という行為に慣れているので、研修でも順応しやすい。
でも、ニートの場合は、まず『働くこと』そのものに慣れてもらう必要があるので、採用のハードルが上がってしまう」と率直に語っていました。
③ 世間体・社会的評価の違い
フリーターとニートでは、周囲からの見られ方や社会的な評価にも大きな差があります。
フリーターへの社会的評価
フリーターに対しては、「正社員ではないけれど、一応働いている」という評価をされることが多いです。
親や親戚からも「フリーターでも働いているだけマシ」という見方をされるケースが多いでしょう。
ただし、年齢が上がるにつれて、周囲からのプレッシャーは強くなります。
20代前半であれば「まだ若いし、これから正社員を目指せばいい」と寛容に見てもらえますが、30代に入ると「いつまでフリーターをやっているの?」という厳しい目が向けられるようになります。
また、恋愛や結婚においても、フリーターは不利になることがあります。
「収入が不安定」「将来性がない」という理由で、結婚相手として敬遠されるケースも少なくありません。
ニートへの社会的評価
ニートに対する社会的評価は、残念ながら非常に厳しいのが現実です。
「働いていない」「働く意欲がない」という点が、周囲から強く批判されやすくなります。
親や親戚からは「いつまで家にいるの?」「働きなさい」というプレッシャーを受け続けることになります。
友人や知人との関係も疎遠になりがちで、「ニートであることを知られたくない」という気持ちから、人間関係を避けてしまう人も多いです。
特に、日本社会では「働くこと=当たり前」という価値観が強いため、働いていないニートは社会的に孤立しやすくなります。
SNSで友人が正社員として活躍している姿を見て、劣等感や焦りを感じる人も少なくありません。
世間体・社会的評価の比較表
| 項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 親からの評価 | △ 「働いているだけマシ」 | ❌ 「早く働きなさい」と強いプレッシャー |
| 友人からの見方 | △ 理解される場合もある | ❌ 距離を置かれやすい |
| 恋愛・結婚 | △ やや不利だが可能性あり | ✖ 非常に厳しい |
| 社会的孤立のリスク | ⚠ 中程度 | ⚠⚠ 高い |
私の友人で、ニート状態だった人がいましたが、彼は「親から毎日のように『働け』と言われて、家にいるのが辛かった」と話していました。
一方、フリーターの知人は「親からは『正社員になってほしい』とは言われるけど、働いている分、そこまで厳しくは言われない」とのことでした。
④ 将来性の違い
フリーターとニートでは、将来への展望や可能性にも大きな差があります。
フリーターの将来性
フリーターは、アルバイト経験を活かして正社員に転職できる可能性があります。
特に、接客業や販売業での経験は、営業職やサービス業への転職に有利に働くことがあります。
また、アルバイト先で実績を積めば、正社員登用のチャンスがある職場もあります。
「まずはアルバイトとして働いて、実力を認められたら正社員になれる」という道筋が見える点は、フリーターの強みと言えるでしょう。
ただし、フリーター期間が長引くほど、正社員への転職は難しくなります。
30代半ば以降になると、未経験職種への転職はほぼ不可能になるため、できるだけ早めに行動を起こすことが重要です。
ニートの将来性
ニートの場合、将来への展望が非常に不透明です。働いていないため、スキルも経験も身につかず、年齢だけが上がっていきます。
20代であれば、まだ就職のチャンスはありますが、30代に入ると一気にハードルが高くなります。
特に、35歳を過ぎると「中年無業者」と呼ばれるようになり、就職支援の対象からも外れてしまうケースがあります。
親の支援に頼り続けていると、親が高齢になったり、亡くなったりした時に、生活が一気に困窮するリスクがあります。
ただし、ニートから抜け出すことは決して不可能ではありません。
地域若者サポートステーションやハローワークなどの支援機関を活用すれば、就職への道は開けます。
大切なのは、「今から変わりたい」という気持ちを持つことです。
将来性の比較表
| 項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 正社員への転職可能性 | △ 20代なら十分可能 | ✖ 空白期間の説明が課題 |
| スキル・経験の蓄積 | ✅ アルバイトで一部蓄積可能 | ❌ 何も蓄積されない |
| 年齢を重ねた時のリスク | ⚠ 高い(30代以降厳しい) | ⚠⚠ 非常に高い |
| 生活困窮のリスク | △ 収入不安定だが生活は可能 | ✖ 親の支援が途絶えると困窮 |
別の知人で、28歳までニートだった人がいましたが、地域若者サポートステーションの支援を受けて、未経験OKの介護職に就職しました。
彼は「正直、もっと早く動けばよかったと後悔している。
でも、今からでも遅くないと信じて頑張る」と話していました。
⑤ スキル習得面の違い
フリーターとニートでは、仕事に必要なスキルを習得できるかどうかにも大きな違いがあります。
フリーターのスキル習得
フリーターは、アルバイトを通じてさまざまなスキルを身につけることができます。
たとえば、以下のようなスキルです。
- 接客スキル: 飲食店やコンビニでの接客経験を通じて、コミュニケーション能力や顧客対応力が身につく
- 体力・忍耐力: 倉庫作業や引っ越しバイトなどで、体力や粘り強さが鍛えられる
- 時間管理能力: シフト勤務を通じて、時間を守ることや効率的に働くことを学べる
- チームワーク: 職場のスタッフと協力して働くことで、協調性が育つ
これらのスキルは、正社員として働く際にも役立つ基礎的な能力です。
また、アルバイト先で専門的なスキル(調理、PC操作、接客マナーなど)を学べる場合もあります。
ただし、アルバイトで身につくスキルには限界があります。
正社員のように、責任ある仕事を任されたり、専門的な研修を受けたりする機会は少ないため、キャリアアップには不利です。
ニートのスキル習得
ニートの場合、働いていないため、仕事に必要なスキルがほとんど身につきません。
自宅で過ごす時間が長いため、以下のような問題が生じやすくなります。
- 生活リズムの乱れ: 昼夜逆転の生活になり、朝起きて働くという基本的な習慣が失われる
- コミュニケーション能力の低下: 人と接する機会が減り、会話がうまくできなくなる
- 社会性の欠如: 職場でのルールやマナーを学ぶ機会がないため、社会適応が難しくなる
ただし、ニート期間中に独学で資格取得やスキル習得に取り組んでいる人もいます。
プログラミング、Webデザイン、語学など、自宅で学べるスキルを身につければ、就職活動で有利になる可能性があります。
スキル習得面の比較表
| 項目 | フリーター | ニート |
|---|---|---|
| 仕事の基礎スキル | ✅ アルバイトで習得可能 | ❌ 習得機会なし |
| コミュニケーション能力 | ✅ 職場で鍛えられる | ❌ 低下しやすい |
| 専門スキル習得 | △ 限定的だが可能 | △ 独学次第で可能 |
| 生活習慣 | ✅ 働くリズムが保たれる | ❌ 乱れやすい |
私の知人で、ニート期間中に独学でプログラミングを学び、ポートフォリオを作成してIT企業に就職した人がいます。
彼は「ニート期間は無駄だったとは思わない。
この期間に集中してスキルを磨けたから、今の仕事ができている」と話していました。
フリーターもニートも、それぞれにメリット・デメリットがありますが、大切なのは「今の状態から次のステップへ進む」という意識を持つことです。
どちらの状態であっても、行動を起こせば必ず道は開けますよ。
フリーターは経済面・就職活動・将来性のすべての面でニートより有利です。
ただし、年齢を重ねるほど正社員への転職は難しくなるため、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
「フリーター」と「ニート」のメリット・デメリット
ここでは、フリーターとニートそれぞれのメリットとデメリットを客観的に見ていきます。
どちらの状態にも良い面と悪い面があるため、冷静に理解することが大切です。
自分の現状を振り返りながら、今後のキャリアを考えるヒントにしてください。
フリーターの3つのメリット
フリーターという働き方には、正社員にはない自由さや柔軟性があります。
ここでは、フリーターの主なメリットを3つ紹介します。
① 時間の融通が利く
フリーター最大のメリットは、自分の時間をコントロールしやすいという点です。
シフト制のアルバイトであれば、働く曜日や時間帯を自分で調整できます。
「平日は働いて、週末は趣味に没頭する」「午前中だけ働いて、午後は資格の勉強をする」といった柔軟な働き方が可能です。
夢を追いかけている人や、スキルアップのために時間を確保したい人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
私の知人で、バンド活動をしながらコンビニでアルバイトをしている人がいます。
彼は「正社員だと、ライブやリハーサルの予定を入れるのが難しい。
フリーターなら、シフトを調整して音楽活動ができるから助かっている」と話していました。
② 仕事の責任が比較的軽い
フリーターは、正社員に比べて仕事の責任が軽いというメリットもあります。
重要なプロジェクトを任されたり、部下の管理をしたりすることはほとんどありません。
「失敗したらどうしよう」「責任を取らされるのが怖い」といったプレッシャーが少ないため、精神的な負担が軽くなります。
人間関係のストレスも、正社員に比べれば少ない傾向にあります。
③ さまざまな仕事を経験できる
フリーターは、複数のアルバイトを掛け持ちしたり、転々としたりすることで、さまざまな職種を経験できるというメリットがあります。
接客、事務、倉庫作業、イベントスタッフなど、多様な仕事を体験することで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。
「正社員になる前に、色々な仕事を試してみたい」という人にとっては、有益な経験になるでしょう。
フリーターの5つのデメリット
一方で、フリーターには多くのデメリットもあります。
特に、長期的に見ると不利な点が多いため、注意が必要です。
① 収入が不安定
フリーター最大のデメリットは、収入が不安定という点です。
時給制や日給制のため、働いた分しか給料がもらえません。
病気や怪我で働けなくなると、収入がゼロになってしまいます。
また、ボーナスがないため、年収は正社員に比べて大幅に低くなります。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、正社員の平均年収は約531万円ですが、非正規雇用(フリーター含む)の平均年収は約306万円と、225万円もの差があります。
【出典】
② 昇給やキャリアアップが難しい
フリーターは、昇給がほとんどないというデメリットもあります。
時給が上がったとしても、数十円〜数百円程度で、大幅な収入アップは期待できません。
また、責任ある仕事を任されることが少ないため、キャリアアップの機会もほとんどありません。
同じアルバイトを5年続けても、スキルや経験が十分に積み上がらず、正社員への転職が難しくなる可能性があります。
③ 社会保険や福利厚生が不十分
フリーターは、社会保険や福利厚生が不十分なケースが多いです。
勤務時間や条件によっては、健康保険や厚生年金に加入できないこともあります。
その場合、国民健康保険や国民年金に自分で加入する必要があり、保険料の負担が重くなります。
また、有給休暇や退職金、住宅手当などの福利厚生も、正社員に比べて大幅に劣ります。
④ 年齢を重ねるほど就職が難しくなる
フリーター期間が長引くと、正社員への就職がどんどん難しくなるというデメリットがあります。
20代であれば「若さ」という武器がありますが、30代に入ると、企業は「なぜ今まで正社員にならなかったのか?」と疑問を持ちます。
特に、35歳を過ぎると、未経験職種への転職はほぼ不可能になります。
年齢を重ねるほど、フリーターから抜け出すハードルが高くなるため、早めの行動が重要です。
⑤ 社会的信用が得られにくい
フリーターは、社会的信用が得られにくいというデメリットもあります。
クレジットカードの審査やローンの審査が通りにくく、賃貸契約でも不利になることがあります。
また、結婚相手を探す際にも「収入が不安定」という理由で敬遠されるケースが少なくありません。
「将来が不安」という理由で、恋愛や結婚がうまくいかないこともあります。
ニートのメリット(あえて挙げるなら)
ニートという状態には、正直なところ、メリットはほとんどありません。
それでも、あえて挙げるとすれば、以下のような点が考えられます。
① 時間が自由に使える
ニートは、働いていないため、時間が完全に自由です。
朝起きる時間も、夜寝る時間も、すべて自分で決められます。
趣味に没頭したり、好きなことをしたりする時間がたっぷりあります。
ただし、この「自由」は、経済的な自立がないため、実質的には「親に依存した自由」に過ぎません。
本当の意味での自由とは言えないでしょう。
② 仕事のストレスがない
ニートは、働いていないため、職場での人間関係や業務上のストレスがないという点も挙げられます。
上司に怒られることも、ノルマに追われることもありません。
ただし、働かないことによる別のストレス(親からのプレッシャー、将来への不安、社会的孤立など)が生じるため、結局は精神的な負担が大きくなる傾向があります。
③ 自分と向き合う時間がある
ニート期間を前向きに捉えれば、自分と向き合う時間として活用できる可能性があります。
「本当にやりたいことは何か?」「自分に合った仕事は何か?」を深く考える時間を持てるという点です。
ただし、ただ漠然と時間を過ごすだけでは意味がありません。
自己分析をしたり、スキルを身につけたりする努力をしない限り、ニート期間は「無駄な時間」になってしまいます。
正直に言えば、ニートのメリットはほとんどありません。
一時的な休息としてニート期間を過ごすのは理解できますが、長期化すると取り返しのつかないことになります。
ニートの5つのデメリット
ニートには、非常に多くのデメリットがあります。
特に、長期的に見ると、人生全体に深刻な影響を及ぼすリスクが高いです。
① 収入がゼロで経済的に自立できない
ニート最大のデメリットは、収入が一切ないという点です。
親や家族の支援に完全に依存しているため、経済的な自立ができません。
自分でお金を稼いでいないため、欲しいものを買うことも、旅行に行くことも、すべて親の許可や支援が必要になります。
親が高齢になったり、亡くなったりすると、生活が一気に困窮するリスクがあります。
② 社会的スキルや経験が身につかない
ニートは、働いていないため、仕事に必要なスキルや社会経験が一切身につきません。
コミュニケーション能力、時間管理能力、チームワークなど、社会人として必要な基礎的な能力が育たないため、いざ就職しようとした時に大きなハードルになります。
また、生活リズムが乱れやすく、昼夜逆転の生活になってしまうケースも多いです。
朝起きて働くという基本的な習慣が失われると、就職後の適応が非常に難しくなります。
③ 就職活動で空白期間の説明が困難
ニートは、履歴書に何年もの空白期間ができてしまうため、就職活動で大きな不利になります。
企業の採用担当者は必ず「この期間、何をしていたのか?」と質問しますが、説得力のある答えを用意するのは非常に難しいです。
空白期間が長いほど、「働く意欲がない」「問題がある人物」という印象を持たれやすくなり、書類選考すら通らないケースも増えてきます。
④ 社会的孤立と精神的な不調
ニートは、社会との接点が少ないため、孤立しやすくなります。
友人は正社員として働き、結婚や昇進をしていく中で、自分だけが取り残されたような気持ちになり、劣等感や焦りが募ります。
また、人と接する機会が減ることで、コミュニケーション能力が低下し、人と話すこと自体が怖くなってしまうケースもあります。
引きこもり状態になると、さらに社会復帰が難しくなります。
精神的にも、うつ病や不安障害などのリスクが高まります。
「このままでいいのか?」「将来はどうなるのか?」という不安が常に付きまとい、自己肯定感が低下していきます。
⑤ 親が高齢化・亡くなった後の生活困窮リスク
ニートが最も恐れるべきは、親が高齢化したり、亡くなったりした後の生活です。
親の支援に依存している限り、親がいなくなった時点で収入源が途絶えます。
貯金もスキルもない状態で、いきなり自立しなければならなくなると、生活保護を受けるしかない状況に陥る可能性があります。
また、親の介護が必要になった場合、収入がないため、介護費用を捻出することもできません。
厚生労働省の調査によると、ニート期間が長期化するほど、社会復帰の成功率は低下します。
1年以内のニート期間であれば、比較的スムーズに就職できますが、3年以上になると、就職率が大幅に下がるというデータもあります。
【出典】
私の知人の弟さんは、5年間ニート状態でしたが、親が病気になったことをきっかけに「このままではいけない」と奮起し、地域若者サポートステーションの支援を受けて就職しました。
彼は「親に何かあった時、自分が支えられるようにならないといけないと気づいた」と話していました。
フリーターにもニートにも、それぞれメリット・デメリットがありますが、長期的に見れば、どちらも正社員を目指すべき状態です。
現状を冷静に見つめ直し、次のステップへ進む行動を起こすことが大切ですよ。
「フリーター」や「ニート」を続けるリスクと将来の末路
フリーターやニートという状態を続けると、将来的にどのようなリスクがあるのでしょうか?
ここでは、現実的な視点から、長期的にフリーターやニートを続けた場合に待ち受ける厳しい現実について解説します。
決して脅すつもりはありませんが、事実を知ることで、今後の行動を考えるきっかけにしていただければと思います。
年齢を重ねるほど就職が困難になる
フリーターやニートを続ける最大のリスクは、年齢を重ねるほど正社員への就職が困難になるという点です。
20代の就職状況
20代であれば、フリーターからでもニートからでも、正社員への就職チャンスは十分にあります。
企業も「若さ」や「伸びしろ」を評価してくれるため、未経験職種への挑戦も可能です。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、20〜24歳のフリーターから正社員への移行率は約32.7%と、比較的高い数値を示しています。
この年齢層であれば、「まだ若いから大丈夫」と考える企業も多いです。
30代の就職状況
しかし、30代に入ると状況は一変します。
同調査によると、30〜34歳のフリーターから正社員への移行率は約18.1%と、20代の半分近くまで下がります。
さらに、35〜39歳になると約15.5%まで低下します。
企業側は「なぜ30代になってもフリーターなのか?」「今まで何をしていたのか?」という疑問を持ち、採用に慎重になります。
特に、35歳を過ぎると「中年フリーター」と呼ばれるようになり、未経験職種への転職はほぼ不可能になります。
【出典】
40代以降の絶望的な状況
40代になると、フリーターやニートから正社員になるのは、ほぼ絶望的です。
企業は即戦力を求めるため、未経験の40代を採用するメリットがほとんどありません。
この年齢になると、「このままフリーターを続けるしかない」「生活保護に頼るしかない」という状況に追い込まれる人も少なくありません。
親の年金や貯金に頼っていた人も、親が亡くなると収入源が途絶え、生活が一気に困窮します。
年齢別の正社員移行率
| 年齢層 | フリーター→正社員の移行率 |
|---|---|
| 15〜19歳 | 29.9% |
| 20〜24歳 | 32.7% |
| 25〜29歳 | 25.5% |
| 30〜34歳 | 18.1% |
| 35〜39歳 | 15.5% |
この表を見れば分かる通り、年齢を重ねるごとに、正社員になるチャンスは確実に減っていきます。
だからこそ、できるだけ早い段階で行動を起こすことが重要なんです。
私の知人で、38歳までフリーターを続けていた人がいました。
彼は「20代の時は『まだ大丈夫』と思っていたけど、気づいたら30代後半。今になって本気で後悔している」と話していました。
幸い、職業訓練を受けて資格を取得し、なんとか正社員として就職できましたが、「もっと早く動いていれば、選択肢が広がっていた」と悔やんでいました。
生涯年収で大きな差が生まれる
フリーターやニートを続けることで、生涯年収に致命的な差が生まれるというリスクがあります。
正社員とフリーターの年収差
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、正社員の平均年収は約531万円ですが、非正規雇用(フリーター含む)の平均年収は約306万円です。
年間で約225万円もの差があります。
【出典】
これを生涯で計算すると、驚くべき差が生まれます。
生涯年収の比較(22歳〜60歳まで働いた場合)
- 正社員: 約531万円 × 38年 = 約2億円
- フリーター: 約306万円 × 38年 = 約1億1,600万円
- 差額: 約8,400万円
つまり、フリーターを続けると、正社員に比べて生涯で8,400万円も収入が少なくなるのです。
これは、家を1軒買えるほどの金額です。
さらに、フリーターにはボーナスがないため、実際の年収はもっと低くなります。
また、昇給もほとんどないため、年齢を重ねても収入が増えません。
ニートの場合はさらに深刻
ニートの場合、収入がゼロのため、生涯年収もゼロです。
親の支援に頼り続けた場合、親が亡くなった後は貯金を切り崩すか、生活保護を受けるしかありません。
厚生労働省の調査によると、生活保護を受給している人の中には、長期ニートだった人が一定数含まれていると報告されています。
親の遺産があれば一時的にしのげますが、いずれは困窮するリスクが非常に高いです。
老後資金の不足
正社員であれば、厚生年金に加入しているため、老後の年金受給額も多くなります。
一方、フリーターは国民年金のみの加入が多いため、受給額が少なくなります。
- 正社員の年金受給額(平均): 月額約14〜16万円
- フリーター(国民年金のみ)の年金受給額: 月額約6.5万円
この差は、老後の生活に大きな影響を与えます。
月6.5万円では、家賃や食費、医療費を賄うのが精一杯で、ゆとりのある生活は望めません。
社会的信用が得られない
フリーターやニートを続けると、社会的信用が得られず、生活のあらゆる場面で不利になるというリスクがあります。
クレジットカードやローンの審査が通らない
フリーターは収入が不安定なため、クレジットカードの審査やローンの審査が通りにくくなります。
特に、住宅ローンや自動車ローンなど、高額なローンはほぼ審査に通りません。
ニートの場合は、収入がゼロのため、審査に通ることはまずありません。
クレジットカードすら作れないため、現金払いしかできず、日常生活でも不便を感じることが多くなります。
賃貸契約が難しい
賃貸物件を借りる際にも、フリーターやニートは不利です。
大家さんや不動産会社は「家賃を滞納するリスクが高い」と判断し、契約を断られるケースがあります。
特に、ニートの場合は、親が保証人になっても契約できないこともあります。
結果的に、実家を出て一人暮らしをすることが難しくなります。
結婚が困難になる
フリーターやニートは、結婚相手としても敬遠されやすくなります。
特に、男性の場合、「経済力がない」という理由で、恋愛対象から外されることが多いです。
結婚相談所や婚活サイトでも、フリーターやニートは「収入が不安定」という理由でマッチングしにくくなります。
たとえ恋人ができても、相手の親から結婚を反対されるケースも少なくありません。
社会的孤立
フリーターやニートを続けると、友人や知人との関係も疎遠になりがちです。
同世代の友人が正社員として働き、結婚や出世をしていく中で、自分だけが取り残されたような気持ちになります。
同窓会に行っても、「今何してるの?」と聞かれるのが怖くて、参加できなくなる人も多いです。
SNSで友人の充実した生活を見るたびに、劣等感や焦りが募り、精神的に追い詰められていきます。
別の知人で、33歳までフリーターだった人がいましたが、彼は「友人の結婚式に呼ばれても、『フリーターの自分が行っていいのか』と悩んで、結局行けなかった。それから友人とも疎遠になってしまった」と寂しそうに話していました。
老後の生活が困窮する可能性
フリーターやニートを続けた場合、老後の生活が非常に厳しくなるというリスクがあります。
年金受給額が少ない
フリーターの多くは国民年金のみに加入しているため、老後の年金受給額は月額約6.5万円程度です。
この金額では、家賃、食費、医療費、光熱費を賄うのが精一杯で、ゆとりのある生活は望めません。
ニートの場合、国民年金保険料を支払っていないケースも多く、その場合は年金を受け取れない可能性もあります。
無年金状態になると、老後は生活保護に頼るしかなくなります。
貯蓄がない
フリーターは収入が少ないため、貯蓄をする余裕がほとんどありません。
若い頃は「老後なんてまだ先の話」と考えがちですが、気づいた時にはもう手遅れという状況になります。
総務省の「家計調査」によると、老後の生活には最低でも月額約22万円が必要とされています。
年金だけでは到底足りないため、貯蓄を切り崩して生活することになります。
しかし、貯蓄がなければ、生活は破綻します。
【出典】
医療費の負担が重い
高齢になると、医療費の負担が増えます。
正社員であれば、会社の健康保険組合が充実しているため、医療費の自己負担が少なくなりますが、フリーターやニートは国民健康保険のみのため、負担が重くなります。
特に、慢性疾患や大きな病気にかかった場合、医療費が払えずに治療を諦めるケースもあります。
孤独死のリスク
フリーターやニートを続けた結果、社会的に孤立し、家族や友人との関係も疎遠になると、老後に孤独死するリスクが高まります。
一人暮らしで誰にも看取られずに亡くなる「孤独死」は、近年増加しています。
特に、経済的に困窮し、社会とのつながりが薄い人ほど、このリスクが高くなります。
生活保護に頼る未来
フリーターやニートを続けた結果、老後は生活保護に頼らざるを得なくなる人も少なくありません。
厚生労働省の統計によると、生活保護受給者の中には、長期フリーターや元ニートだった人が一定数含まれています。
生活保護を受給すること自体は悪いことではありませんが、最低限の生活しか保障されないため、ゆとりのある老後は望めません。
私の遠い親戚に、60代までフリーターを続けていた人がいました。
彼は貯蓄もなく、年金も少ないため、現在は生活保護を受けながら暮らしています。
「若い頃に正社員になっておけばよかった」と後悔していますが、もう取り返しがつきません。
フリーターやニートを続けることは、目先の楽さと引き換えに、将来の人生を犠牲にすることです。
今はまだ若くて実感が湧かないかもしれませんが、確実にリスクは迫っています。
手遅れになる前に、今から行動を起こすことが大切ですよ。
フリーターやニートを続けると、生涯年収で8,400万円以上の差が生まれ、老後は生活困窮のリスクが高まります。
手遅れになる前に、地域若者サポートステーションやハローワークなどの支援機関を活用しましょう。
【クイズ】「フリーター」と「ニート」を正しく使い分け
ここまで、フリーターとニートの違いを詳しく解説してきました。
では、実際に具体的なケースを見て、正しく判断できるかチェックしてみましょう!
ケース①:コンビニでアルバイトしながら夢を追う23歳
【ケース①の状況】
Aさん(23歳・男性)は、大学を卒業後、正社員としては就職せず、現在コンビニでアルバイトをしています。
週5日、1日8時間勤務で、月収は約16万円です。
彼の夢はミュージシャンになることで、アルバイトが終わった後や休日には、バンド活動やライブ、音楽制作に時間を費やしています。
「正社員になると、音楽活動の時間が取れなくなる。今はアルバイトで生活費を稼ぎながら、夢を追いかけたい」とAさんは話しています。
【問題】
Aさんは「フリーター」「ニート」のどちらに該当するでしょうか?
【答え】
フリーター
【解説】
Aさんは、コンビニでアルバイトとして実際に働いて収入を得ているため、フリーターに該当します。
たとえ正社員ではなくても、パート・アルバイトという形で働いている以上、厚生労働省の定義ではフリーターです。
フリーターの条件は「15〜34歳で、アルバイトやパートとして働いている人」または「アルバイト・パートを探している人」です。
Aさんは前者に該当しますね。
夢を追いかけるために、あえてフリーターという働き方を選ぶ人は少なくありません。
「夢追求型フリーター」と呼ばれるタイプです。
ただし、年齢を重ねるほど正社員への転職が難しくなるため、いつまでに夢を諦めるか、または夢と仕事を両立する道を見つけるかを考えることが大切です。
私の知人にも、俳優を目指しながらカフェでアルバイトをしている人がいます。
彼は「30歳までに芽が出なければ、正社員を目指す」と期限を決めて頑張っています。
このように、明確な期限や計画を持つことが重要ですね。
ケース②:就職活動をせず家にいる22歳の大卒者
【ケース②の状況】
Bさん(22歳・女性)は、今年の3月に大学を卒業しましたが、現在は無職です。
在学中に就職活動をしましたが、希望する企業から内定をもらえず、「もう就職活動をするのが嫌になった」と、卒業後は求職活動を一切していません。
現在は実家で暮らしており、家事も手伝わず、特に何もせずに毎日を過ごしています。
親から「働きなさい」と言われていますが、「やりたい仕事が見つからない」「どうやって仕事を探せばいいか分からない」と、動き出せない状態が続いています。
【問題】
Bさんは「フリーター」「ニート」のどちらに該当するでしょうか?
【答え】
ニート
【解説】
Bさんは、働いておらず、求職活動もしておらず、通学も家事もしていないため、ニートに該当します。
ニートの定義は「15〜34歳で、非労働力人口(働いていない、かつ求職活動もしていない)のうち、家事も通学もしていない人」です。
Bさんはまさにこの条件に当てはまります。
「就職活動がうまくいかなかった」という理由でニート状態になる人は少なくありません。
何度も面接で落ちると、自信を失い、「また落ちるのではないか」という恐怖から、求職活動ができなくなってしまうんです。
ただし、Bさんのような状態は「求職型ニート」と呼ばれ、働きたい気持ちはあるけれど動けないというタイプです。
このタイプのニートは、適切な支援を受ければ社会復帰できる可能性が高いです。
地域若者サポートステーションやハローワークでは、就職活動に不安を感じている人向けのカウンセリングやセミナーを実施しています。
一人で悩まず、こうした支援機関を活用することが、ニートから抜け出す第一歩になります。
【出典】
私の友人の弟さんも、大学卒業後に就職活動がうまくいかず、半年ほどニート状態になっていました。
しかし、地域若者サポートステーションでカウンセリングを受け、履歴書の書き方や面接対策を学んだことで、無事に正社員として就職できたそうです。
「一人で悩んでいた時は出口が見えなかったけど、相談したら道が開けた」と話していました。
ケース③:35歳以上の無業者はどう呼ばれる?
【ケース③の状況】
Cさん(37歳・男性)は、大学卒業後、いくつかのアルバイトを転々としてきましたが、現在は無職です。
求職活動もしておらず、実家で両親と暮らしています。
家事も手伝わず、特に何もせずに過ごしている状態です。
Cさんは、かつては「ニート」と呼ばれていましたが、35歳を過ぎてからは周囲の呼び方が変わってきました。
【問題】
35歳以上の無業者は、何と呼ばれるでしょうか?
【答え】
中年無業者(または中年ニート)
【解説】
厚生労働省や総務省統計局の定義では、ニートは15〜34歳までとされています。
つまり、35歳を過ぎると、公式には「ニート」という呼び方は使われなくなります。
その代わりに、35歳以上の無業者は「中年無業者」と呼ばれることが多いです。
一部では「中年ニート」「高齢ニート」「壮齢ニート」とも呼ばれますが、公式な定義としては「中年無業者」が一般的です。
【出典】
35歳を境に何が変わるのか?
35歳を過ぎると、呼び方が変わるだけでなく、就職支援の対象から外れるケースが増えます。
たとえば、「わかものハローワーク」は34歳までが対象のため、35歳以上は利用できません。
ただし、2024年10月現在、地域若者サポートステーション(サポステ)は、就職氷河期世代対策として一時的に49歳まで利用可能となっています。
これは35歳以上の無業者にとって大きなチャンスです。
中年無業者の厳しい現実
35歳以上の無業者は、若年ニートに比べてさらに就職が困難になります。
企業は即戦力を求めるため、職歴がない、またはアルバイト経験しかない37歳を採用するメリットがほとんどありません。
また、親も高齢化しているため、経済的な支援が難しくなります。
親が病気になったり、亡くなったりすると、収入源が途絶え、生活が一気に困窮するリスクが高まります。
総務省の調査によると、2022年時点で35〜44歳の中年無業者は約36万人いると報告されています。
彼らの多くは、若い頃にニート状態だった人が、そのまま年齢を重ねたケースです。
【出典】
35歳を過ぎても諦めない
ただし、35歳を過ぎたからといって、社会復帰が不可能なわけではありません。
職業訓練を受けて資格を取得したり、介護職や警備員など人手不足の業界を狙ったりすれば、就職のチャンスはあります。
地域若者サポートステーション(49歳まで利用可能)や、ハローワークの「生涯現役支援窓口」など、中高年向けの就職支援も充実してきています。
諦めずに行動を起こすことが大切です。
私の遠い親戚に、40歳までニート状態だった人がいましたが、職業訓練校で介護の資格を取得し、現在は介護施設で正社員として働いています。
彼は「40歳を過ぎても、やり直せる。遅すぎることはない」と前向きに話していました。
クイズを通じて、フリーターとニートの違いを理解できましたか?
大切なのは、自分が今どの状態にあるのかを正しく認識し、次のステップへ進むための行動を起こすことです。
年齢を重ねるほど難しくなるのは事実ですが、諦めなければ道は必ず開けますよ!
「フリーター」と「ニート」に関するQ&A
ここでは、フリーターとニートに関して、よくある質問にQ&A形式で答えていきます。
記事を読んで生まれた疑問を解消して、理解を深めていきましょう。
フリーターとニートは企業からの印象に違いがある?
Q. フリーターとニートは、企業からの印象に違いがありますか?
A. はい、大きな違いがあります。フリーターは「働いている」という点で評価される一方、ニートは「空白期間」の説明が必要になり、不利になりやすいです。
企業の採用担当者は、フリーターに対しては「正社員ではないものの、働く意欲はある」「最低限の社会経験は積んでいる」という見方をすることが多いです。
アルバイトであっても、接客スキルやコミュニケーション能力、時間管理能力などは身についているため、研修で順応しやすいと判断されます。
一方、ニートに対しては、「働く意欲がない」「社会性に欠ける」「生活リズムが乱れている可能性がある」といったネガティブな印象を持たれやすいです。
厚生労働省の「雇用管理調査」(2004年)によると、フリーター経験をプラス評価する企業はわずか3.6%ですが、ニートに対してはさらに厳しい評価になると考えられます。
ただし、これは一般的な傾向であって、企業や採用担当者によって判断は異なります。
フリーターであってもニートであっても、「なぜその状態になったのか」「その期間に何を学んだか」「今後どうしたいのか」を明確に説明できれば、理解してくれる企業は必ずあります。
大切なのは、過去を言い訳にするのではなく、今から変わろうとする姿勢を見せることです。
前向きな姿勢と具体的な行動計画を示せば、採用のチャンスは広がりますよ。
フリーター歴は職歴として認められる?
Q. フリーターとして働いた期間は、履歴書に「職歴」として書いてもいいのでしょうか?
A. はい、フリーター期間は職歴として記載できます。ただし、書き方にはコツがあります。
履歴書の職歴欄には、アルバイトやパートの経験も記載できます。
特に、長期間(半年以上)同じ職場で働いた経験や、正社員と同等の業務を任されていた場合は、しっかりアピールすべきです。
職歴の書き方例:
接客業務、商品管理、レジ業務を担当
令和○年○月 一身上の都合により退職
ポイントは、単に「アルバイト」と書くだけでなく、具体的な業務内容を記載することです。
「接客業務」「在庫管理」「新人教育」など、どんなスキルを身につけたかを明確にしましょう。
また、短期間のアルバイトを繰り返している場合は、すべてを書く必要はありません。
応募する職種に関連する経験や、長期間勤務した職場を中心に記載するのがおすすめです。
面接では、「アルバイトで何を学んだか」「どんな工夫をしたか」「その経験を正社員としてどう活かせるか」を具体的に説明できるように準備しておきましょう。
フリーター経験を前向きにアピールすることで、採用の可能性は高まります。
私の知人で、5年間飲食店でアルバイトをしていた人がいましたが、履歴書に「接客業務を通じてコミュニケーション能力を磨き、新人教育も担当しました」と具体的に書いたことで、営業職に採用されたそうです。
35歳以上のニートはなんと呼ばれる?
Q. 35歳以上のニートは、何と呼ばれるのでしょうか?
A. 35歳以上の無業者は「中年無業者」と呼ばれることが一般的です。
厚生労働省や総務省統計局の定義では、ニートは15〜34歳までとされています。
35歳を過ぎると、公式には「ニート」という呼び方は使われなくなり、代わりに「中年無業者」と呼ばれます。
一部では「中年ニート」「高齢ニート」「壮齢ニート」とも呼ばれますが、統計上の正式な呼称は「中年無業者」です。
【出典】
総務省の調査によると、2022年時点で35〜44歳の中年無業者は約36万人いると報告されています。
彼らの多くは、若い頃にニート状態だった人が、そのまま年齢を重ねたケースです。
35歳を過ぎると、呼び方が変わるだけでなく、就職支援の対象から外れるケースもあります。
たとえば、「わかものハローワーク」は34歳までが対象のため、35歳以上は利用できません。
ただし、2024年10月現在、地域若者サポートステーション(サポステ)は、就職氷河期世代対策として一時的に49歳まで利用可能となっています。
これは35歳以上の無業者にとって大きなチャンスです。
【出典】
35歳を過ぎても、社会復帰は決して不可能ではありません。
職業訓練や資格取得、支援機関の活用など、できることはたくさんあります。
諦めずに一歩ずつ前に進むことが大切ですよ。
無職とニートの違いは?
Q. 無職とニートは、どう違うのでしょうか?
A. 無職は幅広い概念で、ニートはその中の特定の層を指します。最大の違いは「求職活動の有無」と「年齢」です。
無職とは、文字通り「職業がない状態」を指す言葉です。
働いていない人全般を指すため、以下のような人も含まれます。
- 求職活動をしている失業者
- 学生
- 専業主婦・主夫
- 年金生活者
- 病気療養中の人
- ニート
つまり、無職は非常に広い概念で、年齢制限もありません。
一方、ニートは、無職の中でも特定の条件を満たす人を指します。
- 年齢: 15〜34歳
- 状態: 働いておらず、求職活動もしていない
- 除外対象: 学生、主婦・主夫、家事をしている人
つまり、ニートは無職の一種ですが、無職すべてがニートではないということです。
具体例で考えてみましょう:
- ケース①: 25歳で求職活動をしている人 → 無職(失業者)だが、ニートではない
- ケース②: 30歳で働いておらず、求職活動もしていない人 → 無職であり、ニート
- ケース③: 40歳で働いておらず、求職活動もしていない人 → 無職だが、ニートではない(年齢が34歳を超えているため)
- ケース④: 22歳の学生 → 無職だが、ニートではない(学生は除外対象)
このように、無職とニートは重なる部分もありますが、明確な違いがあります。
ニートは「働く意欲がない、または求職活動をしていない若年無業者」という、より限定的な概念なんですね。
引きこもりとニートの違いは?
Q. 引きこもりとニートの違いは何ですか?
A. 引きこもりは「社会参加を回避し、6ヶ月以上家庭にとどまり続ける状態」を指し、ニートは「働いておらず、求職活動もしていない15〜34歳の若者」を指します。両者は重なる場合もありますが、異なる概念です。
厚生労働省によれば、引きこもりとは以下のような状態を指します。
さまざまな要因の結果として、社会参加(通学、就労、家庭外での交遊など)を回避しており、原則6ヶ月以上にわたり、おおむね家庭に留まり続ける状態
【出典】
引きこもりの特徴は、社会との接点が極めて少ないという点です。
他者と交流しない形での外出(コンビニへの買い物など)は可能でも、家庭外での社会的な活動を避けている状態を指します。
また、引きこもりには年齢制限がありません。
一方、ニートは、働いておらず求職活動もしていない15〜34歳の若者を指しますが、外出や他者との交流に制限はありません。
ニートであっても、友人と遊びに行ったり、趣味のイベントに参加したりすることは可能です。
引きこもりとニートの比較表
| 項目 | 引きこもり | ニート |
|---|---|---|
| 年齢 | 制限なし | 15〜34歳 |
| 社会参加 | 6ヶ月以上回避 | 制限なし |
| 外出 | 他者と交わらない形なら可 | 自由 |
| 働いているか | 働いていない | 働いていない |
| 求職活動 | していない | していない |
両方に該当するケースもある
引きこもりとニートは、両方の条件を満たす場合もあります。
たとえば、25歳で働いておらず、6ヶ月以上家から出ずに過ごしている人は、「引きこもりでありニートでもある」と言えます。
厚生労働省の調査によると、ニート全体の約49.5%が「ひきこもり経験がある」という結果も出ており、両者には深い関係があることが分かります。
【出典】
引きこもりもニートも、本人の意思だけでなく、家庭環境や社会的な要因が複雑に絡み合って生じることが多いです。
どちらの状態であっても、専門の支援機関に相談することで、社会復帰への道は開けます。
一人で抱え込まず、周囲に助けを求めることが大切ですよ。
以上で、フリーターとニートに関するよくある質問への回答は終わりです。
これらのQ&Aを通じて、さらに理解が深まったのではないでしょうか?
フリーターもニートも、今の状態から抜け出して、より安定した生活を目指すことが大切です。
年齢を重ねるほど難しくなるのは事実ですが、諦めずに行動を起こせば、必ず道は開けます。
地域若者サポートステーション、ハローワーク、職業訓練校など、さまざまな支援機関があるので、ぜひ活用してみてください。
あなたの人生は、これからいくらでも変えられます。小さな一歩から、勇気を持って踏み出してみましょう!
まとめ
フリーターとニートの最大の違いは「働く意思」と「収入の有無」です。
フリーターはアルバイトで収入を得て社会経験を積めますが、ニートは働いておらず、就職活動で空白期間の説明が必要になります。
どちらも年齢を重ねるほど正社員への就職は難しくなり、生涯年収や老後の生活に大きな影響を及ぼします。
ただし、フリーターからもニートからも正社員になることは可能です。
大切なのは、できるだけ早く行動を起こすこと。
地域若者サポートステーション、ハローワーク、職業訓練校など、さまざまな支援機関があなたの社会復帰をサポートしています。
今の状態を変えたいと思ったら、まずは一歩踏み出してみましょう。
あなたの未来は、今日の行動から変えられます!



















