
「適用」と「摘要」、どちらも「てきよう」と読みますが、意味はまったく違います。
契約書を作成していて「この規則を○○する」と書きたいとき、請求書の記載欄を見て「○○欄」と読むとき、どちらの漢字を使えばいいのか迷ったことはありませんか?

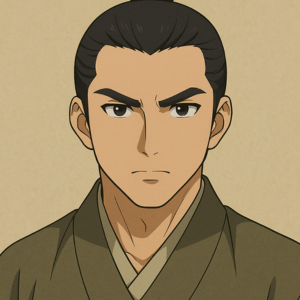
「適用」は法律や制度をあてはめるときに使い、「摘要」は書類の記載欄や要点をまとめるときに使います。
この記事では、それぞれの正しい意味と使い方を、具体例や比較表を使って分かりやすく解説していますので、最後までご覧ください。
「適用」と「摘要」の違いとは?
「適用」と「摘要」は、どちらも「てきよう」と読む同音異義語です。
発音が同じため、会話では区別がつきませんが、意味はまったく異なります。

ここでは、それぞれの意味の違いや混同されやすい理由について解説します。
それぞれの言葉の意味を解説
まず、それぞれの言葉の基本的な意味を確認しましょう。
「適用(てきよう)」の意味
「適用」とは、法律やルール、制度などをある対象にあてはめて使うことを意味します。
たとえば、「新しい税制を適用する」「割引制度を適用する」といった使い方をします。何かの基準や規則を実際に使う場面で用いられる言葉です。
「摘要(てきよう)」の意味
一方、「摘要」とは、大事な部分を抜き出して簡潔にまとめることを意味します。
主に書類や伝票の中で、取引内容や用件を短く記載する欄のことを「摘要欄」と呼びます。
請求書や領収書などでよく見かける言葉です。
このように、「適用」は「ルールをあてはめる」、「摘要」は「要点をまとめる」という、まったく異なる意味を持っています。
意味の違いを一言でまとめると?
それぞれの言葉の違いを一言でまとめると、次のようになります。
- 適用:ルールや制度を対象にあてはめて使うこと
- 摘要:重要な内容を抜き出して簡潔に書くこと
覚え方のコツとしては、「適用」の「適」という漢字には「ぴったり合う」という意味があり、「摘要」の「摘」には「つまむ・抜き出す」という意味があることを意識すると良いでしょう。
また、使われる場面も大きく異なります。
「適用」は法律や規則、制度に関する文脈で使われるのに対し、「摘要」は書類や伝票の記載欄として使われることがほとんどです。
文脈を考えれば、どちらを使うべきか判断しやすくなります。
なぜ混同されやすいのか?
「適用」と「摘要」が混同されやすい理由は、主に次の3つです。
1. 読み方が完全に同じ
どちらも「てきよう」と読むため、話し言葉では区別がつきません。
会議や電話での会話では、前後の文脈から判断するしかありません。
2. ビジネス文書で頻繁に登場する
どちらも契約書や請求書、報告書などのビジネス文書でよく使われる言葉です。
同じような場面で目にする機会が多いため、混同しやすくなります。
3. 漢字が似た印象を与える
「適」と「摘」はどちらも「てき」と読む漢字で、見た目も似ています。
さらに両方とも「要」という漢字を含んでいるため、視覚的にも混同しやすいのです。
特にパソコンやスマートフォンで文字入力する際、変換候補に両方が表示されるため、誤って選んでしまうミスが起こりがちです。
正しく使い分けるには、それぞれの意味をしっかり理解することが重要です。
「適用」の意味と使い方
「適用」は、法律や規則、制度などを具体的な対象にあてはめて使うことを意味する言葉です。
ビジネスや法律の場面で頻繁に使われ、何らかの基準やルールを実際のケースに適用する際に用いられます。
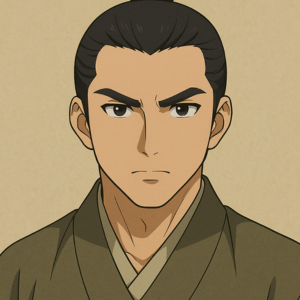
「適用」の正しい意味
「適用」という言葉は、次のような意味を持っています。
基本的な意味
「適用」とは、法律や規則、制度、方法などを、ある特定の対象や状況にあてはめて使うことです。
「適」という漢字には「ぴったり合う」「ふさわしい」という意味があり、「用」は「使う」という意味です。
つまり、既にあるルールや仕組みを、実際の場面に合わせて使うことを表します。
使われる主な場面
「適用」は、主に次のような場面で使われます。
- 法律や条例をある事例にあてはめる
- 制度や規則を特定の対象に使う
- 割引や特典を条件を満たす人に適用する
- 新しい方式や手法を業務に取り入れる
ポイントは、「すでに存在するもの」を「具体的な対象」にあてはめるという点です。
新しく何かを作るのではなく、既存のルールを使うという意味合いが強い言葉です。
ビジネスでの「適用」の使い方と例文
ビジネスシーンでは、「適用」は非常に多く使われる言葉です。
実際の使い方を例文で確認しましょう。
契約・法律関連の例文
- 「この契約には消費者契約法が適用されます」
- 「新しい労働基準法は来月から適用される予定です」
- 「軽減税率を適用した価格で請求いたします」
制度・規則関連の例文
- 「新入社員には試用期間中の給与規定が適用されます」
- 「早期割引制度を適用させていただきます」
- 「この案件には特別料金を適用することができます」
業務・手法関連の例文
- 「新しい管理システムを全部署に適用する」
- 「このプロジェクトには新しい手法を適用してみましょう」
- 「成功した戦略を他の商品にも適用できないか検討中です」
これらの例文から分かるように、「適用」は何か既存のもの(法律、制度、方法など)を、具体的な対象や状況にあてはめる際に使います。
「適応」との違い
「適用」とよく混同される言葉に「適応(てきおう)」があります。
読み方が似ているため、間違えやすい言葉です。
「適応」の意味
「適応」とは、環境や状況に合わせて、自分を変化させることを意味します。
外部の変化に対して、自分の側が調整するというニュアンスです。
使い分けのポイント
- 適用:ルールを対象にあてはめる(ルールが主体)
- 適応:環境に自分を合わせる(自分が主体)
比較例文
- 「新しい規則を社員に適用する」→ 規則を社員にあてはめる
- 「社員が新しい環境に適応する」→ 社員が環境に慣れる
- 「割引制度を適用する」→ 制度をあてはめる
- 「新しい職場に適応する」→ 自分が慣れる
このように、「適用」は外側から何かをあてはめる行為、「適応」は自分が変化して合わせる行為という違いがあります。
どちらが主体になるかを考えると、使い分けがしやすくなります。
「摘要」の意味と使い方
「摘要」は、重要な部分を抜き出して簡潔にまとめることを意味する言葉です。
特に請求書や領収書、伝票などの書類で、取引内容や用件を記載する欄として使われます。

ここでは、「摘要」の正しい意味や書類での使われ方、また似た言葉である「要約」との違いについて解説します。
「摘要」の正しい意味
「摘要」という言葉は、次のような意味を持っています。
基本的な意味
「摘要」とは、文章や資料の中から重要な部分を選び出し、要点を簡潔にまとめることです。
「摘」という漢字には「つまむ」「抜き取る」という意味があり、「要」は「大事な部分」を表します。
つまり、必要な情報だけを抜き出して、短くまとめることを意味します。
書類における「摘要」
現代のビジネスシーンでは、「摘要」は主に書類や伝票の記載欄として使われます。
特に次のような書類で目にすることが多いでしょう。
- 請求書や領収書の「摘要欄」
- 会計伝票の「摘要」
- 銀行の通帳明細の「摘要」
- 経理書類の「摘要」
これらの摘要欄には、取引の内容や目的、商品名やサービス内容など、その取引に関する重要な情報を簡潔に記載します。
長々と書くのではなく、必要最小限の情報をコンパクトにまとめるのがポイントです。
書類・伝票などでの「摘要」の使われ方
実際の書類で「摘要」がどのように使われているか、具体例を見てみましょう。
請求書の摘要欄の記載例
- 「2025年1月分コンサルティング料」
- 「ホームページ制作費(初期費用)」
- 「事務用品一式(詳細は別紙参照)」
- 「10月度広告掲載料」
領収書の摘要欄の記載例
- 「お品代として」
- 「会議費として」
- 「研修参加費として」
- 「交通費として」
銀行通帳の摘要表示例
- 「カ)ヤマダショウジ」(振込元の会社名)
- 「キュウヨ」(給与の振込)
- 「カードリヨウリョウ」(クレジットカード利用料)
会計伝票の摘要記載例
- 「取引先A社との会食費用」
- 「営業用パソコン購入」
- 「事務所賃料(10月分)」
このように、摘要欄には取引の内容が一目で分かるような簡潔な記載をします。
詳細な説明は別紙や備考欄に記載し、摘要欄にはポイントだけを書くのが一般的です。
経理処理や後から内容を確認する際に、摘要欄の情報が重要な手がかりとなります。
「要約」と「摘要」の違い
「摘要」と似た言葉に「要約(ようやく)」があります。
どちらも「まとめる」という意味合いがありますが、使い方には違いがあります。
「要約」の意味
「要約」とは、文章や話の内容を短くまとめることです。
長い文章の重要な部分を抽出して、短い文章に作り直すことを指します。
使い分けのポイント
- 摘要:書類の記載欄として使われることが多く、短いフレーズや単語で記載する
- 要約:文章をまとめる行為そのものを指し、ある程度の長さの文章になる
比較例文
- 「請求書の摘要欄に取引内容を記入する」→ 書類の欄に短く書く
- 「会議の内容を要約して報告する」→ まとめた文章を作る
- 「通帳の摘要を確認する」→ 記載されている項目を見る
- 「論文を要約する」→ 短い文章にまとめる
つまり、「摘要」は書類の記載欄や簡潔なメモ的な使い方が中心で、「要約」は文章をまとめる行為全般を指します。
「摘要」の方がより限定的で、実務的な場面で使われる言葉といえるでしょう。
「適用」と「摘要」の違いを一覧で比較
「適用」と「摘要」の違いを、より分かりやすく整理してみましょう。
それぞれの意味や使われる場面、具体的な例文を比較表で確認することで、使い分けのポイントが明確になります。
ここでは、両者の違いを一覧表で比較し、効果的な覚え方のコツについても解説します。
意味・使う場面・例文を比較表で整理
「適用」と「摘要」の違いを、表形式で整理すると次のようになります。
| 項目 | 適用(てきよう) | 摘要(てきよう) |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | ルールや制度を対象にあてはめて使うこと | 重要な部分を抜き出して簡潔にまとめること |
| 漢字の意味 | 適:ぴったり合う/用:使う | 摘:つまむ、抜き取る/要:大事な部分 |
| 主な使用場面 | 法律、契約、制度、規則など | 請求書、領収書、伝票、通帳など |
| よく使われる形 | 「○○を適用する」「適用される」 | 「摘要欄」「摘要に記載する」 |
| 例文1 | 新しい税制を適用する | 請求書の摘要欄に内容を記入する |
| 例文2 | 割引制度を適用させていただきます | 摘要には「会議費」と記載してください |
| 例文3 | この法律が適用されるケース | 通帳の摘要を確認する |
| 対象 | ルールや方法をあてはめる相手 | 書類の記載欄や要点 |
| 動作の主体 | ルールをあてはめる側 | 情報をまとめる側 |
比較から分かる重要なポイント
- 「適用」は何かを「使う・あてはめる」という動作を表す動詞的な使い方が中心
- 「摘要」は書類の「記載欄」としての使い方や、「まとめたもの」を指す名詞的な使い方が中心
- 使われる分野が明確に異なる(適用=法律・制度、摘要=書類・経理)
この表を見れば、文脈によってどちらを使うべきか判断しやすくなります。
違いを覚えるコツと覚え方のポイント
「適用」と「摘要」を確実に使い分けるための、効果的な覚え方を紹介します。
1. 漢字の意味から覚える方法
- 適用:「適」は「適切」「適当」など「ぴったり合う」という意味。ルールが対象にぴったり合うようにあてはめる
- 摘要:「摘」は「摘む(つまむ)」「摘出」など「つまみ取る」という意味。大事な部分をつまんで取り出す
この漢字の基本的な意味を覚えておけば、迷ったときに判断できます。
2. 使われる場面で覚える方法
- 適用:法律や制度の話 → 「法律を適用する」
- 摘要:書類や伝票の話 → 「摘要欄に書く」
どんな文書や会話の中で使われているかを考えれば、自然と正しい方を選べます。
3. セットフレーズで覚える方法
よく使われる決まった表現を覚えておくと便利です。
- 適用のセットフレーズ
- 「制度を適用する」
- 「法律が適用される」
- 「割引を適用する」
- 摘要のセットフレーズ
- 「摘要欄」
- 「摘要に記載する」
- 「摘要を確認する」
4. 言い換えて確認する方法
迷ったときは、別の言葉に置き換えてみましょう。
- 「適用」→「あてはめる」「使う」に置き換えられるか?
- 「摘要」→「要点」「記載欄」に置き換えられるか?
5. 実務での使用頻度から覚える方法
実際のビジネスシーンでは、次のような傾向があります。
- 契約書や規約では「適用」を使うことがほとんど
- 請求書や領収書では「摘要」(摘要欄)を使うことがほとんど
書類の種類で判断すると、間違いが減ります。
日常的に触れる書類で、どちらの言葉が使われているか意識してみると、自然と使い分けが身につくでしょう。
「適用」と「摘要」よくある間違いと注意点
「適用」と「摘要」は同音異義語であるため、書き間違いや変換ミスが起こりやすい言葉です。
特にビジネス文書では、誤用すると意味が通じなくなったり、相手に誤解を与えたりする可能性があります。

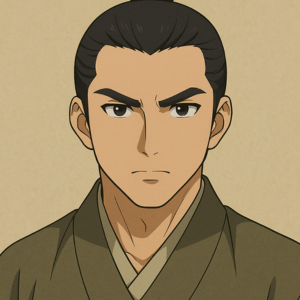
「適用」と「摘要」を誤用しやすい文例
実際のビジネスシーンで起こりがちな間違い例を見てみましょう。
誤用例1:書類関連での間違い
❌「請求書の適用欄にサービス内容を記入してください」
⭕「請求書の摘要欄にサービス内容を記入してください」
書類の記載欄は「摘要欄」です。
「適用欄」という言葉は存在しません。
誤用例2:制度関連での間違い
❌「この割引制度を摘要させていただきます」
⭕「この割引制度を適用させていただきます」
制度やルールをあてはめる場合は「適用」を使います。
誤用例3:法律関連での間違い
❌「この契約には消費者契約法が摘要されます」
⭕「この契約には消費者契約法が適用されます」
法律をあてはめる場合は必ず「適用」です。
誤用例4:通帳・伝票での間違い
❌「銀行通帳の適用を確認する」
⭕「銀行通帳の摘要を確認する」
通帳や伝票の記載内容を見る場合は「摘要」です。
誤用例5:説明文での間違い
❌「詳細は適用欄をご覧ください」
⭕「詳細は摘要欄をご覧ください」
書類の欄を指す場合は「摘要欄」が正しい表現です。
誤用例6:業務システムでの間違い
❌「経費精算システムの適要に目的を入力する」
⭕「経費精算システムの摘要に目的を入力する」
「適要」という言葉は存在しません。
記載欄の意味では「摘要」を使います。
これらの間違いは、パソコンやスマートフォンでの変換ミスによって起こることが多いため、入力後の確認が重要です。
正しい表現に直すポイント
間違いを防ぎ、正しい表現を使うためのチェックポイントを紹介します。
ポイント1:文脈で判断する
使っている文脈を確認しましょう。
- 法律・制度・ルールの話 → 「適用」
- 「税率を○○する」「制度を○○する」「規則が○○される」
- 書類・記載欄の話 → 「摘要」
- 「○○欄に書く」「伝票の○○」「通帳の○○を見る」
文脈を意識すれば、ほとんどの場合正しく判断できます。
ポイント2:「欄」がついたら「摘要」
「○○欄」という形で使われる場合は、必ず「摘要欄」です。「適用欄」という言葉は存在しません。
⭕ 摘要欄
❌ 適用欄
書類や入力フォームの項目名として使われる場合は、迷わず「摘要」を選びましょう。
ポイント3:動詞として使うなら「適用」
「する」「される」をつけて動詞として使う場合は、ほとんど「適用」です。
- 「制度を適用する」
- 「法律が適用される」
- 「割引を適用させていただく」
「摘要する」という表現もありますが、現代ではあまり使われず、「摘要欄」という名詞形での使用が圧倒的に多いです。
ポイント4:変換候補をよく確認する
パソコンやスマートフォンで「てきよう」と入力すると、次のような候補が出てきます。
- 適用
- 摘要
- 適応
- 的要(これは誤変換)
慌てて変換確定せず、候補をしっかり確認しましょう。
特に「適応」も混ざってくるため、三つの違いを理解しておくことが大切です。
ポイント5:書類を見直す習慣をつける
ビジネス文書を作成したら、次の点をチェックしましょう。
- 請求書や領収書では「摘要欄」になっているか
- 契約書や規約では「適用」になっているか
- 同じ文書内で使い分けが統一されているか
特に重要な書類では、提出前に必ず見直しを行い、誤用がないか確認する習慣をつけることをおすすめします。
自分だけでなく、可能であれば他の人にもチェックしてもらうと、より確実です。
「適用」と「摘要」に関するよくある質問
「適用」と「摘要」について、実務でよく寄せられる質問をまとめました。
請求書や契約書など、実際のビジネスシーンで迷いやすいポイントを、具体例を交えて分かりやすく回答します。
ここでは、書類作成時に役立つ実践的な情報をQ&A形式で解説します。
請求書の「摘要欄」には何を書くのが正しい?
請求書の摘要欄には、取引内容が一目で分かる情報を簡潔に記載します。
摘要欄に書くべき内容
摘要欄には、次のような情報を記載するのが一般的です。
- 商品名やサービス名
- 取引の対象期間(「○月分」など)
- 取引の目的や用途
- 数量や単位(必要に応じて)
- 補足情報(「詳細は別紙参照」など)
具体的な記載例
- 「2025年10月分コンサルティング業務」
- 「ホームページ制作費(初期構築)」
- 「オフィス用品一式」
- 「研修講師料(10/15実施分)」
- 「広告掲載料(3ヶ月分)」
記載時の注意点
摘要欄は限られたスペースなので、次の点に注意しましょう。
- 長文は避け、要点だけを簡潔に書く
- 専門用語は避け、誰が見ても分かる表現にする
- 詳細な説明が必要な場合は「詳細別紙」と記載し、別の書類を添付する
- 複数の項目がある場合は、明細欄で詳しく書き、摘要欄には総称を記載する
摘要欄の記載内容は、経理処理や税務調査の際に重要な情報となるため、正確で分かりやすく書くことが大切です。
契約書に「適用」と「摘要」どちらを使うべき?
契約書では、ほとんどの場合「適用」を使います。
「摘要」を使う場面はほぼありません。
契約書で「適用」を使う場面
契約書では、次のような文脈で「適用」が使われます。
- 「本契約には日本国の法律が適用されます」
- 「消費税法に基づく税率を適用します」
- 「早期契約割引を適用した金額とします」
- 「本規約は○年○月○日より適用されます」
- 「準拠法として民法の規定を適用します」
これらはすべて、法律やルール、制度を契約にあてはめるという意味なので、「適用」が正しい表現です。
契約書で「摘要」は使わない理由
「摘要」は書類の記載欄や要点をまとめたものを指す言葉です。
契約書は、条項や条件を詳しく記載する文書であり、簡潔にまとめる「摘要」という概念とは異なります。
ただし、契約に添付する請求書や支払明細などの書類に「摘要欄」がある場合は、その欄には「摘要」という言葉が使われます。
しかし、契約書本文では「適用」を使うのが正しいです。
判断のポイント
- 法律や条件をあてはめる → 「適用」
- 記載欄や要約 → 「摘要」
契約書では法的な効力を持つ条項を定めるため、「適用」を使うと覚えておきましょう。
公文書や報告書ではどう使い分ける?
公文書や報告書では、文脈に応じて「適用」と「摘要」を正しく使い分ける必要があります。
公文書での使い分け
公文書では、次のように使い分けます。
「適用」を使う場面
- 「本条例は○年○月○日より適用する」
- 「この規則は全職員に適用される」
- 「特例措置を適用した場合の計算方法」
- 「関係法令を適用して判断する」
法令や規則を具体的なケースにあてはめる場合は「適用」です。
「摘要」を使う場面
- 「予算書の摘要欄に事業名を記載する」
- 「支出伝票の摘要に使途を明記すること」
- 「摘要:会議出席のための交通費」
書類の記載欄や簡潔な説明には「摘要」を使います。
報告書での使い分け
報告書では、次のような使い分けになります。
「適用」を使う場面
- 「新しい評価基準を適用した結果」
- 「統計手法を適用して分析した」
- 「この方式を適用することで効率化が図れる」
手法や基準をあてはめる場合は「適用」です。
「摘要」を使う場面
- 報告書に添付する経費明細の「摘要欄」
- 「各項目の摘要は表の通り」(表の要約部分を指す場合)
ただし、報告書本文では「摘要」を使う機会は少なく、「要約」や「概要」という言葉の方が一般的です。
迷ったときの判断基準
公文書や報告書で迷ったら、次の基準で判断しましょう。
- ルールや方法をあてはめる内容なら → 「適用」
- 書類の記載欄なら → 「摘要」
- 内容を短くまとめる行為なら → 「要約」または「概要」
公文書は正確性が求められるため、特に慎重に使い分けることが大切です。
不安な場合は、過去の同様の文書を参考にしたり、上司や関係部署に確認したりすることをおすすめします。
まとめ
「適用」と「摘要」は、どちらも「てきよう」と読む同音異義語ですが、意味と使い方はまったく異なります。
「適用」は、法律や制度、ルールなどを具体的な対象にあてはめて使うことを意味します。
契約書では「本契約には日本国の法律が適用されます」、ビジネスでは「割引制度を適用します」といった形で使われます。
何かの基準や規則を実際の場面にあてはめる際に用いる言葉です。
一方、「摘要」は、重要な部分を抜き出して簡潔にまとめることを意味し、特に書類や伝票の記載欄として使われます。
請求書や領収書の「摘要欄」、銀行通帳の「摘要」など、取引内容や用件を短く記載する場面で目にする言葉です。
使い分けのポイントは、法律や制度の話なら「適用」、書類の記載欄なら「摘要」と覚えておくことです。
また、漢字の意味からも区別できます。「適」は「ぴったり合う」、「摘」は「つまむ・抜き取る」という意味があるため、文脈に応じて判断しましょう。
パソコンやスマートフォンで入力する際は、変換候補をしっかり確認することが大切です。
特にビジネス文書では誤用が相手に誤解を与える可能性があるため、提出前に必ず見直しを行いましょう。
この記事で紹介した比較表や具体例を参考に、正しく使い分けられるようになれば、ビジネスシーンでの文書作成がよりスムーズになります。
迷ったときは、「ルールをあてはめるなら適用」「記載欄なら摘要」という基本に立ち返って判断してください。



















