
「初め」と「始め」、どちらも「はじめ」と読みますが、使い分けに迷ったことはありませんか?
うむ...
『年の初め』と『仕事始め』、どちらも『はじめ』なのに漢字が違うとは!
神のお告げでもわからぬぞ...
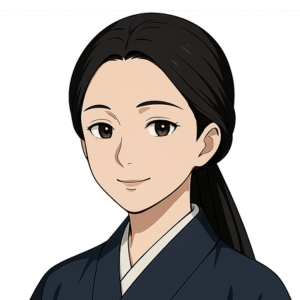
卑弥呼様、神頼みの前に使い分けのルールを学びましょう!
私も昔、幕府の公文書で間違えて赤っ恥をかきましたからね...
「年の初め」「仕事始め」「初めまして」など、日常やビジネスシーンで頻繁に使う言葉だからこそ、正しく使いたいものです。
この記事では、「初め」と「始め」の意味の違いから、具体的な使い分けのポイント、ビジネス文書での正しい表記まで、豊富な例文とともに徹底解説します。
「をはじめとする」「まず初めに」など、よくある疑問にも答えていきます。
読み終わる頃には、もう迷うことなく正しい漢字を選べるようになります。
楽しく読んで頂ける内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
「初め」と「始め」の違いとは?
「初め」と「始め」は、どちらも「はじめ」と読みますが、意味や使い方が異なります。
「初め」は時間的な最初や順序の1番目を表し、「始め」は動作や行為のスタートを表します。
この違いを理解すれば、文章を書くときに迷わず使い分けられるようになります。
「初め」の意味|時間的な最初・順序の1番目
「初め」は、時間の流れの中での「最初の時点」や、順番における「1番目」を指す言葉です。
状態や時期を表現するときに使われます。
「初め」の特徴:
🔵 時間的な最初を示す
例:「年の初め」「月の初め」「初めのころ」
🔵 順序の1番目を表す
例:「初めに挨拶をする」「名簿の初めに記載」
🔵 経験の最初を示す
例:「初めて訪れた場所」「初めての経験」
🔵 関連する言葉
「最初」「初回」「初期」「初日」など
私の同僚が、取引先へのメールで「年の始めにご挨拶」と書いて、上司から「これは『初め』が正しいよ」と指摘されていました。
「年が始まる」という動作ではなく、「1年の最初の時期」という時間を表しているため、「初め」を使うのが適切なんです。
「始め」の意味|動作・行為の開始・スタート
「始め」は、何かを「開始する」「スタートする」という動作や行為を表す言葉です。
動詞「始める」の名詞形として使われることが多いです。
「始め」の特徴:
🟢 動作の開始を示す
例:「仕事始め」「稽古始め」「会議を始める」
🟢 物事のスタートを表す
例:「プロジェクトの始め」「授業の始め」
🟢 「〜を始める」という動作と結びつく
例:「勉強を始める」「準備を始める」
🟢 関連する言葉
「開始」「スタート」「着手」「発端」など
違いを比較表で確認
「初め」と「始め」の違いを表で整理すると、次のようになります。
| 項目 | 初め | 始め |
|---|---|---|
| 意味 | 時間的な最初・順序の1番目 | 動作・行為の開始・スタート |
| 表すもの | 状態・時期・順番 | 動作・プロセス |
| キーワード | 「最初」「1番目」 | 「開始」「スタート」 |
| 例文 | 年の初め、初めて会った日 | 仕事始め、会議を始める |
| 関連語 | 最初、初回、初期、初日 | 開始、着手、スタート |
✓ 初め = 時間的な最初・順序の1番目を表す
✓ 始め = 動作・行為の開始・スタートを表す
✓ 迷ったら「最初」「開始」に置き換えて確認しよう
「初め」と「始め」の使い分けポイント
「初め」と「始め」を正しく使い分けるには、その言葉が「時間や順序」を表すのか、「動作や行為」を表すのかを判断することが重要です。
この基準を押さえれば、迷うことなく正しい漢字を選べるようになります。
ここでは具体的な判断方法と、簡単に見分けるコツを紹介します。
判断基準は「時間」か「行動」か
「初め」と「始め」を使い分ける最も重要なポイントは、その文脈が「時間的な概念」を表すのか、「動作的な概念」を表すのかを見極めることです。
「初め」を使う場面(時間・順序):
🔵 時間の流れの中の最初の時点
✓ 「年の初め」「月の初め」「初めのうちは難しかった」
🔵 順番の1番目
✓ 「初めに自己紹介をします」「リストの初めに書く」
🔵 最初の体験や経験
✓ 「初めて食べた料理」「初めて訪れた国」
🔵 「最初」と置き換えられる場合
✓ 「初めに(=最初に)確認してください」
「始め」を使う場面(動作・開始):
🟢 動作のスタート・開始
✓ 「仕事始め」「稽古始め」「営業を始める」
🟢 「開始する」「スタートする」と置き換えられる場合
✓ 「プロジェクトの始め(=開始)」
🟢 「〜を始める」という動詞と結びつく表現
✓ 「勉強を始める」「会議を始める」
🟢 行事や活動の初回
✓ 「初詣」ではなく慣用的に「仕事始め」「書き始め」
私の知人がブログを書く際、「初めまして」を「始めまして」と書いてしまい、読者から指摘を受けたことがありました。
「初めまして」は「初めてお会いします」という意味なので、時間的な「最初の出会い」を表す「初め」が正解です。
動作ではなく、状態を表している点がポイントですね。
迷ったときの簡単な見分け方
どちらを使うか迷ったときは、次の3つの方法で判断してみましょう。
シンプルな基準なので、文章を書く際にすぐ使えます。
見分け方①: 「最初」に置き換えられるか確認する
「初め」は「最初」と置き換えても意味が通る場合が多いです。
✓ 「年の初め」→「年の最初」○
✓ 「初めに説明する」→「最初に説明する」○
✗ 「仕事始め」→「仕事最初」✕(意味が通らない)
見分け方②: 「スタート・開始」に言い換えられるか試す
「始め」は「スタート」「開始」と言い換えられる場合が多いです。
✓ 「仕事始め」→「仕事開始」○
✓ 「会議の始め」→「会議の開始」○
✗ 「年の初め」→「年の開始」✕(違和感がある)
見分け方③: 動詞「〜する」がつくか確認する
「始め」は動作を表すため、「〜する」「〜を始める」と繋がります。
✓ 「仕事を始める」○ → 「仕事始め」
✓ 「勉強を始める」○ → 「勉強の始め」
✗ 「年を初める」✕ → 「年の初め」
| 見分け方 | 初め | 始め |
|---|---|---|
| 「最初」に置き換え | ○ 意味が通る | ✕ 違和感がある |
| 「開始・スタート」に置き換え | ✕ 違和感がある | ○ 意味が通る |
| 「〜する」が繋がる | ✕ 繋がらない | ○ 繋がる |
この3つの方法を使えば、ほとんどのケースで正しく判断できるようになります。
✓ 「最初」に置き換えられる → 「初め」
✓ 「開始・スタート」に置き換えられる → 「始め」
✓ 「〜する」が繋がる → 「始め」
「初め」を使う場面と例文
「初め」は、時間的な最初の時点や順序の1番目を表す場面で使われます。
日常会話からビジネス文書まで幅広く使われる表現なので、具体的な例文を通して正しい使い方を確認しましょう。
ここでは、よく使われるパターン別に「初め」の用例を紹介します。
時間・順序を表す場合の例文
「初め」は時間の流れや物事の順番を示すときに使います。
以下の例文で、具体的な使い方を見てみましょう。
時間的な最初を表す例文:
✓ 「年の初めに目標を立てる」
✓ 「月の初めに予算を確認する」
✓ 「初めのころは慣れなかった」
✓ 「初めは難しく感じたが、次第に理解できた」
✓ 「授業の初めに出席を取る」
✓ 「週の初めに予定を整理する」
順序の1番目を表す例文:
✓ 「初めに結論を述べます」
✓ 「名簿の初めに社長の名前が記載されている」
✓ 「初めにご挨拶申し上げます」
✓ 「文章の初めに要点をまとめる」
✓ 「初めから順番に説明していきます」
経験の最初を表す例文:
✓ 「初めて訪れた場所で感動した」
✓ 「初めて会った日のことを覚えている」
✓ 「初めて経験する仕事で緊張した」
✓ 「初めて食べた料理が忘れられない」
これらの例文はすべて、「時間」「順序」「初めての体験」という状態を表しているため、「初め」を使います。
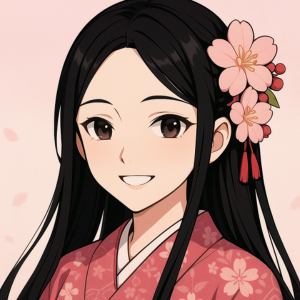
まあ私、モテすぎて『初めて』が何回あったか覚えてませんけど...
ふふっ、全部『初め』で正解よね?
『時間と順序』ですもの!
「初めて」「初めは」など定型表現
「初め」を使った定型表現は数多く存在します。
これらはセットで覚えておくと、使い分けに迷わなくなります。
「初めて」の表現:
この表現は「今までに一度も経験したことがない」という意味で、必ず「初め」を使います。
✓ 「初めてお会いします」
✓ 「初めて知った事実に驚いた」
✓ 「初めて挑戦する分野」
✓ 「初めて参加したイベント」
✓ 「彼女に初めて会った場所」
「初めは」の表現:
「最初のうちは」という意味で、時間的な最初の段階を表します。
✓ 「初めは不安だったが、今は慣れた」
✓ 「初めは少人数だったチームが大きくなった」
✓ 「初めは理解できなかった内容も、今では分かる」
✓ 「この仕事も初めは大変でした」
「初めから」の表現:
「最初から」という意味で、物事のスタート地点を表します。
✓ 「初めから計画していた」
✓ 「初めからやり直す」
✓ 「初めから最後まで読む」
✓ 「初めから丁寧に説明する」
「〜の初め」の表現:
時間や期間の最初の部分を表します。
✓ 「年の初め」
✓ 「月の初め」
✓ 「週の初め」
✓ 「学期の初め」
✓ 「世紀の初め」
友人が就職活動の面接で「御社を志望した理由は、初めて説明会に参加したときに…」と話したそうです。
この「初めて」は「最初の経験」を表しているので、「初め」が正しい使い方ですね。
こうした定型表現を覚えておくと、実際の場面でスムーズに使えます。
「始め」を使う場面と例文
「始め」は、動作や行為の開始・スタートを表す場面で使われます。
「〜を始める」という動詞と結びつく表現が多く、何かをスタートさせる意味を持ちます。
ここでは、「始め」を使った具体的な例文と、日本の伝統的な慣用表現を紹介します。
動作の開始を表す場合の例文
「始め」は、何かを開始する・スタートするという動作を表すときに使います。
以下の例文で、具体的な使い方を確認しましょう。
動作の開始を表す例文:
🟢 「会議を始めます」
🟢 「プロジェクトを始める前に準備が必要だ」
🟢 「新しい事業を始めた」
🟢 「勉強を始めてから3ヶ月が経った」
🟢 「授業を始める時間になりました」
🟢 「ダイエットを始めようと決心した」
🟢 「営業活動を始めてから売上が伸びた」
物事のスタート地点を表す例文:
🟢 「プロジェクトの始めに目標を設定する」
🟢 「講演の始めに自己紹介をした」
🟢 「作業の始めに道具を準備する」
🟢 「授業の始めに前回の復習をする」
🟢 「イベントの始めに注意事項を説明する」
「〜を始める」という動詞表現:
🟢 「ピアノを始めたのは5歳のときだ」
🟢 「副業を始めることにした」
🟢 「ランニングを始めてから体調が良い」
🟢 「英会話を始めて半年になる」
🟢 「読書を始めたら集中できた」
これらの例文は、すべて「動作の開始」や「スタート」という行為を表しているため、「始め」を使います。
「〜する」「〜を始める」という動詞と繋がる点が特徴です。
私の後輩が企画書で「プロジェクトの初めに予算を確認」と書いていたのですが、これは「始め」が正解です。
プロジェクトという行為を開始する段階を指しているので、動作の開始を表す「始め」を使うべきなんですね。

わしも薩長同盟を始め、大政奉還を始め、日本の大改革を始めたぜよ!
ただ、風呂に入るのを『始める』のだけは苦手じゃったがのう...ガハハ!
「仕事始め」「稽古始め」など慣用表現
「始め」を使った慣用表現は、日本の伝統的な行事や習慣と深く結びついています。
これらは決まった形で使われるため、セットで覚えておきましょう。
年中行事での「始め」表現:
日本では、新年や特定の時期に「〜始め」という表現を使います。
これらはすべて「その活動を開始する」という動作を表しています。
🟢 仕事始め
正月休み明けに仕事を開始する日。「今日が仕事始めです」
🟢 書き始め
新年に初めて書道や筆で文字を書くこと。「書き初め」とも書きます。
🟢 稽古始め
新年に初めて稽古を行うこと。武道や芸事で使われます。
🟢 弾き始め
音楽家が新年に初めて楽器を演奏すること。
🟢 初売り
これは「初め」ではありませんが、新年の最初の販売という意味です。
その他の慣用表現:
🟢 「をはじめとする」
公用文では「始め」を使います。「東京を始めとする大都市」
🟢 「〜に始まり〜に終わる」
「春に始まり冬に終わる一年」のように、開始と終了を表します。
🟢 「始めよければ終わりよし」
物事は最初が肝心という意味のことわざです。
| 慣用表現 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 仕事始め | 新年の業務開始日 | 1月4日が仕事始めです |
| 書き始め(書き初め) | 新年最初の書道 | 書き始めで目標を書いた |
| 稽古始め | 新年最初の稽古 | 道場で稽古始めを行った |
| 〜を始めとする | 〜を代表例として | 野菜を始めとする食材 |
これらの表現は、いずれも「動作の開始」を表しているため、「始め」を使うのが正しいです。
同僚が年賀状に「今年も仕事初めから頑張ります」と書いて送ろうとしていたのですが、「仕事始め」が正解です。
仕事を「開始する日」という動作的な意味を持つため、「始め」を使います。
こうした慣用表現は、日本の文化と深く結びついているので、正しく使いたいですね。
ビジネスシーンでの正しい使い方
ビジネス文書やメールでは、「初め」と「始め」の使い分けを間違えると、相手に誤った印象を与える可能性があります。
特に取引先への挨拶文や報告書では、正確な日本語表現が求められます。
ここでは、ビジネスシーンでよく使われる場面ごとに、正しい使い分け方を解説します。
メール・報告書での使い分け
ビジネスメールや報告書では、文脈に応じて「初め」と「始め」を正しく使い分ける必要があります。
実際によく使われる表現を見てみましょう。
メールでよく使う「初め」の表現:
✓ 「初めてご連絡させていただきます」
→ 最初の連絡という意味なので「初め」
✓ 「初めにお礼を申し上げます」
→ 順序の1番目という意味なので「初め」
✓ 「月の初めにご報告いたします」
→ 時間的な最初なので「初め」
✓ 「初めてお会いしたのは昨年でした」
→ 最初の経験なので「初め」
✓ 「初めからご説明させていただきます」
→ 最初からという意味なので「初め」
メールでよく使う「始め」の表現:
✓ 「プロジェクトを始めることになりました」
→ 開始するという動作なので「始め」
✓ 「営業活動を始めて3ヶ月が経ちました」
→ 開始したという動作なので「始め」
✓ 「東京を始めとする主要都市で展開します」
→ 公用文では「始め」を使用
✓ 「会議を始めさせていただきます」
→ 開始するという動作なので「始め」
報告書での使い分け例:
| 場面 | 正しい表現 | 理由 |
|---|---|---|
| プロジェクト開始 | 「プロジェクトを始めました」 | 動作の開始 |
| 時期の報告 | 「月の初めに実施しました」 | 時間的な最初 |
| 説明の順序 | 「初めに背景を説明します」 | 順序の1番目 |
| 展開地域 | 「関東を始めとする地域」 | 公用文の慣例 |
私の上司が新人に「報告書では『初めに結論を書く』が基本だよ」と指導していました。
これは順序の1番目を表しているので「初め」が正解です。
一方、「新規事業を始めました」は動作なので「始め」になります。
この違いを意識すると、ビジネス文書の質が格段に上がります。
「新年の挨拶」はどちらが正解?
新年の挨拶文でよく迷うのが「年の初め」と「年の始め」の使い分けです。
結論から言うと、「年の初め」が正解です。
「年の初め」が正しい理由:
🔵 「年」は時間の単位を表している
「1年」という時間の流れの中で、その最初の時期を指しているため「初め」を使います。
🔵 「最初」と置き換えられる
「年の初め」→「年の最初」と言い換えても自然な日本語になります。
🔵 状態を表している
「年を始める」という動作ではなく、「1年の最初の時期」という状態を表しています。
新年の挨拶での正しい表現例:
✓ 「新年の初めにご挨拶申し上げます」
✓ 「年の初めにあたり、本年もよろしくお願いいたします」
✓ 「年の初めから良いスタートが切れました」
✓ 「年初めのご挨拶として」
間違いやすい表現の訂正:
✗ 「年の始めにご挨拶申し上げます」→ ✓ 「年の初めにご挨拶申し上げます」
✗ 「新年の始めにあたり」→ ✓ 「新年の初めにあたり」
ただし、「仕事始め」は例外です。
これは「仕事を開始する」という動作を表すため、「始め」を使います。
取引先への年賀状で「年の初めにご挨拶申し上げます」と書くのが正式な表現です。
私の同僚が「年の始め」と書いて送りそうになったのですが、これは時間的な最初を表しているので「初め」が正解だと教えました。
新年の挨拶は第一印象を左右するので、正しい表現を使いたいですね。
プレゼン資料での注意点
プレゼン資料やスライドでは、簡潔で正確な日本語が求められます。
「初め」と「始め」の使い分けを間違えると、聞き手に違和感を与えてしまいます。
プレゼン資料でよく使う表現:
「初め」を使う場面:
✓ 「初めに本日のアジェンダを説明します」
→ 順序の1番目なので「初め」
✓ 「初めにご紹介するのは〇〇です」
→ 最初に紹介するという順序なので「初め」
✓ 「プロジェクト初期の課題」
→ 時間的な最初の段階なので「初め」(初期)
✓ 「初めての取り組みとして」
→ 最初の経験なので「初め」
「始め」を使う場面:
✓ 「〇〇を始めとする主要3都市」
→ 公用文・ビジネス文書では「始め」
✓ 「開発を始めた経緯」
→ 開始したという動作なので「始め」
✓ 「サービスを始めてから1年」
→ 開始してからという動作なので「始め」
プレゼンでの使い分けチェックリスト:
| 表現 | 正しい漢字 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 「初めに結論を述べます」 | 初め | 順序の1番目 |
| 「事業を始めました」 | 始め | 動作の開始 |
| 「初めての試みです」 | 初め | 最初の経験 |
| 「〇〇を始めとする」 | 始め | 慣用表現 |
| 「月の初めに実施」 | 初め | 時間的な最初 |
プレゼン資料作成のコツ:
✓ 「初めに」で始まるスライドは、順序を示すので「初め」
✓ 「〜を開始した」という内容は「始め」
✓ 時系列で「最初の段階」を示すときは「初め」
✓ 迷ったら「最初」「開始」に置き換えて確認
先日、部下が作ったプレゼン資料で「初めにプロジェクト概要をご説明します」というスライドがありました。
これは正しい使い方です。
一方、「新サービスを始めました」というスライドでは「始め」が正解です。
プレゼンは多くの人の目に触れるので、正確な表現を心がけることが信頼につながります。
✓ 「年の初め」が正解(時間的な最初)
✓ 「仕事始め」が正解(動作の開始)
✓ 「〜を始めとする」が公用文の基本
よくある疑問と使い分けの迷いポイント
「初め」と「始め」の使い分けでは、特定の表現で迷う人が多くいます。
「はじめまして」「をはじめとする」「まず初めに」など、日常やビジネスでよく使う表現こそ、正しい使い方を知っておきたいものです。
ここでは、多くの人が迷いやすい表現について、それぞれ詳しく解説します。
「はじめまして」はどっち?
「はじめまして」という挨拶は、「初めまして」が正解です。
この表現は「初めてお会いします」という意味の省略形なので、「初め」を使います。
「初めまして」が正しい理由:
🔵 「初めて会う」の省略形
「初めてお会いします」→「初めまして」という流れで生まれた挨拶です。
🔵 最初の出会いという状態を表す
「会う」という動作を開始するのではなく、「初めての出会い」という状態を表しています。
🔵 時間的な最初を示している
その人と会うのが「最初」であることを表しているため、「初め」を使います。
正しい表現例:
✓ 「初めまして、田中と申します」
✓ 「初めましてよろしくお願いします」
✓ 「初めまして。お会いできて光栄です」
間違った表現:
✗ 「始めまして」→ これは誤り
✗ 「初めまして。今日から仕事を始めます」→ この場合、前半は「初めまして」、後半は「始めます」が正解
ひらがなで「はじめまして」と書く場合もありますが、漢字を使う場合は必ず「初めまして」です。
私の友人が名刺交換の際に「始めまして」と書かれた名刺を受け取ったことがあるそうです。
相手はきっと「これから仕事を始める」という意味で「始め」を使ったのかもしれませんが、挨拶としては「初めまして」が正しいです。
第一印象を左右する挨拶なので、正確に覚えておきたいですね。
| 表現 | 正しい漢字 | 理由 |
|---|---|---|
| はじめまして | 初めまして | 初めて会うという意味 |
| はじめてお会いします | 初めてお会いします | 最初の出会い |
| はじめましてよろしく | 初めましてよろしく | 初対面の挨拶 |
「をはじめとする」の正しい表記
「をはじめとする」という表現は、「を始めとする」が正解です。
公用文や論文、ビジネス文書では「始め」を使うのが一般的です。
「を始めとする」が正しい理由:
🟢 文化庁の指針に従っている
公用文作成の要領では「始め」を使うことが推奨されています。
🟢 列挙の起点を表す
「〜から始まって、他にも含む」という意味合いで、動作的なニュアンスがあります。
🟢 慣用表現として定着
ビジネス文書や公的文書では「始め」を使うのが慣例です。
正しい表現例:
✓ 「東京を始めとする大都市」
✓ 「野菜を始めとする食材」
✓ 「英語を始めとする外国語」
✓ 「社長を始めとする役員一同」
✓ 「健康を始めとする様々な効果」
注意が必要な場面:
一般的な文章では「始め」を使いますが、「順序の最初」を強調したい場合は「初め」を使うこともあります。
✓ 「リストの初めに社長の名前を記載する」
→ 順序の1番目を強調する場合は「初め」
✓ 「社長を始めとする役員」
→ 列挙の起点を表す場合は「始め」
| 表現 | 推奨される漢字 | 使用場面 |
|---|---|---|
| 〜を始めとする | 始め | ビジネス文書・公用文 |
| 〜を初めとする | 初め | 順序を強調する場合 |
| 〜をはじめ | ひらがな | カジュアルな文章 |
会社の報告書で後輩が「東京を初めとする都市」と書いていたので、「ビジネス文書では『始め』を使うのが一般的だよ」とアドバイスしました。
公的な文書では特に、この使い分けが重要視されます。
「まず初めに」vs「まず始めに」
「まず初めに」と「まず始めに」のどちらが正しいかというと、「まず初めに」が一般的です。
ただし、文脈によっては「まず始めに」も使えます。
「まず初めに」を使う場合(推奨):
🔵 順序の1番目を表す場合
「まず最初に」と同じ意味で、話の順番を示すときに使います。
✓ 「まず初めに、自己紹介をします」
✓ 「まず初めに、結論をお伝えします」
✓ 「まず初めに、本日のアジェンダを確認しましょう」
✓ 「まず初めに、前回のおさらいをします」
これらは「順序として最初に」という意味なので、「初め」が適切です。
「まず始めに」を使う場合(限定的):
🟢 動作の開始を強調する場合
何かを開始することを強調したいときは「始め」を使うこともあります。
✓ 「まず始めに、エンジンをかけてください」
→ 動作の開始手順を説明している
✓ 「まず始めに、アプリを起動します」
→ 操作の開始を指示している
ただし、このような場合でも「まず初めに」を使っても問題ありません。
迷ったら「まず初めに」を使うのが無難です。
使い分けの判断基準:
| 文脈 | 推奨される表記 | 理由 |
|---|---|---|
| プレゼンや説明の順序 | まず初めに | 順序の1番目 |
| 話の切り出し | まず初めに | 最初に述べる内容 |
| 動作の開始手順 | まず始めに(初めにでも可) | 動作の開始 |
| 一般的な使用 | まず初めに | 迷ったらこちら |
「まず」と「初めに」の重複について:
「まず」も「初めに」も「最初に」という意味なので、厳密には意味が重複しています。
しかし、日本語として定着した表現なので、ビジネスシーンでも広く使われています。
「年の初め」vs「年の始め」
「年の初め」と「年の始め」では、「年の初め」が正解です。
これは前述の「新年の挨拶」でも解説しましたが、ここでさらに詳しく見ていきます。
「年の初め」が正しい理由:
🔵 時間的な最初の時期を表す
「1年」という時間の流れの中で、その最初の部分を指しています。
🔵 「最初」と置き換えられる
「年の初め」→「年の最初」と言い換えても自然です。
🔵 状態を表している
「年を始める」という動作ではなく、「年の最初の時期」という状態を示しています。
正しい表現例:
✓ 「年の初めに目標を立てる」
✓ 「年の初めにご挨拶申し上げます」
✓ 「年の初めから忙しい」
✓ 「年初め(ねんはじめ)のご挨拶」
類似表現との比較:
| 表現 | 正しい漢字 | 理由 |
|---|---|---|
| 年の初め | 初め | 時間的な最初 |
| 月の初め | 初め | 時間的な最初 |
| 週の初め | 初め | 時間的な最初 |
| 仕事始め | 始め | 仕事を開始する日 |
| 書き始め | 始め | 書くことを開始する |
「年の初め」は時間を表し、「仕事始め」は動作を表すという違いがあります。
間違いやすい理由:
「年が始まる」「新年を迎える」という表現があるため、「年の始め」と書いてしまう人が多いです。
しかし、「年の初め」という表現は「1年の最初の時期」を指しているので、「初め」が正解です。
同じ「はじめ」でも:
- 「年の初め」→ 時間の最初(初め)
- 「年が始まる」→ 動作の開始(始まる)
と使い分ける必要があります。
取引先への年始の挨拶状で、私の同僚が「年の始めにあたり」と書こうとしていたので、「これは『初め』だよ」と教えました。
年賀状や挨拶メールは相手の目に触れるものなので、正しい表記を使いたいですね。
「初め」と「始め」に関するQ&A
ここでは、「初め」と「始め」に関してよく寄せられる質問に答えていきます。
漢字の成り立ちや英語表現、覚え方のコツまで、理解を深める情報をまとめました。
これらの知識があれば、より自信を持って使い分けができるようになります。
公用文や論文ではどちらを使う?
Q: 公用文や論文を書くときは、「初め」と「始め」のどちらを使えば良いですか?
A: 文脈によって使い分けが必要ですが、基本的なルールがあります。
公用文での使い方:
文化庁の「公用文作成の要領」では、次のように定められています。
🔵 「初め」を使う場合:
- 「初めに」「初めて」など、時間や順序を表すとき
- 例:「初めに結論を述べる」「初めて実施する」
🟢 「始め」を使う場合:
- 「〜を始めとする」という慣用表現
- 例:「東京を始めとする大都市」
🔵 ひらがなで「はじめ」と書く場合:
- 接続詞的に使うとき
- 例:「はじめ、反対意見が多かった」
論文での使い方:
学術論文では、次の使い分けが一般的です。
✓ 「初めに」→ 論文の冒頭、序論を示すとき(順序の1番目)
✓ 「実験を始めた」→ 動作の開始を表すとき
✓ 「初期の段階」→ 時間的な最初を表すとき
公用文・論文での使用例:
| 場面 | 正しい表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 論文の序論 | 「初めに背景を述べる」 | 順序の1番目 |
| 列挙の表現 | 「化学を始めとする分野」 | 慣用表現 |
| 研究開始 | 「調査を始めた」 | 動作の開始 |
| 接続詞的 | 「はじめ困難だった」 | ひらがなが推奨 |
公的文書や学術論文では、このルールに従うことで、統一された読みやすい文章になります。
迷ったときは、文化庁のガイドラインや執筆要項を確認するのが確実です。
「初」と「始」の漢字の成り立ちは?
Q: 「初」と「始」の漢字は、どのような成り立ちがあるのですか?
A: それぞれの漢字には異なる由来があり、その成り立ちが現在の意味につながっています。
「初」の漢字の成り立ち:
🔵 構成要素:「衣」+「刀」
布を刀で裁つ様子を表しています。
🔵 本来の意味:
布を裁つときの「最初の一刀」から、「はじめ」「最初」という意味が生まれました。
🔵 意味の広がり:
最初の時点、始まりの時期、初めての経験といった、時間的・順序的な「最初」を表すようになりました。
🔵 「初」を使った熟語:
初回、初日、初期、初心、初対面、初恋、初雪など
「始」の漢字の成り立ち:
🟢 構成要素:「女」+「台」
女性が子どもを産む様子、または物事が生じる様子を表しています。
🟢 本来の意味:
物事が生まれる、発生する、始まるという動作を表しています。
🟢 意味の広がり:
何かを開始する、スタートする、始動するといった、動作的な「始まり」を表すようになりました。
🟢 「始」を使った熟語:
開始、始動、始発、終始、原始、創始など
漢字の成り立ちから見る使い分け:
| 漢字 | 成り立ち | 意味の特徴 | 現代の用法 |
|---|---|---|---|
| 初 | 布を裁つ最初の一刀 | 時間的・静的な最初 | 状態・時期・順序 |
| 始 | 物事が生じる様子 | 動作的・動的な開始 | 動作・行為・スタート |
漢字の成り立ちを知ると、「初」は静的なイメージ、「始」は動的なイメージということが分かります。
この違いが、現代の使い分けにもつながっているんですね。
英語ではどう表現する?
Q: 「初め」と「始め」を英語で表現するとどうなりますか?
A: 英語でも意味によって異なる単語を使い分けます。
「初め」の英語表現:
🔵 first(最初の、1番目の)
時間的な最初や順序の1番目を表します。
- 「年の初め」→ the first of the year / the beginning of the year
- 「初めに」→ first / at first / firstly
- 「月の初め」→ the beginning of the month / early in the month
🔵 beginning(始まり、最初の部分)
時間の流れの中の最初の部分を表します。
- 「初めのころ」→ at the beginning / in the beginning
- 「文章の初め」→ the beginning of the sentence
🔵 for the first time(初めて)
最初の経験を表します。
- 「初めて会った」→ met for the first time
- 「初めて訪れた」→ visited for the first time
「始め」の英語表現:
🟢 start(始める、開始する)
動作の開始を表します。
- 「仕事を始める」→ start working / begin work
- 「プロジェクトを始める」→ start a project
🟢 begin(始まる、開始する)
物事の開始を表します。
- 「会議を始める」→ begin the meeting
- 「勉強を始める」→ begin studying
🟢 commence(開始する)
フォーマルな場面での開始を表します。
- 「営業を始める」→ commence operations
🟢 including(〜を含む)
「〜を始めとする」の表現に使います。
- 「東京を始めとする都市」→ cities including Tokyo / Tokyo and other cities
英語での使い分け例:
| 日本語 | 英語表現 | 単語 |
|---|---|---|
| 初めに説明します | First, I'll explain | first |
| 初めて会った | met for the first time | first time |
| 年の初め | the beginning of the year | beginning |
| 仕事を始める | start working | start |
| 会議を始める | begin the meeting | begin |
| 〜を始めとする | including ~ | including |
英語でも日本語と同じように、「最初」を表す単語と「開始」を表す単語が区別されています。
この共通点を理解すると、日本語の使い分けもより明確になります。
言い換え表現・類語は?
Q: 「初め」と「始め」の言い換え表現や類語にはどんなものがありますか?
A: それぞれに適した言い換え表現があります。文章の雰囲気や状況に応じて使い分けましょう。
「初め」の言い換え表現・類語:
🔵 時間的な最初を表す類語:
- 最初(さいしょ)→ 「最初に確認する」
- 当初(とうしょ)→ 「当初の予定では」
- 序盤(じょばん)→ 「序盤の段階」
- 初期(しょき)→ 「初期の段階」
- 冒頭(ぼうとう)→ 「冒頭でお伝えした通り」
- 出だし(でだし)→ 「出だしは順調だった」
🔵 順序の1番目を表す類語:
- 第一(だいいち)→ 「第一に考えるべきこと」
- 一番目(いちばんめ)→ 「一番目の項目」
- トップ → 「リストのトップ」
- まず → 「まず確認してください」
🔵 初めての経験を表す類語:
- 初回(しょかい)→ 「初回の訪問」
- 処女(しょじょ)→ 「処女作」「処女航海」
- デビュー → 「デビュー作」
- 未経験(みけいけん)→ 「未経験の分野」
「始め」の言い換え表現・類語:
🟢 動作の開始を表す類語:
- 開始(かいし)→ 「営業を開始する」
- スタート → 「プロジェクトをスタートする」
- 着手(ちゃくしゅ)→ 「作業に着手する」
- 始動(しどう)→ 「エンジンを始動する」
- 発足(ほっそく)→ 「委員会を発足する」
- 創設(そうせつ)→ 「会社を創設する」
🟢 物事のスタートを表す類語:
- 出発点(しゅっぱつてん)→ 「プロジェクトの出発点」
- 起点(きてん)→ 「計画の起点」
- 発端(ほったん)→ 「事件の発端」
- きっかけ → 「始めるきっかけ」
文脈別の使い分け例:
| 文脈 | 「初め」系 | 「始め」系 |
|---|---|---|
| フォーマル | 当初、冒頭、初期 | 開始、着手、発足 |
| カジュアル | 最初、出だし | スタート、きっかけ |
| ビジネス | 第一、初回 | 開始、始動 |
| 文章表現 | 冒頭、序盤 | 着手、創設 |
これらの類語を適切に使うことで、文章に変化をつけたり、より正確なニュアンスを伝えたりすることができます。
同じ言葉の繰り返しを避けたいときにも便利です。
子どもにも分かる覚え方はある?
Q: 子どもでも分かりやすい、「初め」と「始め」の覚え方はありますか?
A: シンプルな覚え方があります。イメージと言葉で関連付けると覚えやすいです。
覚え方①: 「最初」「開始」で覚える
これが最もシンプルで確実な方法です。
🔵 「初め」→「最初」に置き換えられる
「年の初め」→「年の最初」○
意味が通れば「初め」を使います。
🟢 「始め」→「開始」に置き換えられる
「仕事始め」→「仕事開始」○
意味が通れば「始め」を使います。
覚え方②: 「うい」「はじ」で覚える
漢字の読み方に注目します。
🔵 「初」→「うい」と読める
「初々しい(ういういしい)」「初陣(ういじん)」
→ 時間的な最初、フレッシュなイメージ
🟢 「始」→「はじ」とだけ読む
「始まる(はじまる)」「始める(はじめる)」
→ 動作のスタート、動きのあるイメージ
覚え方③: 具体例で覚える
よく使う表現をセットで覚えます。
🔵 「初め」を使う表現:
- 「初めまして」(あいさつ)
- 「初めて」(はじめての経験)
- 「年の初め」(お正月)
- 「初めに」(最初に)
🟢 「始め」を使う表現:
- 「仕事始め」(お正月明け)
- 「始める」(スタートする)
- 「〜を始めとする」(〜を含む)
- 「会議を始めます」(開始する)
子どもに教えるときのポイント:
| 方法 | 説明の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 最初か開始か | 「最初」なら「初め」、「開始」なら「始め」 | シンプルで分かりやすい |
| 動くか動かないか | 「止まってる」→「初め」、「動いてる」→「始め」 | イメージで理解 |
| 具体例で覚える | 「初めまして」「仕事始め」をセットで | 実用的 |
子どもへの説明例:
『初め』は『最初』の『初』だから、『一番最初』とか『初めて』のときに使うよ。
『始め』は『始まる』『始める』の『始』だから、『何かをスタートする』ときに使うんだ。
『初めまして』は『初めて会う』だから『初め』、『仕事始め』は『仕事をスタートする日』だから『始め』だよ。
このように、身近な例を使って教えると、子どもでも理解しやすくなります。
まとめ
「初め」と「始め」は、どちらも「はじめ」と読みますが、意味が異なります。
「初め」は時間的な最初や順序の1番目を表し、「年の初め」「初めて」「初めに」のように使います。
一方「始め」は動作や行為の開始を表し、「仕事始め」「会議を始める」「〜を始めとする」のように使います。
迷ったときは、「最初」に置き換えられれば「初め」、「開始・スタート」に置き換えられれば「始め」と覚えておきましょう。
ビジネス文書では特に、この使い分けが重要です。
正しい表記を使うことで、相手に信頼感を与え、より正確なコミュニケーションができるようになります。




















