
「異議」「異義」「意義」「威儀」は、どれも「いぎ」と読む同音異義語で、使い分けに迷う方が多い言葉です。
特に「異議を唱える」と「意義を唱える」のどちらが正しいのか、「存在の意義」はどの漢字を使うのか、混乱してしまうことはありませんか?

天下を取るより、この「いぎ」の使い分けの方が難しいわい!

わしも「存在の異議」って書いて、薩長同盟の書状で恥かいたぜよ。
この記事で一緒に学び直そうぜ!
この記事では、4つの「いぎ」の意味の違いを比較表で分かりやすく整理し、具体的な例文とともに正しい使い分け方を解説します。
ビジネスシーンや日常会話で自信を持って使えるよう、間違えやすいポイントもしっかりカバーしています。
楽しく読んで頂ける内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
「異議」「異義」「意義」「威儀」の違いを一覧で比較
「異議」「異義」「意義」「威儀」は、どれも「いぎ」と読む同音異義語です。
読み方は同じでも、それぞれ全く異なる意味を持っています。
まずは4つの言葉の違いを一覧表で確認し、基本的な意味を押さえましょう。
| 言葉 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|
| 異議 | 反対の意見や異なる考え | 「その提案に異議があります」「異議なし!」 |
| 異義 | 異なる意味・別の解釈 | 「この言葉には異義がある」「同音異義語」 |
| 意義 | 意味や価値・重要性 | 「存在の意義」「意義深い経験」 |
| 威儀 | 威厳のある態度や作法 | 「威儀を正す」「威儀を保つ」 |
4つの言葉の中で、日常生活やビジネスシーンで最もよく使われるのは「異議」と「意義」です。
「異義」は主に言語学や文章表現の分野で使われ、「威儀」は格式ある場面や宗教的な文脈で用いられることが多い言葉です。
それぞれの言葉を正しく使い分けるには、漢字の意味に注目するのがポイントです。
「異」は「異なる」、「意」は「心の考え」、「威」は「威厳」を表しています。
【ここがポイント!】
✓ 異議 = 反対の意見や異なる考え(会議や議論で使う)
✓ 異義 = 異なる意味・別の解釈(言語学の専門用語)
✓ 意義 = 意味や価値・重要性(最も日常的に使う)
✓ 威儀 = 威厳のある態度や作法(格式ある場面で使う)
「異議」の意味と使い方
「異議」は、ビジネスや会議などで頻繁に使われる言葉です。
相手の意見や提案に対して反対の立場を示すときに用います。
「異なる意見」を表す重要な言葉として、正しい使い方を理解しておきましょう。
「異議」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「異議」の意味
「異議」とは、他人の意見や提案に対して反対する意見や異なる考えを指します。
「異」は「異なる」、「議」は「議論・意見」を意味し、文字通り「異なる議論」という意味になります。
会議や法廷、日常会話など幅広い場面で使われる言葉です。
特にビジネスシーンでは「異議を申し立てる」「異議を唱える」といった形で、自分の反対意見を相手に伝える際に用いられます。
また「異議なし」という表現は、会議の場で「反対意見はありません」「賛成です」という意味を表す定型句として広く使われています。
この言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「異議」は単に反対するだけでなく、建設的な議論を進めるための重要な概念です。
異なる視点や意見を持つことで、より良い結論に導くための議論が深まります。

軍議で誰も反対せん時ほど怖いもんはないぞ。「異議なし」ばっかりの会議は、実は一番危険なんじゃよ。
ガハハ!
「異議」を使った例文
具体的な使用例を見ていきましょう。
- 会議で提案された新しい方針に異議を唱えた
- 裁判で弁護士が検察側の主張に異議を申し立てた
- 「この決定に異議はありますか?」「異議なし!」
- 彼の発言内容に異議を感じたので質問した
- その計画には多くのメンバーから異議が出た
- 株主総会で一部の株主が経営方針に異議を表明した
友人の田中さんがこんな経験を話してくれました。
会社の会議で新しいプロジェクトの進め方が提案されたとき、納期が厳しすぎると感じた田中さんは勇気を出して「この日程には異議があります」と発言したそうです。
最初は緊張したものの、その後の議論で現実的なスケジュールに修正され、プロジェクトは無事成功したとのことでした。
「異議」を使う場面
「異議」は主に以下のような場面で使用されます。
🔹 ビジネス・会議
会社の会議や株主総会で、提案や決定事項に対して反対意見を述べる場面で使います。
「この予算案に異議があります」のように、フォーマルな表現として適しています。
🔹 法律・裁判
法廷での異議申し立ては非常に一般的です。
弁護士が相手方の主張や証拠に対して「異議あり!」と発言するシーンは、ドラマや映画でもよく見かけますね。
🔹 議会・公式な場
国会や地方議会、各種委員会などの公式な議論の場でも頻繁に使われます。
民主的な議論を進める上で欠かせない表現です。
🔹 日常会話
友人や家族との会話でも使えます。
ただし、やや堅い表現なので、カジュアルな場面では「反対」「それはちょっと違うと思う」などの方が自然な場合もあります。
「異義」の意味と使い方
「異義」は、日常生活ではあまり使われない言葉ですが、言語学や文章表現の分野では重要な概念です。
一つの言葉が複数の意味を持つ場合に使用される専門的な用語として理解しておきましょう。
「異義」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「異義」の意味
「異義」とは、一つの言葉が持つ異なる意味や、別の解釈のことを指します。
「異」は「異なる」、「義」は「意味・解釈」を表し、「異なる意味」という意味になります。
最も身近な例は「同音異義語」です。
これは「発音は同じだけれど意味が異なる言葉」を指します。
まさに今回のテーマである「異議」「異義」「意義」「威儀」も同音異義語の関係にあります。
また、一つの単語が文脈によって複数の意味を持つ場合にも「異義」という言葉が使われます。
例えば「かける」という動詞は「電話をかける」「時間をかける」「眼鏡をかける」など、さまざまな意味を持ちますが、これらは異義の関係にあると言えます。
「異義」は主に言語研究や辞書編纂、国語教育などの専門的な場面で使用される学術用語です。
一般のビジネス会話や日常会話で使う機会はほとんどありません。
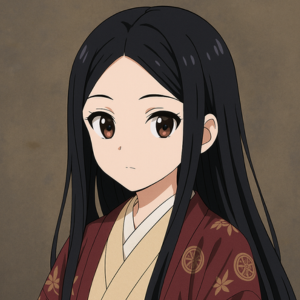
「月にかける想い」「橋をかける」「声をかける」…
同じ音なのに違う意味、これぞ日本語の奥ゆかしさですわね。
現代の皆さんも「異義」を知れば、言葉遊びがもっと楽しくなりますわよ。ふふふ♪
「異義」を使った例文
具体的な使用例を見ていきましょう。
- 「かみ」には「紙」「髪」「神」などの同音異義語がある
- この単語には複数の異義が存在する
- 国語辞典では異義ごとに番号を付けて説明している
- 文脈によって異義を判断する必要がある
- 「いぎ」の同音異義語を調べる
- 言語学では異義の研究が重要なテーマの一つだ
知り合いの高校教師から聞いた話ですが、国語の授業で同音異義語を教える際、生徒たちが「異義」と「異議」を混同してしまうことがよくあるそうです。
「同音異義語って、反対意見のこと?」と質問されたこともあったとか。
その先生は「『異なる意味』が異義、『異なる意見』が異議だよ」と覚え方を教えているそうです。
「異義」を使う場面
「異義」は主に以下のような場面で使用されます。
🔹 言語学・国語教育
大学の言語学講義や国語の授業で、言葉の意味の多様性を説明する際に使います。
「この言葉には3つの異義があります」のように学術的な文脈で登場します。
🔹 辞書・参考書
国語辞典や専門用語辞典では、一つの見出し語に複数の意味がある場合、それぞれを「異義」として区別して記載しています。
🔹 翻訳・言語研究
外国語を翻訳する際、一つの単語が複数の意味を持つ場合に「異義」という概念が重要になります。
文脈から正しい意味を判断する必要があるためです。
🔹 文章作成・執筆
文章を書く際に、読者が誤解しないよう「異義」を意識して言葉を選ぶことがあります。
ただし「異義」という言葉自体を使うことは稀です。
「意義」の意味と使い方
「意義」は、日常生活からビジネスシーンまで幅広く使われる言葉です。
物事の価値や重要性を表す際に用いられ、「異議」と並んで最もよく使用される「いぎ」の一つです。
正しい使い方を身につけましょう。
「意義」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「意義」の意味
「意義」とは、言葉や行動が持つ意味や価値、重要性のことを指します。
「意」は「心の考え・思い」、「義」は「意味・道理」を表し、「物事が持つ本質的な意味や価値」を表現する言葉です。
「意義」は単なる意味だけでなく、その物事がどれだけ重要か、どんな価値があるかという評価的なニュアンスも含みます。
「存在の意義」「人生の意義」のように、哲学的な文脈でも頻繁に使われる深い言葉です。
また「意義深い」という形容詞は、非常に価値がある、重要な意味を持つという意味で使われます。
特別な経験や出来事に対して「意義深い一日だった」のように表現します。
ビジネスシーンでは「このプロジェクトの意義は何か」「社会的意義がある取り組み」といった形で、事業や活動の目的や価値を説明する際によく使われる重要な言葉です。

「この行動に意義はあるか?」って自分に問いかけることが、人生で一番大事ながじゃ。
まあ、当時は「存在の異議」って書いて笑われたけんど…(笑)
「意義」を使った例文
具体的な使用例を見ていきましょう。
- この仕事には大きな社会的意義がある
- 人生の意義について深く考える
- 今回のボランティア活動は意義深い経験だった
- 存在意義を見失ってしまった
- 教育の意義を改めて実感した
- このプロジェクトの意義を全員で共有しよう
- 彼の研究には意義がある
同僚の佐藤さんが話してくれたエピソードがあります。
転職を考えていた時期に「今の仕事に意義を感じられない」と悩んでいたそうです。
しかし、自社の製品を使ったお客様から感謝の手紙が届いたことで「この仕事には確かに意義がある」と気づき、やりがいを取り戻したとのこと。
「意義」という言葉が、人の働く動機に深く関わっていることを実感させられる話でした。
「意義」を使う場面
「意義」は主に以下のような場面で使用されます。
🔹 ビジネス・仕事
プロジェクトの目的や価値を説明する際に「このプロジェクトの意義は〇〇です」のように使います。
社員のモチベーション向上や方向性の共有にも役立つ表現です。
🔹 教育・学術
研究の価値や学習の重要性を説明する場面で頻繁に使われます。
「この研究の意義は」「教育の意義を考える」といった形で登場します。
🔹 哲学・自己啓発
人生の目的や存在価値について語る際に使います。
「生きる意義」「存在意義」など、深い思索を伴う文脈で用いられる言葉です。
🔹 社会活動・ボランティア
社会貢献活動の価値を表現する際に「社会的意義がある」「意義深い活動」のように使います。
活動の重要性を強調したいときに効果的です。
🔹 日常会話
「今日は意義深い一日だった」「この経験には意義があった」など、日常的な出来事に対しても気軽に使える言葉です。
「威儀」の意味と使い方
「威儀」は、4つの「いぎ」の中で最も使用頻度が低い言葉です。
格式ある場面や宗教的な文脈で使われることが多く、日常会話ではほとんど耳にしません。
しかし、正式な場での振る舞いを表現する重要な言葉として知っておくと便利です。
「威儀」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
「威儀」の意味
「威儀」とは、威厳のある立ち居振る舞いや、礼儀正しく厳かな態度のことを指します。
「威」は「威厳・威力」、「儀」は「礼儀・作法」を意味し、「威厳を保った正しい作法」という意味になります。
特に仏教や神道などの宗教儀式において、僧侶や神職が保つべき厳かな態度を指す言葉として使われてきました。
また、武士道や茶道などの伝統文化においても、正しい姿勢や所作を表現する際に用いられます。
現代では、格式の高い式典や公式行事における立ち居振る舞いを表す際にも使われます。
ただし、一般的なビジネスシーンや日常会話で使われることは稀で、やや古風で文語的な印象を与える言葉です。
「威儀を正す」という表現は、姿勢や態度を正して礼儀正しく振る舞うという意味で、今でも時々使われます。
改まった場面で背筋を伸ばし、きちんとした態度を取ることを指します。
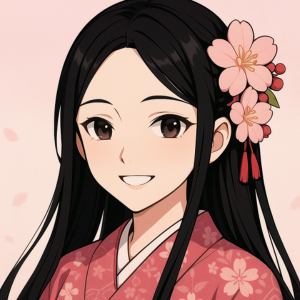
平安の宮中では、十二単を着て一歩歩くだけで威儀が問われたものですわ。
背筋をピンと伸ばして、優雅に…って、現代の皆さんはスマホ見ながら猫背になってません?
せめて大事な場面では「威儀」を思い出してくださいな。
美しい姿勢は永遠の美の秘訣ですのよ♪
「威儀」を使った例文
具体的な使用例を見ていきましょう。
- 式典では威儀を正して参列した
- 僧侶の威儀ある振る舞いに感銘を受けた
- 武道では威儀を重んじる
- 彼は常に威儀を保った態度で接する
- 茶道の師範は威儀正しい所作を見せた
- 天皇陛下の威儀に満ちたお姿
祖父の葬儀に参列した際の出来事を親戚が話してくれました。
読経をする僧侶の姿勢や所作があまりにも美しく、一つ一つの動作に無駄がなかったそうです。
後で住職に「あの立ち居振る舞いは何と呼ぶのですか」と尋ねたところ、「威儀と言います。僧侶として長年修行して身につけるものです」と教えてもらったとのこと。
それ以来「威儀」という言葉の重みを感じるようになったそうです。
「威儀」を使う場面
「威儀」は主に以下のような場面で使用されます。
🔹 宗教・儀式
仏教の法要や神道の神事など、宗教的な儀式における厳かな態度や作法を表現する際に使います。
「僧侶の威儀」「神職の威儀」のように用いられます。
🔹 伝統文化・武道
茶道、華道、武道などの伝統的な文化や芸道において、正しい姿勢や礼儀作法を指す言葉として使われます。
「威儀を正す」は稽古の基本です。
🔹 格式高い式典
国家的な式典や皇室関連の行事など、非常に格式の高い場面での振る舞いを表現する際に用いられます。
一般的な結婚式や卒業式では使いません。
🔹 文学・歴史書
時代小説や歴史書の中で、武士や貴族の立ち居振る舞いを描写する際に登場します。
現代文学でもあえて格調高い雰囲気を出したい場面で使われることがあります。
🔹 日常会話での使用
日常会話で使うことはほとんどありません。
使う場合も「威儀を正す」という慣用的な表現に限られることが多いです。
「異議」と「異義」の違いと使い分け
「異議」と「異義」は、どちらも「異なる」という意味を持つ「異」の字が使われているため、混同しやすい言葉です。
しかし、実際には全く異なる場面で使用される言葉なので、明確に区別して理解しましょう。
意味の違いを詳しく解説
「異議」と「異義」の最も大きな違いは、何が「異なる」のかという点です。
異議=異なる意見
「異議」は「議論・意見」が異なることを指します。
つまり、人と人との間で意見や考え方が食い違っている状況を表す言葉です。
会議や議論の場面で「私はその提案に異議があります」と言えば、相手の意見に賛成できない、反対の立場であることを示します。
「異議」は人間関係やコミュニケーションの中で使われる言葉であり、必ず「誰かの意見に対して」という相手が存在します。
一人で考えているだけでは「異議」は生まれません。
異義=異なる意味
一方「異義」は「意味・解釈」が異なることを指します。
一つの言葉が複数の意味を持っている、または同じ音でも違う意味の言葉が存在するという、言語そのものの性質を表す言葉です。
「異義」は言語学や国語学の専門用語として使われることが多く、人間の意見の対立とは関係ありません。
「この単語には2つの異義がある」と言えば、その言葉が2つの異なる意味を持っているという客観的な事実を述べているだけです。
| 比較項目 | 異議 | 異義 |
|---|---|---|
| 何が異なるか | 意見・考え | 意味・解釈 |
| 使用場面 | 会議・議論・裁判 | 言語学・辞書・教育 |
| 対象 | 人の意見 | 言葉の意味 |
| 使用頻度 | 高い(日常的) | 低い(専門的) |
使い分けのポイント
「異議」と「異義」を正しく使い分けるには、以下のポイントを押さえましょう。
✅ 「異議」を使うとき
・会議や議論で反対意見を述べる
→ 「この計画には異議があります」
・誰かの提案や決定に賛成できない
→ 「その方針に異議を唱える」
・法廷で弁護士が反論する
→ 「異議あり!」
・決定事項に反対者がいないか確認する
→ 「この件について異議はありますか?」
✅ 「異義」を使うとき
・同音異義語について説明する
→ 「『いぎ』には複数の同音異義語がある」
・一つの言葉に複数の意味がある
→ 「この単語には3つの異義がある」
・辞書で意味の違いを説明する
→ 「異義ごとに用例を示す」
・言語学や国語の授業で使う
→ 「異義の研究は重要だ」
間違えやすいポイント
❌ 「その意見に異義があります」
→ 意見に対して使うのは「異議」が正解
❌ 「同音異議語」
→ 言葉の意味に関することなので「同音異義語」が正解
迷ったときは「人の意見なら異議、言葉の意味なら異義」と覚えておくと便利です。
ビジネスや日常生活で使う機会が圧倒的に多いのは「異議」の方なので、まずは「異議」の使い方をしっかり身につけましょう。
「異義」と「意義」の違いと使い分け
「異義」と「意義」は、どちらも「いぎ」と読み、「義」という漢字を共有しているため、特に混同しやすい組み合わせです。
しかし、最初の漢字「異」と「意」の違いによって、全く異なる意味を持つ言葉になっています。
意味の違いを詳しく解説
「異義」と「意義」の違いは、言葉が指し示す対象が根本的に異なります。
異義=異なる意味
「異義」は「異なる意味」を表す言葉で、一つの言葉が複数の意味を持つこと、または発音が同じで意味が違う言葉が存在することを指します。
「異」は「異なる・違う」という意味です。
「異義」は言語の性質や特徴を説明するための専門用語であり、言葉そのものの分析に使われます。
辞書や言語学の教科書で目にする機会が多い言葉です。
意義=意味や価値
一方「意義」は「意味や価値、重要性」を表す言葉で、物事が持つ本質的な意味や、その存在価値を指します。
「意」は「心・考え・思い」を表します。
「意義」は言葉だけでなく、行動、出来事、プロジェクト、人生など、あらゆる物事の価値や重要性を評価する際に使う非常に汎用性の高い言葉です。
日常生活やビジネスシーンで頻繁に使われます。
| 比較項目 | 異義 | 意義 |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 異なる意味 | 意味・価値・重要性 |
| 対象 | 言葉・単語 | あらゆる物事 |
| 使用場面 | 言語学・国語教育 | ビジネス・日常生活全般 |
| 使用頻度 | 低い(専門的) | 高い(日常的) |
| ニュアンス | 客観的・学術的 | 評価的・価値判断を含む |
使い分けのポイント
「異義」と「意義」を正しく使い分けるには、以下のポイントを押さえましょう。
✅ 「異義」を使うとき
・同音異義語について述べる
→ 「『いぎ』の同音異義語を調べる」
・一つの言葉に複数の意味がある
→ 「この言葉には複数の異義が存在する」
・辞書で意味を区別する
→ 「異義ごとに番号を付けて説明する」
・言語学の文脈で使う
→ 「異義の分析を行う」
✅ 「意義」を使うとき
・物事の価値や重要性を述べる
→ 「このプロジェクトには大きな意義がある」
・存在の理由や目的を問う
→ 「存在意義を考える」
・経験の価値を表現する
→ 「意義深い体験だった」
・言葉や概念の意味を説明する
→ 「教育の意義とは何か」
間違えやすいポイント
❌ 「この仕事には異義がある」
→ 価値や重要性を述べるときは「意義」が正解
❌ 「同音意義語」
→ 言葉の異なる意味を指すので「同音異義語」が正解
❌ 「存在異義」
→ 存在の価値を問うのは「存在意義」が正解
覚え方のコツ
「異義」は「異なる意味」の「異」
「意義」は「意味・価値」の「意」
と覚えると間違えにくくなります。
また、日常会話やビジネスで使うのはほぼ100%「意義」の方だと覚えておけば、迷ったときも安心です。
「異義」は国語や言語学の専門的な話題以外ではほとんど登場しません。
間違えやすい表現「異議を唱える」と「意義を唱える」
「異議を唱える」と「意義を唱える」は、最も間違えやすい表現の一つです。
実は「意義を唱える」は誤用で、正しくは「異議を唱える」が正解です。
この違いをしっかり理解して、恥ずかしい間違いを防ぎましょう。
正しいのは「異議を唱える」
結論から言うと、正しい表現は「異議を唱える」です。
「唱える」は「意見や主張を声に出して述べる」という意味の動詞です。
会議や議論の場で反対意見を表明することを「異議を唱える」と表現します。
この表現は、ビジネスシーンや法廷、議会などで頻繁に使われる正式な言い回しです。
「その決定に異議を唱える」「彼女の提案に異議を唱えた」のように、反対の立場を明確に示す際に用います。
「異議を申し立てる」という似た表現もありますが、これも正しい日本語です。
「申し立てる」は「正式に意見や要求を述べる」という意味で、特に法律や行政の分野でよく使われます。
一方、「意義を唱える」という表現は存在しません。
「意義」は物事の価値や重要性を表す言葉であり、「唱える」という動詞とは組み合わせて使わないのです。
「意義を唱える」が間違いである理由
「意義を唱える」が間違いである理由は、「意義」という言葉の性質にあります。
「意義」は唱えるものではない
「意義」は物事が持つ意味や価値を指す名詞です。
価値や重要性は「唱える(声に出して主張する)」ものではなく、「見出す」「感じる」「考える」「認める」といった動詞と組み合わせて使います。
正しい表現は以下の通りです:
- 意義を見出す
- 意義を感じる
- 意義を見失う
- 意義を問う
- 意義を認める
- 意義を説明する
なぜ間違えやすいのか
「異議」と「意義」は発音が全く同じため、音だけで覚えていると間違えやすくなります。
特に会話で「いぎをとなえる」と聞いたとき、漢字を意識せずに覚えてしまうと、後で文章を書く際に誤字として現れてしまいます。
また、「意義」の方が日常的によく使う言葉なので、無意識のうちに「意義を唱える」と書いてしまう人が多いのです。
しかし、ビジネス文書や公式な場面でこの間違いをすると、恥ずかしい思いをすることになります。
| 表現 | 正誤 | 説明 |
|---|---|---|
| 異議を唱える | ✅ 正しい | 反対意見を述べること |
| 意義を唱える | ❌ 間違い | 存在しない表現 |
| 意義を見出す | ✅ 正しい | 価値を発見すること |
| 異議を見出す | ❌ 不自然 | 反対意見は「唱える」もの |
「異議を唱える」の正しい使い方
「異議を唱える」を正しく使いこなすために、具体的な使用例を確認しましょう。
ビジネスシーンでの使用例
- 会議で提案された予算案に異議を唱えた
- 部長の方針に対して異議を唱える勇気が必要だ
- 誰も異議を唱えないまま決定が下された
- 新しいルールに異議を唱える社員が続出した
- 彼は常に建設的な視点から異議を唱える
- 不当な扱いに対して堂々と異議を唱えた
法律・公式な場面での使用例
- 弁護士が判決に異議を唱えた
- 株主総会で経営陣の決定に異議を唱える株主がいた
- 市民団体が条例案に異議を唱えている
- 裁判で検察側の証拠に異議を唱えた
日常会話での使用例
- 友人の意見に異議を唱えるつもりはない
- 親の決定に異議を唱えたが聞き入れられなかった
- ルール変更に異議を唱えるメンバーが多かった
営業部の山田さんからこんな話を聞きました。
会議で新しい営業方針が提案されたとき、現場の実情に合わないと感じた山田さんは「この方針には異議があります」と発言したそうです。
最初は緊張したものの、きちんと理由を説明したところ、上司も理解を示し、方針の修正につながったとのこと。
「異議を唱える」ことは、より良い結果を生むための大切なコミュニケーションなのだと実感したそうです。
間違いを防ぐポイント
📌 「いぎをとなえる」と聞いたら「異議を唱える」
📌 反対意見を述べる = 異議を唱える
📌 価値を見出す = 意義を見出す
📌 迷ったら「反対するなら異議」と覚える
メールやレポートを書く際は、変換後に必ず漢字を確認する習慣をつけましょう。
特にスマートフォンやパソコンの予測変換で「意義を唱える」が候補に出てくることもありますが、これは間違いですので注意が必要です。
【間違えやすいポイント!】
✅ 正しい → 「異議を唱える」(反対意見を述べること)
❌ 間違い → 「意義を唱える」(この表現は存在しない)
覚え方:
・反対意見を述べる = 異議を唱える
・価値を見出す = 意義を見出す
・「いぎをとなえる」と聞いたら「異議を唱える」と覚えよう!
「異議」「異義」「意義」「威儀」に関するQ&A
ここまで4つの「いぎ」について詳しく解説してきましたが、まだ疑問に思う点があるかもしれません。
よくある質問をQ&A形式でまとめましたので、最終確認として活用してください。
「存在の意義」はどの漢字が正しい?
答え:「存在の意義」が正しい表記です。
「存在の意義」は「存在することの意味や価値」を表す表現なので、「意義(意味・価値)」を使います。
「存在の異議」や「存在の異義」は間違いです。
この表現は哲学的な文脈だけでなく、ビジネスシーンでも頻繁に使われます。
「この部署の存在意義は何か」「自社製品の存在意義を問い直す」のように、組織や物事の価値を考える際に用いられる重要な表現です。
同様に「人生の意義」「仕事の意義」「学びの意義」なども全て「意義」を使います。
何かの価値や重要性を述べる場合は、基本的に「意義」が正解だと覚えておきましょう。
「異議なし」と「意義なし」の違いは?
答え:「異議なし」が正しく、「意義なし」は全く異なる意味です。
「異議なし」は会議などで「反対意見はありません」「賛成です」という意味を表す定型表現です。
議長が「ご異議ありませんか?」と尋ね、参加者が「異議なし!」と答える場面は、映画やドラマでもよく見かけますね。
一方「意義なし」は「価値がない」「重要性がない」という意味になります。
「この仕事には意義がない」と言えば「この仕事には価値がない」という否定的な評価を表します。
会議の場面で「意義なし」と言ってしまうと、「この会議には価値がない」という全く別の意味になってしまうので要注意です。
反対意見がないことを伝えたいときは、必ず「異議なし」を使いましょう。
「意義深い」と「意味深い」の違いは?
答え:「意義深い」は価値がある、「意味深い」は深い意味が隠れているという違いがあります。
「意義深い」は「非常に価値がある」「重要な意味を持つ」という意味で、ポジティブな評価を表します。
「意義深い経験」と言えば「とても価値のある経験」という意味になります。
格式ある表現として、スピーチや文章でよく使われます。
「意味深い」は「何か深い意味が隠されている」「裏の意味がありそう」というニュアンスで使われます。
「意味深な発言」と言えば「何か含みのある発言」という意味になります。
やや口語的で、日常会話でも気軽に使える表現です。
どちらも正しい日本語ですが、使う場面とニュアンスが異なります。
フォーマルな場面で価値を強調したいなら「意義深い」、カジュアルに「何か意味がありそう」と言いたいなら「意味深い」を選びましょう。
ビジネスシーンではどう使い分ける?
答え:「異議」と「意義」を使い分けることが重要です。
「異議」を使う場面
会議で反対意見を述べるときや、提案に賛成できないときに使います。
「この計画には異議があります」「予算案に異議を唱えます」のように、自分の立場を明確に示す際に効果的です。
建設的な議論のために異議を述べることは、ビジネスでは重要なスキルです。
ただし、単に反対するだけでなく、代替案や理由もセットで伝えることが大切です。
「意義」を使う場面
プロジェクトの価値や目的を説明するときに使います。
「このプロジェクトの意義は顧客満足度の向上です」「社会的意義のある事業」のように、活動の重要性を強調する際に用いられます。
社員のモチベーション向上や、ステークホルダーへの説明資料でも「意義」という言葉は効果的です。
仕事の価値を再認識させる力のある表現です。
「異義」と「威儀」
これら2つはビジネスシーンではほとんど使いません。
「異義」は言語学の専門用語、「威儀」は格式ある式典での振る舞いを指すため、一般的な業務では登場する機会がありません。
「威儀」は日常会話で使う言葉?
答え:日常会話ではほとんど使わない、格式の高い言葉です。
「威儀」は現代の日常会話で使われることはほぼありません。
使用されるのは主に以下のような限られた場面です。
使われる場面
・宗教儀式(仏教の法要、神道の神事など)
・伝統文化の稽古(茶道、武道など)
・歴史小説や時代劇
・格式の高い式典の描写
もし日常会話で使うとしたら「威儀を正す(姿勢や態度を正す)」という慣用表現くらいでしょう。
ただし、これも少し堅苦しい印象を与えるため、カジュアルな場面では「姿勢を正す」「態度を改める」などの表現の方が自然です。
「威儀」という言葉を知識として覚えておくことは大切ですが、実際に使う機会は少ないと考えて良いでしょう。
代わりに「異議」と「意義」の使い分けをしっかりマスターすることをおすすめします。
まとめ
「異議」「異義」「意義」「威儀」は、どれも「いぎ」と読む同音異義語ですが、それぞれ全く異なる意味を持っています。
日常生活やビジネスシーンで最もよく使われるのは「異議(反対意見)」と「意義(価値・重要性)」の2つです。
特に「異議を唱える」が正しく、「意義を唱える」は誤用なので注意しましょう。
「異義」は言語学の専門用語、「威儀」は格式ある場面での振る舞いを指す言葉で、使用頻度は低めです。
迷ったときは「反対意見なら異議、価値や重要性なら意義」と覚えておくと間違いありません。
正しい使い分けをマスターして、自信を持って使いこなしましょう。



















