
「過程」と「課程」、どちらも「かてい」と読むこの2つの言葉は、使い分けに迷うことが多いのではないでしょうか。
「教育課程」なのか「教育過程」なのか、「博士課程」なのか「博士過程」なのか、正しいのはどちらか分からず不安になることもあるでしょう。
実はこの2つ、意味も使い方も全く異なります。「過程」は物事が進んでいくプロセスを、「課程」は学校などで定められた学習プログラムを指します。

龍馬よ、お主は学問好きじゃから「課程」の方が詳しいじゃろ?

秀吉さん、その通りぜよ!
わしが作りたかった教育の仕組みは「教育課程」。
でも、そこに至る道のりは「過程」じゃ。
使い分けが大事ながじゃき!
本記事では、「過程」と「課程」の意味の違いから、具体的な使い分け方、間違えやすいポイント、よくある質問まで、豊富な例文とともに徹底解説します。
比較表やポイントボックスを使って分かりやすく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。
「過程」と「課程」の違いを一目で理解
「過程」と「課程」は、どちらも「かてい」と読む同音異義語です。
一見似ていますが、意味も使い方も全く異なります。
「過程」は物事が進んでいく道筋やプロセスを指し、「課程」は学校などで定められた学習内容やカリキュラムを意味します。
この違いを正しく理解すれば、間違えることはありません。
意味の違いを比較表で整理
まずは、両者の基本的な違いを表で確認しましょう。
| 項目 | 過程 | 課程 |
|---|---|---|
| 読み方 | かてい | かてい |
| 基本的な意味 | 物事が進行する道筋・プロセス | 学習・訓練の計画や内容 |
| 使われる場面 | 仕事、製造、成長など一般的な場面 | 教育、資格取得など学習関連 |
| 英語表現 | process(プロセス) | curriculum(カリキュラム)、course(コース) |
| よくある使い方 | 「製造過程」「成長過程」「過程を重視する」 | 「教育課程」「履修課程」「課程を修了する」 |
この表を見れば分かるように、「過程」は動的なプロセス、「課程」は静的なカリキュラムという違いがあります。
「過程」は時間の流れに沿って変化していくものを表し、「課程」はあらかじめ決められた学習内容の枠組みを指します。
そのため、同じ教育の場面でも「学習が進んでいく過程」と「学校で定められた教育課程」では、使う言葉が異なります。
使い分けのポイントは「プロセス」か「カリキュラム」か
使い分けに迷ったときは、英語に置き換えて考えると分かりやすくなります。
◆「プロセス(process)」に置き換えられる場合は「過程」
- 「結果より過程が大事」= 結果よりプロセスが大事
- 「製品の製造過程」= 製品の製造プロセス
- 「成長過程を記録する」= 成長プロセスを記録する
◆「カリキュラム(curriculum)」や「コース(course)」に置き換えられる場合は「課程」
- 「大学の教育課程」= 大学のカリキュラム
- 「博士課程に進学する」= 博士コースに進学する
- 「専門課程を履修する」= 専門コースを履修する
この方法を使えば、ほとんどの場面で正しい使い分けができます。
また、「○○を経る」という表現では「過程を経る」が正しく、「課程を経る」とは言いません。
「修了する」という表現では「課程を修了する」が正しく、「過程を修了する」とは言いません。
このように、組み合わせる動詞にも注意が必要です。
覚え方のコツ
漢字の成り立ちから覚える方法もおすすめです。
✅ 「過程」の「過」= 過ぎる・通り過ぎる
→ 時間が経過していく様子を表す → 動いていくプロセスを意味する
「過程」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
✅ 「課程」の「課」= 課題・課す
→ 与えられた・定められたものを表す → 決められたカリキュラムを意味する
「課程」は、精選版 日本国語大辞典 では次のように説明されています。
出典:精選版 日本国語大辞典 (コトバンク)
友人が大学院に進学するとき「博士課程に合格した!」と報告してくれたのですが、最初は「博士過程」と勘違いしていました。
しかし、これは大学が定めた学習プログラムのことなので、正しくは「博士課程」です。
このように、教育関連では「課程」を使うと覚えておくと間違いが減ります。
【ここがポイント!】
✓ 過程 = 物事が進行するプロセス(時間の流れを伴う)
✓ 課程 = 定められた学習プログラム(教育・資格関連)
✓ 迷ったら英語で考える:process → 過程、curriculum → 課程
✓ 一般的には「過程」の使用頻度が圧倒的に高い
「過程」の意味と使い方
「過程」は、物事が始まりから終わりまで進んでいく道筋を表す言葉です。
ビジネスや日常生活で最もよく使われる「かてい」で、結果に至るまでの一連の流れやプロセスを指します。
時間の経過とともに変化していく様子を表現するときに使います。
「過程」の基本的な意味
「過程」は、ある物事が変化し進行していく際の段階や経路を意味します。
スタートからゴールまでの間にある、すべてのステップや出来事を含んだ概念です。
辞書的には「物事が変化し進行して、ある結果に達するまでの道筋」と定義されます。
重要なのは、「過程」には必ず時間の流れが含まれているという点です。
何かが始まって、途中で変化や進展があり、最終的に結果に至るまでの一連の動きを捉えた言葉です。
そのため、静止した状態や固定されたものには使いません。
また、「過程」という言葉には、結果だけでなく途中経過にも価値があるというニュアンスが含まれています。
「結果より過程が大事」という表現がよく使われるのは、この言葉が持つ特徴を表しています。
プロジェクトの進め方、問題解決の手順、成長の軌跡など、目に見えにくい部分を大切にする場面で「過程」が活躍します。
さらに、「過程」は単なる順序だけでなく、その途中で起こる試行錯誤や困難、発見なども含みます。
完成品だけを見るのではなく、どのように作られたか、どんな工夫があったかという背景まで含めて表現できる言葉です。
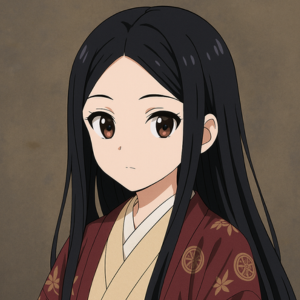
何度も書き直し、悩み、眠れぬ夜を過ごしましたの。
完成した物語だけでなく、その創作の「過程」にこそ、作者の魂が宿るのですわよ。
ほほほ。
「過程」を使う具体的な場面
「過程」は、教育、ビジネス、製造業、研究など、幅広い分野で使われます。
特に以下のような場面で頻繁に登場します。
◆ビジネス・仕事の場面
- プロジェクトの進行状況を報告するとき
- 業務の手順や工程を説明するとき
- 問題解決のプロセスを振り返るとき
- 意思決定に至った経緯を説明するとき
会社の先輩が新人に「この仕事は結果も大事だけど、そこに至る過程で何を学んだかがもっと重要だよ」とアドバイスしていたのを聞いたことがあります。
失敗しても、その過程で試行錯誤した経験が次に活きるという意味で、「過程」という言葉を使っていました。
◆製造・生産の場面
- 製品がどのように作られるかを説明するとき
- 品質管理のチェックポイントを示すとき
- 原料から完成品までの流れを追うとき
◆成長・発達の場面
- 子どもの成長記録をつけるとき
- スキルアップの軌跡を振り返るとき
- 組織の変遷を語るとき
◆科学・研究の場面
- 実験の手順を記録するとき
- 現象の発生メカニズムを説明するとき
- データ分析の手法を報告するとき
これらの場面に共通するのは、「どのように変化したか」「どんな手順を踏んだか」という時間軸を伴う説明が必要な点です。
「過程」の例文集(5つ)
実際の使い方を例文で確認しましょう。
例文1:ビジネス
「新商品の開発過程で、お客様の声を何度も取り入れて改良を重ねました。」
→ 開発がどのように進められたかというプロセスを表現
例文2:教育
「子どもの学習過程を観察することで、つまずきやすいポイントが見えてきた。」
→ 学習がどう進んでいくかという変化の様子を表現
例文3:製造
「この製品の製造過程では、厳しい品質チェックが3回行われます。」
→ 製造がどのように行われるかという手順を表現
例文4:成長
「今回の失敗は、成長過程における貴重な経験だと前向きに捉えています。」
→ 成長していく道のりの一部として表現
例文5:意思決定
「最終決定に至る過程では、多くの関係者の意見を聞きました。」
→ 決定までのプロセスを表現
これらの例文を見ると、「過程」は常に「動き」「変化」「進行」を伴っていることが分かります。
「課程」の意味と使い方
「課程」は、教育や訓練の場面で使われる言葉で、学校や組織が定めた学習内容や履修すべきプログラムを指します。
「過程」とは異なり、あらかじめ決められた固定的な枠組みを表現するときに使います。
特に教育分野では欠かせない言葉です。
「課程」の基本的な意味
「課程」は、学校などで一定期間に学ぶべき内容や科目の体系を意味します。
辞書的には「学校などで、一定期間に割り当ててさせる学習・作業の範囲・順序」と定義されます。
「過程」との大きな違いは、時間の流れではなく、内容の枠組みを表す点です。
「課程」には「課す」という漢字が含まれているように、誰かによって設定された、学ぶべき範囲やプログラムを指します。
そのため、自然に進んでいくものではなく、計画的に定められたものに使われます。
また、「課程」は教育機関や資格制度など、公式な場面で使われることが多い言葉です。
学校の教育システム、大学の専攻プログラム、国家資格の取得ルートなど、制度として確立されているものを表現します。
日常会話ではあまり使わず、フォーマルな文書や公式な説明で登場する傾向があります。
「課程」という言葉は、単に科目の羅列ではなく、体系的に組み立てられた学習プログラム全体を指すことも重要なポイントです。
たとえば「大学の教育課程」と言えば、4年間で履修すべきすべての科目や単位、卒業要件までを含んだ全体的な仕組みを意味します。
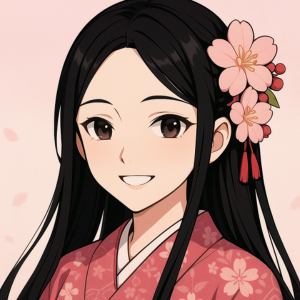
「美女になる課程」なんて存在しませんけれど、教養を身につける「修練課程」は確かにございましたの。
ふふ、「過程」じゃなくて「課程」と覚えてくださいな。
「課程」を使う具体的な場面
「課程」は、主に教育関連や資格取得の場面で使われます。
以下のような状況で頻繁に登場します。
◆学校教育の場面
- 小学校から高校までの教育内容を示すとき
- 大学の専攻や学位プログラムを説明するとき
- 履修科目や卒業要件を示すとき
- カリキュラムの変更を通知するとき
知人が教員をしているのですが、「新しい教育課程が導入されて、授業の進め方が大きく変わった」と話していました。
これは文部科学省が定めた学習指導要領のことで、学校が教えるべき内容全体を指しています。
このように、公的に定められた教育の枠組みには「課程」が使われます。
◆大学院・専門教育の場面
- 修士課程や博士課程への進学を説明するとき
- 専攻分野のプログラムを紹介するとき
- 研究者としてのキャリアパスを示すとき
◆資格・免許取得の場面
- 国家資格の取得ルートを説明するとき
- 専門職の養成プログラムを案内するとき
- 研修や講習の体系を示すとき
◆訓練・育成の場面
- 社員研修プログラムを説明するとき
- 技能習得のためのコースを案内するとき
- 認定制度の要件を示すとき
これらの場面に共通するのは、「何を学ぶべきか」が明確に定められている点です。
自由に進むのではなく、決められた内容を順序立てて学んでいく仕組みを表現します。
「課程」の例文集(5つ)
実際の使い方を例文で確認しましょう。
例文1:学校教育
「文部科学省が定める教育課程に基づいて、各学校でカリキュラムが組まれています。」
→ 公的に定められた教育内容の枠組みを表現
例文2:大学院
「博士課程に進学して、専門的な研究に取り組むことを決めました。」
→ 大学院の学位プログラムを表現
例文3:資格取得
「看護師になるには、指定された養成課程を修了する必要があります。」
→ 資格取得のために定められたプログラムを表現
例文4:履修
「必修課程の単位をすべて取得したので、来年は選択科目を中心に履修します。」
→ 必ず学ぶべき科目群を表現
例文5:専門教育
「この専門課程では、実践的なスキルを3年間かけて体系的に学びます。」
→ 専門分野の学習プログラムを表現
これらの例文から分かるように、「課程」は常に「定められた学習内容」「決められたプログラム」を指しています。
「過程」と「課程」の使い分け実践ガイド
ここからは、実際の場面でどちらを使うべきか、具体的な使い分けのポイントを解説します。
特に間違えやすいシチュエーションを中心に、正しい選び方を身につけましょう。
ビジネス文書での使い分け
ビジネスシーンでは、報告書や企画書、メールなどで「かてい」を使う機会が多くあります。
どちらを選ぶべきか迷ったときは、以下のポイントを確認しましょう。
◆「過程」を使うべき場面
プロジェクトの進行状況や業務の手順を説明するときは「過程」を使います。
- 「プロジェクト推進の過程で明らかになった課題」
- 「製品開発の過程における品質管理」
- 「意思決定に至る過程を記録する」
- 「業務改善の過程で得られた知見」
これらはすべて、時間の流れに沿った変化やプロセスを表現しています。
◆「課程」を使うべき場面
社員研修や教育プログラムなど、定められた学習内容を指すときは「課程」を使います。
- 「新入社員研修課程の修了者」
- 「管理職養成課程への参加」
- 「専門技術習得課程のカリキュラム」
- 「資格取得のための必修課程」
これらはすべて、あらかじめ設定されたプログラムや枠組みを表現しています。
ビジネス文書では圧倒的に「過程」の使用頻度が高いのが特徴です。
会社の同僚が企画書で「開発課程」と書いてしまい、上司から「これは『開発過程』が正しいよ」と指摘されていたことがありました。
開発がどう進むかというプロセスなので、「過程」が適切です。
教育現場での使い分け
教育分野では両方の言葉が使われますが、使い分けがより重要になります。
混同すると意味が大きく変わってしまうので注意が必要です。
◆「過程」を使う場合
学習や成長がどのように進んでいくかという変化を表すときは「過程」です。
- 「子どもの成長過程を記録する」
- 「学習過程で躓きやすいポイント」
- 「理解に至る過程を大切にする」
- 「思考過程を言語化させる授業」
◆「課程」を使う場合
学校が定めた教育内容や履修プログラムを指すときは「課程」です。
- 「小学校の教育課程」
- 「大学院の博士課程」
- 「必修課程の単位」
- 「専門課程への進級」
同じ教育の話でも、視点が「どう変化するか」なら「過程」、「何を学ぶか」なら「課程」と覚えておくと便利です。
たとえば、「学習指導要領に基づく教育課程」は学ぶべき内容の枠組みなので「課程」、「児童の学習過程における支援」は学びがどう進むかというプロセスなので「過程」となります。
間違えやすいシーンと正しい選び方
実際によく間違えられる表現を集めました。
正しい使い分けを確認しましょう。
◆「○○を修了する」の場合
| 正しい表現 | 間違った表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 課程を修了する | ~~過程を修了する~~ | 修了するのは定められたプログラムなので「課程」 |
| 大学院の修士課程 | ~~大学院の修士過程~~ | 学位プログラムを指すので「課程」 |
◆「○○を経る」「○○を経て」の場合
| 正しい表現 | 間違った表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 過程を経る | ~~課程を経る~~ | 時間の経過やプロセスを経るので「過程」 |
| 長い過程を経て完成した | ~~長い課程を経て完成した~~ | 時間をかけたプロセスなので「過程」 |
◆教育関連でよく間違える表現
| 正しい表現 | 間違った表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 教育課程 | ~~教育過程~~ | 文科省が定める教育内容の体系なので「課程」 |
| 発達過程 | ~~発達課程~~ | 成長がどう進むかというプロセスなので「過程」 |
| 履修課程 | ~~履修過程~~ | 履修すべき科目群のプログラムなので「課程」 |
◆製造・ビジネスでよく使う表現
| 正しい表現 | 間違った表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 製造過程 | ~~製造課程~~ | 製造のプロセスなので「過程」 |
| 生産過程 | ~~生産課程~~ | 生産の流れなので「過程」 |
| 選考過程 | ~~選考課程~~ | 選考がどう進むかというプロセスなので「過程」 |
迷ったときは、「これは時間の流れを表しているか、それとも決められた枠組みを表しているか」と自問すると正解にたどり着けます。
ほとんどの場合、ビジネスや日常生活では「過程」を使い、教育制度や資格制度の話では「課程」を使うと考えれば間違いません。
【使い分けの鉄則!】
✓ 「○○を経る」「○○を辿る」→ 過程
✓ 「○○を修了する」「○○に在籍する」→ 課程
✓ ビジネス文書ではほぼ「過程」を使う
✓ 教育制度・資格制度の話では「課程」を使う
✓ 「教育課程」は専門用語なので絶対に「課程」
よくある間違いと正しい表現
「過程」と「課程」は混同されやすく、実際に間違って使われているケースも少なくありません。
ここでは、特に間違えやすい表現を取り上げて、正しい使い方を解説します。
「結果より過程が大事」は正しい?
答え:正しいです。
この表現は「結果よりも、そこに至るまでのプロセスや取り組み方が大事」という意味です。
時間の流れに沿った変化や経験を指しているので、「過程」が適切です。
もし「結果より課程が大事」と書いてしまうと、「結果よりもカリキュラムが大事」という意味不明な文章になってしまいます。
「課程」は教育プログラムを指す言葉なので、この文脈では使えません。
正しい使用例:
- 「このプロジェクトは結果より過程を重視します」
- 「過程を大切にする教育方針」
- 「失敗しても、その過程で学んだことが財産になる」
スポーツの指導者が「試合に勝つことも大事だけど、そこに至る練習の過程でどれだけ成長できるかが本当の価値だ」と話しているのを聞いたことがあります。
このように、結果に至るまでの努力や経験を表現するときは必ず「過程」を使います。
逆に「課程」を使うのは、「この資格を取るには、指定された課程を修了することが大事」のように、定められたプログラムの話をするときです。
「教育課程」を「教育過程」と書いてしまうミス
これは非常によくある間違いで、公式文書でも時々見かけるミスです。
正しい表現:教育課程 間違った表現:教育過程
「教育課程」は、学校で教えるべき内容や科目の体系を指す専門用語です。
文部科学省が学習指導要領で定めているのは「教育課程」であり、「教育過程」ではありません。
◆「教育課程」とは
学校教育法に基づいて、各学校が編成する教育計画のことです。
どの学年でどの科目を何時間教えるか、どんな内容を学ばせるかを体系的にまとめたものを指します。
これは「決められたカリキュラム」なので「課程」を使います。
◆「教育過程」という言葉は?
厳密には間違いではありませんが、意味が全く異なります。
「教育過程」は「教育という行為が進んでいくプロセス」を意味するため、教育学の研究分野などで使われることがあります。
しかし、学校教育の制度や仕組みを指すときは必ず「教育課程」です。
使い分けの例:
- 「文部科学省が定める教育課程」→ カリキュラムの枠組みなので「課程」
- 「子どもの教育過程における親の役割」→ 教育が進むプロセスなので「過程」
教員採用試験の勉強をしていた友人が、「教育課程」と「教育過程」の違いで混乱していました。
試験では「教育課程」が正式な用語として出題されるため、間違えると減点対象になるそうです。
公式な場面では特に注意が必要です。
混同しやすい他の「かてい」(家庭・仮定)
「過程」「課程」以外にも、同じ読み方をする「家庭」と「仮定」があります。
この4つを正しく使い分けることが重要です。
◆家庭(かてい)
家族が生活を共にする場所や、家族による生活の営みを指します。
- 「家庭環境」
- 「家庭訪問」
- 「家庭科の授業」
- 「家庭を大切にする」
これは「過程」や「課程」とは全く異なる概念なので、通常は間違えることはありません。
ただし、音声入力や変換ミスで「家庭科」を「課程科」と変換してしまうケースがあるので注意が必要です。
◆仮定(かてい)
仮に想定すること、または論理学や数学で前提とする条件を指します。
- 「仮定の話」
- 「仮定法」
- 「これを仮定として議論を進める」
- 「もし〜だと仮定すると」
こちらも意味が明確に異なるため、混同は少ないですが、「仮定する」を「過程する」と誤変換してしまうミスがあります。
◆4つの「かてい」の使い分け表
| 言葉 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|
| 過程 | 物事が進行するプロセス | 製造過程、成長過程 |
| 課程 | 定められた学習プログラム | 教育課程、博士課程 |
| 家庭 | 家族の生活の場 | 家庭環境、家庭訪問 |
| 仮定 | 仮に想定すること | 仮定の話、仮定法 |
この4つの中で最も混同されやすいのが「過程」と「課程」です。
「家庭」と「仮定」は意味が大きく異なるため、通常は文脈から判断できます。
しかし、変換ミスには注意が必要です。
特にスマートフォンやパソコンの予測変換で間違った漢字が出てくることがあるので、送信前に必ず確認しましょう。
【間違えやすい表現に注意!】
✓ 「結果より過程が大事」→ 正しい(プロセスを重視)
✓ 「教育課程」→ 正しい(「教育過程」は間違い)
✓ 「博士課程」→ 正しい(「博士過程」は間違い)
✓ 「過程を経る」→ 正しい(「課程を経る」は間違い)
✓ 4つの「かてい」:過程・課程・家庭・仮定を区別する
「過程」「課程」に関するQ&A
ここまで「過程」と「課程」の違いを詳しく見てきました。
最後に、読者の皆さんから寄せられることの多い質問に答えます。
実際の使用場面で迷いやすいポイントを、Q&A形式で解説します。
「過程」と「課程」はどちらが一般的?
答え:「過程」の方が圧倒的に使用頻度が高いです。
日常会話やビジネスシーンでは、「過程」を使う機会が非常に多くあります。
一方、「課程」は教育関係や資格制度など、限られた場面でしか使われません。
新聞記事やビジネス文書を見ると、「過程」は頻繁に登場しますが、「課程」が出てくるのは教育制度や大学のニュースなど特定の話題に限られます。
そのため、一般的には「過程」の方がよく使われていると言えます。
◆使用頻度の違いが生まれる理由
「過程」は、仕事、製造、成長、変化など、あらゆる物事の進行を表現できる汎用性の高い言葉です。
一方「課程」は、カリキュラムやプログラムという特定の概念を指すため、使える場面が限定されています。
たとえば、日常会話で「今日のプロジェクトの進み具合を話そう」という場面では「過程」を使いますが、「課程」を使う機会はほとんどありません。
「課程」という言葉が出てくるのは、「息子が大学院の博士課程に進学した」「教育課程が改訂された」など、教育制度に関する話題に限られます。
このため、どちらを使うか迷ったときは、教育や資格の話でなければ「過程」を選んでおけば、ほぼ間違いありません。
履歴書や公式文書ではどちらを使うべき?
答え:場面によって使い分けが必要です。
履歴書や公式文書では、正確な言葉選びが特に重要です。
誤用は信頼性を損なう可能性があるため、慎重に選びましょう。
◆履歴書での使い分け
学歴欄で大学院について書くときは「課程」を使います。
- 正しい:「○○大学大学院 博士課程 修了」
- 間違い:「○○大学大学院 博士過程 修了」
これは学位プログラムを指すため、必ず「課程」です。
また、「修士課程在学中」「博士課程前期」なども同様に「課程」を使います。
一方、職務経歴欄で業務の進め方を説明するときは「過程」を使います。
- 「プロジェクトの推進過程でリーダーシップを発揮」
- 「業務改善の過程で新しい手法を導入」
◆その他の公式文書での使い分け
報告書や企画書では、ほとんどの場合「過程」を使います。
- 「調査過程で判明した事実」
- 「意思決定過程の透明化」
- 「開発過程における品質管理」
教育関係の公式文書では「課程」を使います。
- 「教育課程の編成方針」
- 「専門課程の設置について」
- 「養成課程の認定基準」
転職活動をしていた知人が、履歴書に「博士過程」と書いて提出したところ、面接で「これは『課程』が正しいですよ」と指摘されたそうです。
小さなミスですが、細かい部分での正確さは評価に影響します。
公式文書では特に注意しましょう。
「工程」との違いは?
答え:「工程」は製造や作業の手順を指す言葉です。
「過程」「課程」に加えて、もう一つ混同されやすいのが「工程(こうてい)」です。
読み方は異なりますが、意味の違いを理解しておくと使い分けがより正確になります。
◆「工程」の意味と使い方
「工程」は、製造や建設などで、作業を順序立てて行う際の各段階を指します。
特に、作業計画や生産管理の文脈で使われることが多い言葉です。
- 「製造工程の見直し」
- 「建設工程表の作成」
- 「作業工程の効率化」
- 「検査工程でのチェック」
◆3つの「てい」の使い分け
| 言葉 | 読み方 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 過程 | かてい | 物事が進行するプロセス全般 | 成長過程、開発過程 |
| 課程 | かてい | 定められた学習プログラム | 教育課程、博士課程 |
| 工程 | こうてい | 製造・作業の手順や段階 | 製造工程、建設工程 |
「過程」は最も広い意味で使える言葉で、あらゆる変化や進行を表現できます。
「工程」は製造や建設など、具体的な作業手順に特化した言葉です。
「課程」は教育分野に限定された言葉です。
製造業で働く友人は「工程管理」という言葉をよく使いますが、これは生産ラインの各段階を管理することを指します。
同じ製造の話でも「製品開発の過程」と言えば全体的なプロセスを、「製造工程」と言えば具体的な作業手順を指すという違いがあります。
英語ではどう表現する?
答え:「過程」はprocess、「課程」はcurriculumやcourseです。
英語での表現を知っておくと、日本語での使い分けもより明確に理解できます。
◆「過程」の英語表現
process(プロセス) が最も一般的です。
- 「製造過程」→ manufacturing process
- 「意思決定過程」→ decision-making process
- 「成長過程」→ growth process
- 「学習過程」→ learning process
その他、文脈によっては以下も使われます。
- stage(段階)
- phase(局面)
- procedure(手続き)
◆「課程」の英語表現
curriculum(カリキュラム) または course(コース) が使われます。
- 「教育課程」→ educational curriculum
- 「博士課程」→ doctoral course / doctoral program
- 「専門課程」→ specialized course
- 「必修課程」→ required curriculum
◆英語で考える使い分け法(再確認)
迷ったときは、英語に置き換えて考える方法が有効です。
- 「process」に置き換えられる → 「過程」
- 「curriculum」や「course」に置き換えられる → 「課程」
この方法を使えば、ほぼ確実に正しい方を選べます。
英語の意味を理解していれば、日本語でも自然と正しい使い分けができるようになります。
「課程を経る」という表現は正しい?
答え:間違いです。正しくは「過程を経る」です。
これは非常によくある間違いで、注意が必要な表現です。
◆なぜ「課程を経る」は間違いなのか
「経る(へる)」は「時間が経過する」「段階を踏む」という意味の動詞です。
時間の流れやプロセスを表す言葉と組み合わせるのが自然です。
「課程」は時間の流れではなく、定められたプログラムの枠組みを指すため、「経る」とは相性が悪い表現です。
「課程」に使う動詞は「修了する」「履修する」「在籍する」などです。
◆正しい表現と間違った表現
| 正しい表現 | 間違った表現 |
|---|---|
| 長い過程を経て完成した | ~~長い課程を経て完成した~~ |
| 様々な過程を経る | ~~様々な課程を経る~~ |
| 課程を修了する | ~~過程を修了する~~ |
| 課程に在籍する | ~~過程に在籍する~~ |
◆「過程」と「課程」で使う動詞の違い
それぞれの言葉には、相性の良い動詞があります。
「過程」と組み合わせる動詞:
- 過程を経る
- 過程を辿る
- 過程を重視する
- 過程を記録する
- 過程を振り返る
「課程」と組み合わせる動詞:
- 課程を修了する
- 課程を履修する
- 課程に在籍する
- 課程を編成する
- 課程に進学する
会社の書類で「選考課程を経て採用されました」という文章を見つけたことがありますが、これは「選考過程を経て採用されました」が正しい表現です。
選考がどのように進んだかというプロセスの話なので「過程」を使い、さらに「経る」という動詞と組み合わせるのが自然です。
この違いを意識すると、より正確な日本語が使えるようになります。
まとめ
「過程」と「課程」は、どちらも「かてい」と読む同音異義語ですが、意味は全く異なります。
「過程」は物事が進んでいくプロセスを表し、ビジネスや日常生活で広く使われる言葉です。
一方「課程」は、学校や資格制度で定められた学習プログラムを指す専門用語で、使える場面が限られています。
使い分けに迷ったときは、英語に置き換えて考えると分かりやすくなります。
「process(プロセス)」に置き換えられるなら「過程」、「curriculum(カリキュラム)」に置き換えられるなら「課程」です。
また、組み合わせる動詞にも注目しましょう。
「経る」「辿る」なら「過程」、「修了する」「履修する」なら「課程」が正しい選択です。
この記事で紹介したポイントを押さえれば、もう間違えることはありません。
正しい日本語を使って、より伝わりやすい文章を書いていきましょう。



















