
「すみません」と「すいません」、どちらが正しいのか迷ったことはありませんか?
普段何気なく使っているこの言葉ですが、実はビジネスシーンでは使い方を間違えると恥ずかしい思いをすることもあります。
本記事では、「すみません」と「すいません」の違いや正しい使い分け、ビジネスでの注意点を例文付きで徹底解説します。

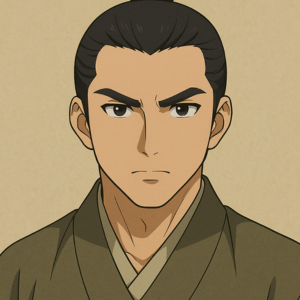
これを読めば、自信を持って正しい言葉遣いができるようになります。
目上の人や取引先とのやり取りで失敗したくない方、言葉遣いに自信を持ちたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
「すみません」と「すいません」の違いとは?

「すいません」と「すみません」、どちらも日常的に使う言葉ですが、正しいのは「すみません」です。
「すいません」は「すみません」が発音しやすく変化した口語表現であり、正式な日本語としては認められていません。
話し言葉では「すいません」でも通じますが、書き言葉や改まった場面では必ず「すみません」を使うのがマナーです。
ここでは、両者の違いと使い分けのポイントを解説します。
結論:正しいのは「すみません」
正式な日本語表記は「すみません」です。
国語辞典にも「すみません」のみが掲載されており、「すいません」は辞書に載っていません。
これは「すみません」が動詞「済む(すむ)」の未然形「済ま(すま)」+丁寧語「ぬ」+丁寧語「せん」から成り立つ言葉だからです。
実際、ビジネス文書や公式な場面では「すみません」が使われます。
例えば、企業のお詫び文や謝罪メールでは必ず「すみません」と記載されます。
文部科学省の公式文書でも「すみません」が標準表記とされています。
一方、「すいません」は話し言葉として広く使われているため、友人や家族との会話では問題ありません。
しかし、就職活動や取引先とのやり取りなど、正式な場面では「すみません」を使うべきです。
言葉の正しさを知ることで、相手に与える印象も大きく変わります。
なぜ「すいません」と言ってしまうのか
「すいません」が広まった理由は、発音のしやすさにあります。
「すみません」の「み」は唇を閉じる音(両唇音)ですが、その直後に「ま」という同じく唇を閉じる音が続きます。
これが発音しづらいため、自然と「すいません」(「い」は唇を横に引く音)に変化したのです。
言語学では、このような発音の変化を「音韻変化」や「音便」と呼びます。
日本語には他にも「寒い(さむい)→さみい」「面白い(おもしろい)→おもしれえ」のように、発音しやすく変化する例が多く存在します。
また、私の友人も無意識に「すいません」と言ってしまい、就職面接で指摘された経験があります。
緊張すると特に口語表現が出やすくなるため、普段から「すみません」を意識して使う習慣をつけることが大切です。
音韻変化は自然な現象ですが、正式な場面では正しい表記を心がけましょう。
話し言葉と書き言葉での使い分け
話し言葉では「すいません」でも許容される場面があります。
友人や家族、親しい同僚との日常会話では「すいません」と言っても失礼にはなりません。
ただし、ビジネスシーンや目上の人との会話では「すみません」を使うのが基本です。
書き言葉では必ず「すみません」を使います。
メール、手紙、レポート、SNSの投稿など、文字で表現する場合は「すみません」が正解です。
特にビジネスメールや公式な文書で「すいません」と書くと、日本語の知識不足と見なされ、信頼を損なう可能性があります。
私の知人は、取引先へのメールで「すいません」と書いてしまい、上司から「言葉遣いに気をつけるように」と注意を受けました。
それ以降、メールを送る前に必ず見直す習慣をつけたそうです。
使い分けの目安は「相手との関係性」と「場面の公式度」です。
迷ったら「すみません」を選べば間違いありません。言葉は相手への敬意を示す大切なツールですので、正しく使い分けましょう。
「すみません」の意味と語源
「すみません」は日本語独特の便利な言葉で、謝罪・感謝・依頼など複数の場面で使えます。
しかし、なぜ一つの言葉でこれほど多様な意味を持つのでしょうか。
その秘密は語源にあります。「すみません」の成り立ちを知ることで、言葉の本質的な意味が理解でき、適切な使い方ができるようになります。
ここでは、「すみません」の語源と3つの意味、そして多用途に使える理由を解説します。
「済む」が語源の「すみません」
「すみません」は動詞「済む(すむ)」が語源です。
「済む」には「物事が終わる」「解決する」「満足する」という意味があり、その否定形「済まない(すまない)」が丁寧語化して「すみません」になりました。
つまり、「すみません」は直訳すると「済まない状態です」という意味になります。
文法的には「済ま(未然形)+ぬ(打消しの助動詞)+せん(丁寧語)」という構造です。
「ぬ」は古語の打消し表現で、現代語の「ない」に相当します。
江戸時代から使われ始め、明治時代以降に広く普及しました。
この「済まない」という感覚が、謝罪だけでなく感謝や依頼にも使われる理由です。
例えば、誰かに親切にされた時「あなたの好意に対して自分は何も返せていない、この状態は済まない」という気持ちから「すみません(ありがとう)」と言います。
私の先輩は、取引先から予想外のサポートを受けた際「すみません、助かります」と言っていました。
これは感謝と恐縮の気持ちが混ざった、まさに「済まない」状態を表現した使い方です。
日本特有の謙遜文化が生んだ、奥深い言葉だと言えるでしょう。
「すみません」の3つの意味
「すみません」は主に3つの意味で使われます。
① 謝罪「ごめんなさい」の意味
最も一般的な使い方です。
自分のミスや迷惑をかけた時に使います。
例えば「遅刻してすみません」「ご迷惑をおかけしてすみません」など。
軽い謝罪から中程度の謝罪まで幅広く対応できます。
② 感謝「ありがとう」の意味
相手の親切や配慮に対して使います。
「わざわざ来ていただいてすみません」「お気遣いいただきすみません」など。
日本人特有の「恐縮」の気持ちを込めた感謝表現です。
③ 依頼・呼びかけの意味
誰かに話しかける時や、お願いする時のクッション言葉として使います。
「すみません、お時間よろしいですか」「すみません、少し道を空けていただけますか」など。
私の同僚は、居酒屋で店員を呼ぶ時に「すみません!」と大声で言って、上司から「呼びかけの『すみません』は丁寧に言わないと失礼だよ」と指摘されていました。
同じ「すみません」でも、使う場面とトーンによって印象が変わります。
なぜ謝罪・感謝・依頼に使えるのか
「すみません」が多用途に使える理由は、「相手に対して気持ちが済まない」という共通の心理があるからです。
謝罪の場合: 迷惑をかけた→申し訳ない気持ちが済まない
感謝の場合: 親切を受けた→恩返しできず気持ちが済まない
依頼の場合: 手間をかける→負担をかけて気持ちが済まない
このように、すべて「相手に対して負い目を感じる」という共通点があります。
日本の文化では、相手との関係性や恩義を重視するため、「すみません」という言葉が多機能化したのです。
欧米では謝罪は"Sorry"、感謝は"Thank you"と明確に分けますが、日本語の「すみません」は両方の気持ちを含むことができます。
この曖昧さが、時に誤解を生むこともあります。
私の後輩は、アメリカ人の同僚に感謝の気持ちで「すみません」と言ったら、「なぜ謝るの?」と不思議がられたそうです。
外国人とコミュニケーションする際は、「ありがとう」と「すみません」をはっきり使い分けることが大切です。
文化の違いを理解して、適切に言葉を選びましょう。
ビジネスシーンで「すみません」を使う時の注意点
「すみません」は便利な言葉ですが、ビジネスシーンでは使い方に注意が必要です。
特に、目上の人や取引先との関係では、「すみません」だけでは失礼にあたる場面が多くあります。
カジュアルすぎる印象を与えたり、誠意が伝わらなかったりする可能性があるため、TPOに応じた言葉選びが求められます。
ここでは、ビジネスシーンで「すみません」を使う際の3つの重要な注意点を解説します。
ビジネスメールでは使用を避ける
ビジネスメールで「すみません」を使うのは避けましょう。
メールは記録に残る正式な文書であり、「すみません」は口語的でカジュアルすぎる表現です。
代わりに「申し訳ございません」「恐れ入ります」などの丁寧な表現を使うべきです。
例えば、納期遅延のお詫びメールで「すみません、遅れてしまいました」と書くと、軽い印象を与えてしまいます。
「誠に申し訳ございません。納期に遅れが生じてしまいました」と書くことで、真摯な姿勢が伝わります。
また、「すみません」は複数の意味(謝罪・感謝・依頼)を持つため、メールでは誤解を招く可能性があります。
「すみませんが、ご確認ください」という文面では、謝罪なのか依頼なのか曖昧です。
「恐れ入りますが、ご確認いただけますでしょうか」と明確に書く方が適切です。
私の同僚は、取引先への初めてのメールで「すみません、資料を送ります」と書いてしまい、上司から「ビジネスメールでは使わないように」と指導を受けました。
それ以降、メールのテンプレートを作成し、「すみません」を使わない習慣をつけたそうです。
特に謝罪メールでは、「すみません」ではなく「お詫び申し上げます」「深くお詫びいたします」などの表現を使いましょう。
言葉の重みが相手への誠意を示します。
目上の人や取引先には不適切
上司や先輩、取引先など目上の人に対して「すみません」を使うのは失礼にあたります。
「すみません」は親しい関係や同僚間では許容されますが、敬意を示すべき相手には不十分な表現です。
対面での会話でも、重要な謝罪や正式な依頼では「すみません」ではなく、「申し訳ございません」「恐縮です」「失礼いたしました」を使うべきです。
例えば、会議に遅刻した場合、「すみません、遅れました」ではなく「申し訳ございません。遅刻いたしました」と言う方が適切です。
感謝を伝える場合も同様です。「すみません、ありがとうございます」という曖昧な表現より、「ありがとうございます。大変助かりました」とはっきり感謝の気持ちを伝える方が好印象です。
私の知人は、社長に資料を手渡す際「すみません、これです」と言ってしまい、先輩から「社長には『失礼いたします』と言うべきだよ」とアドバイスされました。
その場では問題にならなかったものの、言葉遣いの重要性を痛感したそうです。
ただし、軽い呼びかけや廊下でのすれ違いなど、形式ばる必要がない場面では「すみません」でも問題ありません。
状況に応じて柔軟に使い分けることが大切です。
多用すると軽い印象を与える
「すみません」を連発すると、誠意が感じられず、かえって軽薄な印象を与えます。
「すみません、すみません、本当にすみません」と繰り返すより、一度しっかりと「申し訳ございません」と伝える方が効果的です。
また、謝る必要がない場面で「すみません」を使いすぎると、自信がない印象や、卑屈な印象を与えてしまいます。
例えば、プレゼンの冒頭で「すみません、今日は緊張しておりまして…」と言うより、「本日はお時間をいただきありがとうございます」と前向きに始める方が好印象です。
「すみません」を口癖にしてしまう人は、次のような言い換えを意識しましょう。
- 感謝の場面→「ありがとうございます」
- 依頼の場面→「恐れ入りますが」「お手数ですが」
- 謝罪の場面→「申し訳ございません」
私の後輩は、上司との会話で「すみません」を連発する癖があり、「謝りすぎると自信がないように見えるよ」と指摘されていました。
意識して言い換え表現を使うようにしたところ、上司からの評価も上がったそうです。
言葉は相手への敬意と自分の印象を左右します。
「すみません」は便利な言葉ですが、ビジネスシーンでは使いすぎに注意し、場面に応じた適切な表現を選びましょう。
「すみません」の正しい使い方を例文で確認
「すみません」を正しく使うためには、具体的な場面をイメージすることが大切です。
同じ「すみません」でも、謝罪・感謝・依頼のどの意味で使うかによって、前後の文脈や言い方が変わります。
ここでは、実際のビジネスシーンや日常生活で使える例文を紹介しながら、「すみません」の適切な使い方を確認していきます。
例文を参考に、自分の状況に合わせて応用してみてください。
謝罪として使う場合の例文
謝罪の「すみません」は、自分のミスや相手に迷惑をかけた時に使います。
ただし、重大なミスや正式な謝罪では「申し訳ございません」を使う方が適切です。
【日常生活での例文】
- 「すみません、待たせてしまって」(友人との待ち合わせ)
- 「すみません、足を踏んでしまいました」(電車内で)
- 「すみません、間違えて取ってしまいました」(スーパーで)
【職場での例文】
- 「すみません、確認が遅れてしまいました」(同僚へ)
- 「すみません、コピーミスをしてしまいました」(先輩へ、軽いミス)
- 「すみません、さっきの説明が分かりにくかったですね」(会議で)
【より丁寧な謝罪例文】
- 「申し訳ございません。ご迷惑をおかけしました」(上司・取引先へ)
- 「大変失礼いたしました。以後気をつけます」(重要な場面)
私の友人は、取引先との商談で資料を忘れてしまい、「すみません、忘れてしまいました」と言った後、すぐに「大変申し訳ございません。すぐに取りに戻ります」と言い直したそうです。
最初の「すみません」は反射的に出た言葉でしたが、きちんと言い直すことで誠意が伝わり、信頼を損なわずに済みました。
謝罪の際は、「すみません」の後に必ず具体的な理由や改善策を添えることが重要です。
「すみません」だけで終わらせず、「今後このようなことがないよう注意します」と付け加えましょう。
感謝として使う場合の例文
感謝の「すみません」は、相手の親切や配慮に対して「申し訳ない」という気持ちを込めて使います。
ただし、ビジネスシーンでは「ありがとうございます」とはっきり感謝を伝える方が好印象です。
【日常生活での例文】
- 「すみません、わざわざ送ってくれて」(友人に送ってもらった時)
- 「すみません、荷物持っていただいて」(手伝ってもらった時)
- 「すみません、お気遣いありがとうございます」(差し入れをもらった時)
【職場での例文】
- 「すみません、助かります」(同僚にサポートしてもらった時)
- 「すみません、急な依頼だったのに対応してくれて」(協力してもらった時)
- 「すみません、いつもフォローしていただいて」(先輩への感謝)
【より明確な感謝例文】
- 「ありがとうございます。大変助かりました」(目上の人へ)
- 「お忙しい中ご対応いただき、感謝申し上げます」(取引先へ)
私の同僚は、上司が急な仕事をカバーしてくれた時、「すみません、ありがとうございます」と曖昧に言ってしまい、後で先輩から「感謝を伝える時は『ありがとうございます』だけでいいよ。
謝る必要はないから」とアドバイスされました。
それ以降、感謝の場面では「すみません」を使わず、はっきり「ありがとうございます」と言うように心がけているそうです。
日本人は謙遜の文化から「すみません」を使いがちですが、感謝の気持ちは「ありがとう」とストレートに伝える方が相手も嬉しいものです。
特にビジネスでは、感謝と謝罪を混同しないよう注意しましょう。
依頼・呼びかけとして使う場合の例文
依頼や呼びかけの「すみません」は、相手に手間をかける前のクッション言葉として使います。
丁寧に声をかけることで、相手の協力を得やすくなります。
【日常生活での例文】
- 「すみません、お会計お願いします」(レストランで)
- 「すみません、少し道を空けていただけますか」(通路で)
- 「すみません、写真を撮っていただけませんか」(観光地で)
- 「すみません、この辺りに郵便局はありますか」(道を尋ねる時)
【職場での例文】
- 「すみません、今お時間よろしいでしょうか」(上司に話しかける時)
- 「すみません、この書類を確認していただけますか」(同僚への依頼)
- 「すみません、少しお伺いしたいことがあるのですが」(質問する時)
【より丁寧な依頼例文】
- 「恐れ入りますが、ご確認いただけますでしょうか」(上司・取引先へ)
- 「お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです」(メールでの依頼)
- 「失礼いたします。少しお時間をいただけますでしょうか」(正式な依頼)
私の後輩は、初めて上司に質問する際、いきなり「これ教えてください」と言ってしまい、別の先輩から「まず『すみません、今よろしいですか』と声をかけてから質問するといいよ」と教わりました。
クッション言葉を入れるだけで、相手に与える印象が大きく変わることを学んだそうです。
依頼の際は、「すみません」の後に「~していただけますか」「~よろしいでしょうか」という丁寧な表現を続けることがポイントです。
また、依頼後には必ず「ありがとうございます」と感謝を伝えましょう。
シーン別「すみません」の言い換え表現
「すみません」は便利な言葉ですが、ビジネスシーンでは言い換え表現を使うことで、より適切で丁寧な印象を与えられます。
特に、目上の人や取引先とのやり取りでは、場面に応じた言い換えが不可欠です。
謝罪・感謝・依頼・呼びかけの4つのシーンごとに、最適な言い換え表現を使い分けることで、あなたのビジネスマナーが格段に向上します。
ここでは、実践的な言い換え表現と使い方を詳しく解説します。
謝罪する時の言い換え表現
謝罪の場面では、ミスの重大度や相手との関係性によって言い換え表現を選びましょう。
【軽い謝罪】
- 「失礼いたしました」→会議に少し遅れた時、軽いミスの時
- 「申し訳ございません」→一般的な謝罪、ビジネスで最も使いやすい
- 「ご迷惑をおかけしました」→相手に手間をかけた時
【重い謝罪】
- 「深くお詫び申し上げます」→重大なミス、正式な謝罪文
- 「誠に申し訳ございませんでした」→取引先への謝罪
- 「お詫びの言葉もございません」→最上級の謝罪
【状況別の謝罪表現】
- 遅刻した時:「お待たせして申し訳ございません」
- 返信が遅れた時:「ご返信が遅くなり、申し訳ございません」
- ミスをした時:「私の確認不足でご迷惑をおかけし、深くお詫びいたします」
- 聞き返す時:「恐れ入りますが、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」
私の先輩は、取引先への納品遅延の謝罪で、最初「すみませんでした」とメールを送ろうとしましたが、上司から「それでは軽すぎる。『深くお詫び申し上げます』と書きなさい」と指導されました。
言葉の重みが誠意を表すため、状況に応じた適切な表現を選ぶことが重要だと学んだそうです。
また、謝罪の際は言葉だけでなく、原因説明と再発防止策をセットで伝えることが大切です。
「申し訳ございません。確認体制を見直し、今後このようなことがないよう徹底いたします」と具体的に伝えましょう。
感謝を伝える時の言い換え表現
感謝の場面では、「すみません」ではなく明確に感謝の気持ちを表現しましょう。
【基本的な感謝表現】
- 「ありがとうございます」→最も一般的で万能な表現
- 「感謝いたします」→ビジネスメールで丁寧
- 「お礼申し上げます」→正式な感謝
【より丁寧な感謝表現】
- 「誠にありがとうございます」→取引先への感謝
- 「深く感謝申し上げます」→特別な配慮への感謝
- 「心より御礼申し上げます」→書面での丁寧な感謝
【状況別の感謝表現】
- 助けてもらった時:「大変助かりました。ありがとうございます」
- 配慮してもらった時:「お心遣いに感謝いたします」
- 時間を割いてもらった時:「お忙しい中お時間をいただき、ありがとうございました」
- 親切にしてもらった時:「ご親切に感謝いたします」
私の同僚は、上司が残業を手伝ってくれた時、反射的に「すみません」と言いそうになりましたが、「ありがとうございます。大変助かりました」とはっきり感謝を伝えました。
後で上司から「君は感謝の伝え方が上手だね」と褒められたそうです。
日本人は謙遜から「すみません」と言いがちですが、感謝の場面では「ありがとう」とストレートに伝える方が、相手も気持ちよく受け取れます。
特に、相手が好意でしてくれたことに対しては、謝罪ではなく感謝で応えることが、良好な人間関係を築くコツです。
依頼する時の言い換え表現
依頼の場面では、相手への配慮を示すクッション言葉を使いましょう。
【基本的な依頼表現】
- 「恐れ入りますが」→丁寧で使いやすい、ビジネスで頻出
- 「お手数ですが」→相手に手間をかけることへの配慮
- 「恐縮ですが」→申し訳ない気持ちを込めた依頼
【より丁寧な依頼表現】
- 「誠に恐れ入りますが」→重要な依頼
- 「お忙しいところ恐縮ですが」→忙しい相手への依頼
- 「ご面倒をおかけしますが」→手間がかかる依頼
【状況別の依頼表現】
- 確認を依頼する時:「恐れ入りますが、ご確認いただけますでしょうか」
- 教えてもらう時:「お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです」
- 急ぎの依頼:「大変恐縮ですが、お急ぎでご対応いただけますでしょうか」
- 追加の依頼:「重ねてのお願いで恐縮ですが」
私の後輩は、上司に資料作成を依頼する際、「これ作ってください」と直接的に言ってしまい、先輩から「『恐れ入りますが、資料作成をお願いできますでしょうか』と言った方がいいよ」とアドバイスされました。
クッション言葉を使うだけで、依頼がスムーズに通りやすくなることを実感したそうです。
依頼の際は、理由や期限も明確に伝えることが大切です。
「恐れ入りますが、明日までに○○の確認をお願いできますでしょうか。△△のためです」と具体的に伝えましょう。
呼びかける時の言い換え表現
呼びかけや話しかける時も、丁寧な表現を使うことで好印象を与えます。
【基本的な呼びかけ表現】
- 「失礼いたします」→上司の席に行く時、部屋に入る時
- 「お疲れ様です」→社内で声をかける時
- 「恐れ入ります」→忙しそうな人に声をかける時
【より丁寧な呼びかけ表現】
- 「失礼いたします。今お時間よろしいでしょうか」→正式な場面
- 「お忙しいところ失礼いたします」→忙しい相手への配慮
- 「お手すきの際で結構ですので」→急ぎでない依頼
【状況別の呼びかけ表現】
- 会議室に入る時:「失礼いたします」
- 電話をかける時:「お世話になっております。○○の△△と申します」
- 質問する時:「恐れ入りますが、ひとつお伺いしてもよろしいでしょうか」
- 通路で声をかける時:「お疲れ様です。少しお時間よろしいですか」
私の知人は、新入社員の頃、上司に話しかける際にいつも「すみません」と言っていましたが、先輩から「『失礼いたします』の方が丁寧だよ」と教わりました。
それ以降、上司の席に行く時は必ず「失礼いたします。今よろしいでしょうか」と声をかけるようにしたところ、上司からの印象も良くなったそうです。
呼びかけの際は、相手の状況を確認してから本題に入ることがマナーです。
いきなり用件を話すのではなく、「今お時間よろしいですか」と一言添えることで、相手への配慮が伝わります。
「すみません」に関するよくある質問
「すみません」と「すいません」の違いや使い方について、よくある疑問をQ&A形式で解説します。
日常生活やビジネスシーンで迷いがちなポイントを、具体的な事例を交えて分かりやすく回答します。
これらの疑問を解消することで、より自信を持って適切な言葉遣いができるようになります。
「すいません」は間違いですか?
「すいません」は完全な間違いではありませんが、正式な日本語としては認められていません。
国語辞典には「すみません」のみが掲載されており、「すいません」は口語表現として扱われています。
話し言葉では「すいません」でも通じますし、友人や家族との日常会話では問題ありません。
実際、多くの日本人が無意識に「すいません」と発音しています。
これは発音のしやすさから生まれた自然な音韻変化です。
しかし、書き言葉では必ず「すみません」を使うべきです。
特にビジネスメール、公式な文書、レポート、履歴書などでは「すいません」と書くと、日本語の知識不足と見なされる可能性があります。
また、面接や商談など改まった場面では、話し言葉でも「すみません」と正しく発音する方が好印象です。
私の友人は、就職面接で緊張のあまり「すいません」と言ってしまい、面接官から「正しくは『すみません』ですよ」と指摘されて恥ずかしい思いをしたそうです。
結論として、「すいません」は間違いではありませんが、カジュアルな場面に限定し、公式な場面や書き言葉では「すみません」を使いましょう。
迷ったら「すみません」を選べば確実です。
正しい言葉遣いを身につけることで、社会人としての信頼度が高まります。
友達同士なら「すいません」でもOK?
友達同士の日常会話であれば、「すいません」でも全く問題ありません。
親しい間柄では言葉遣いに厳格なルールはなく、むしろ自然なコミュニケーションが大切です。
友人との会話では「すいませ〜ん」「ごめ〜ん」「わりい」など、さらにカジュアルな表現も使われます。
これらは親密さを表す言葉であり、友情を深める役割を果たします。
ただし、LINEやメールなどの文字でのやり取りでは注意が必要です。
友人でも「すいません」より「すみません」と書く方が丁寧な印象を与えます。
特に、真剣な謝罪や感謝の場面では、きちんと「すみません」「ありがとう」と書く方が気持ちが伝わります。
私の友人グループでは、普段の会話では「すいませ〜ん」と軽く言いますが、誰かに迷惑をかけた時や心から感謝する時は、ちゃんと「ごめんね、本当にすまなかった」「ありがとう、助かったよ」とはっきり伝えるようにしています。
また、友人の中でも言葉遣いを大切にする人や、年上の友人には「すみません」と言う方が無難です。
相手によって使い分けることで、良好な人間関係を保てます。
結論として、親しい友達との気軽な会話では「すいません」でOKですが、重要な場面や文字でのやり取りでは「すみません」を使う方が、相手への配慮が伝わります。
「すみません」を英語で言うと?
「すみません」は状況によって英語表現が異なります。
日本語の「すみません」は多用途ですが、英語では謝罪・感謝・呼びかけを明確に使い分ける必要があります。
【謝罪の場合】
- 「Sorry」→一般的な謝罪、友人や同僚に
- 「I'm sorry」→より丁寧な謝罪
- 「I apologize」→ビジネスでの正式な謝罪
- 「My apologies」→丁寧な謝罪
- 「Excuse me」→軽い謝罪(ぶつかった時など)
【感謝の場合】
- 「Thank you」→基本的な感謝
- 「Thank you so much」→深い感謝
- 「I appreciate it」→ビジネスでの感謝
【呼びかけ・依頼の場合】
- 「Excuse me」→人に話しかける時
- 「Pardon me」→丁寧な呼びかけ
- 「Could you~?」→依頼する時
私の同僚は、アメリカ人の取引先に「I'm sorry for your help」と言ってしまい、相手に「なぜ謝るの?」と不思議がられました。
正しくは「Thank you for your help」です。
日本人は感謝の場面でも「すみません」を使う習慣があるため、英語に直訳すると誤解を招きます。
また、レストランで店員を呼ぶ時は「Excuse me」、道を尋ねる時も「Excuse me, could you tell me~?」が適切です。
英語圏では謝罪と感謝を明確に区別するため、「すみません」を英語にする際は、自分がどの意味で使っているのかを意識しましょう。
適切な英語表現を選ぶことで、スムーズなコミュニケーションができます。
「ごめんなさい」との違いは?
「すみません」と「ごめんなさい」は両方とも謝罪表現ですが、使用場面とニュアンスが異なります。
【すみません】
- 軽い謝罪から中程度の謝罪まで幅広く使える
- ビジネスシーンでも使用可能(ただし目上の人には不適切)
- 謝罪以外に感謝や依頼の意味も持つ
- フォーマルさ:中程度
【ごめんなさい】
- 個人的な謝罪、親しい関係での謝罪に使う
- ビジネスシーンでは不適切(子供っぽい印象)
- 謝罪の意味のみ
- フォーマルさ:低い
【使い分けの例】
- 友人に遅刻した時:「ごめんなさい、待たせちゃって」
- 同僚に迷惑をかけた時:「すみません、確認漏れがありました」
- 上司に謝る時:「申し訳ございません、今後気をつけます」
私の後輩は、上司に報告ミスを謝る際、「ごめんなさい」と言ってしまい、先輩から「ビジネスでは『ごめんなさい』は使わないよ。『申し訳ございません』と言おう」とアドバイスされました。
「ごめんなさい」は親しい関係でのみ使う言葉です。また、重大なミスの場合は「すみません」「ごめんなさい」どちらも不十分です。
「大変申し訳ございませんでした」「深くお詫び申し上げます」など、より丁寧な表現を使いましょう。
結論として、「ごめんなさい」は親しい関係での軽い謝罪、「すみません」は日常的な一般的な謝罪、「申し訳ございません」はビジネスでの正式な謝罪と覚えておきましょう。
「すみません」を連発する癖を直すには?
「すみません」を口癖のように連発してしまう人は多くいます。
これは日本人特有の謙遜文化から生まれた習慣ですが、ビジネスシーンでは自信がない印象を与えるため、改善が必要です。
【すみませんを連発する理由】
- 相手に配慮しすぎている
- 自信のなさの表れ
- 間をつなぐクセ
- 謝ることで自分を守ろうとしている
【改善方法】
①感謝の場面では「ありがとう」に変換する
「すみません、手伝ってくれて」→「ありがとうございます、助かります」
②依頼の場面では具体的な言葉を使う
「すみません、お願いできますか」→「恐れ入りますが、ご確認いただけますでしょうか」
③不要な謝罪をしない
プレゼンの冒頭で「すみません、緊張しておりまして」→「本日はお時間をいただきありがとうございます」
④録音して自分の話し方をチェック
会議や商談を録音し、何回「すみません」と言っているか数えてみましょう。
私の知人は、上司から「君は『すみません』が多いね」と指摘され、1週間自分の発言を記録しました。
すると、1日に平均30回以上「すみません」と言っていることが判明。
それから意識的に言い換えるようにしたところ、3ヶ月後には半分以下に減ったそうです。
【意識すべきポイント】
- 謝る必要がない場面では使わない
- 感謝は「ありがとう」で伝える
- 自分の意見を述べる時に謝らない
「すみません」を減らすことで、自信を持ったコミュニケーションができるようになります。
まずは1日に何回言っているか記録することから始めてみましょう。
まとめ
「すみません」と「すいません」の違いについて解説しました。
正しいのは「すみません」であり、「すいません」は口語表現です。
話し言葉では「すいません」でも通じますが、ビジネスメールや改まった場面では必ず「すみません」を使いましょう。
また、ビジネスシーンでは「すみません」だけでは不十分な場面が多くあります。
謝罪では「申し訳ございません」、感謝では「ありがとうございます」、依頼では「恐れ入りますが」など、状況に応じた言い換え表現を使い分けることが大切です。
適切な言葉遣いは、相手への敬意を示し、信頼関係を築く基盤となります。
今日から意識して使い分け、スマートなコミュニケーションを心がけましょう。



















