
「しゅさい」と読む言葉には、「主催」と「主宰」の2つがあります。あなたは正しく使い分けられていますか?
セミナーの案内状を作っているけど、『主催』と『主宰』どっちだろう?

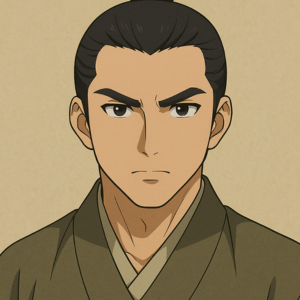
お客様への案内文で間違えたら恥ずかしい…。
こんな悩みを抱えている方は少なくありません。
実は、この2つの言葉は使う場面がまったく違います。
間違えて使うと、相手に誤解を与えたり、ビジネス文書としての信頼性を損なったりする可能性もあります。
でも安心してください。
この記事を読めば、もう迷うことはありません。
この記事でわかること:
- 「主催」と「主宰」の明確な違いと使い分けのルール
- ビジネス文書や招待状での正しい表現方法
- よくある誤用例と、その修正方法
- 「共催」「協賛」「後援」など関連語との違い
- 迷ったときにすぐ判断できる簡単なチェックポイント
実は、覚え方はとてもシンプルです。
「イベントなら主催、組織なら主宰」——この原則さえ押さえれば、ほとんどの場面で正しく使い分けられます。
この記事では、具体的な例文や比較表を使いながら、解説していきます。
ビジネスシーンですぐに使える実践的な知識が身につきますので、ぜひ最後までお読みください。
「主催」と「主宰」の意味
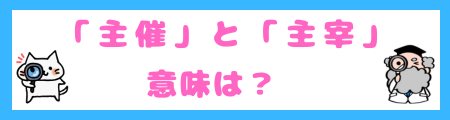
「主催」と「主宰」は、どちらも「しゅさい」と読む同音異義語です。
似ている言葉ですが、使う場面や意味には明確な違いがあります。
「主催」はイベントや行事を企画・運営する責任者を指し、「主宰」は団体や組織を継続的にまとめる立場の人を表します。
ここでは、それぞれの言葉の定義と特徴を詳しく解説します。
「主催」とは(定義と特徴)
「主催」は、イベントや行事、催し物を企画して運営する責任者のことを指します。
コンサート、展覧会、セミナー、スポーツ大会など、具体的な「催し物」に対して使われる言葉です。
「主催」の主な特徴:
- イベントや行事など「一回限りの催し」に使われる
- 企画・運営・実行の責任を負う立場を表す
- 法人でも個人でも使用できる
- ビジネス文書や公式案内で最も一般的
例えば、「このコンサートは○○社が主催します」という使い方をします。

主催者は、会場の手配、チケット販売、当日の運営など、イベント全体に責任を持ちます。
招待状や案内文でよく見かける表現で、「主催:株式会社○○」のように明記されることが多いです。
ビジネスシーンでは、責任の所在を明確にする意味でも重要な言葉といえます。
「主宰」とは(定義と特徴)
「主宰」は、組織や団体、グループを継続的に統率し、中心となって運営する人のことを指します。
文化教室、研究会、流派など、長期的に活動する組織のリーダーに対して使われます。
「主宰」の主な特徴:
- 継続的な組織や団体に使われる
- 中心人物として統率する立場を表す
- 個人に対して使われることが多い
- 伝統芸能や文化活動でよく使用される
例えば、「この茶道教室は山田先生が主宰しています」という使い方をします。
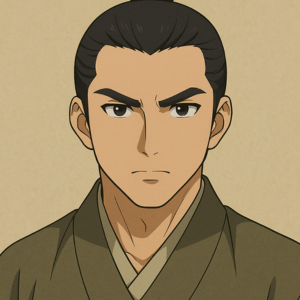
主宰者は、組織の方針を決め、メンバーをまとめ、活動を継続させる役割を担います。
華道の家元、書道教室の師匠、演劇集団の座長など、「その人がいないと成り立たない」ような中心人物に対して使われることが多いです。
一時的なイベントではなく、継続的な活動や組織に焦点が当たる点が「主催」との大きな違いです。
二つの言葉のニュアンスの違い
「主催」と「主宰」の最も大きな違いは、対象が「一時的な催し」か「継続的な組織」かという点です。
言葉のニュアンスを理解すると、使い分けがぐっと簡単になります。
対象の違い:
| 言葉 | 対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 主催 | イベント・行事・催し物 | 一時的 |
| 主宰 | 組織・団体・グループ | 継続的 |
責任の範囲:
- 「主催」は、そのイベントの開催責任を負います。催し物が無事に終われば、責任も完了します。
- 「主宰」は、組織の運営全体に責任を持ち続けます。組織が続く限り、統率責任は継続します。
使われる場面:
- 「主催」→ 展示会、セミナー、コンサート、スポーツ大会など
- 「主宰」→ 茶道教室、研究会、劇団、書道教室など
漢字の意味からも違いが見えてきます。
「催」は「もよおす(催す)」という意味で、何かを起こす・開催するというニュアンスがあります。
一方、「宰」は「つかさどる(司る)」という意味で、統率する・治めるというニュアンスです。
この違いを理解しておけば、「このイベントは誰が主催?」「この教室は誰が主宰?」という使い分けが自然にできるようになります。
「主催」と「主宰」の違い
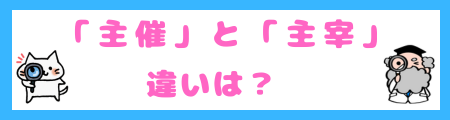
「主催」と「主宰」の違いを、より実践的な視点から整理してみましょう。
使う場面、対象となるもの、責任の範囲という3つの観点から比較すると、両者の違いがより明確になります。
ここでは、具体的なシーンを想定しながら、それぞれの使い分けポイントを解説します。
使う場面の違い
「主催」と「主宰」では、使われる場面が大きく異なります。
どちらを使うべきか迷ったときは、「それが一度きりのものか、続いていくものか」を考えると判断しやすくなります。
「主催」を使う場面:
- コンサートやライブの開催
- 企業が行うセミナーや説明会
- 地域のお祭りやイベント
- スポーツ大会や競技会
- 展覧会や展示会
- 記念式典やパーティー
これらはすべて「特定の日時に行われる催し物」です。
開催日が決まっていて、その日が終われば一区切りつくものに「主催」を使います。
例えば、「来月開催される音楽フェスは○○が主催します」という表現が適切です。

- 茶道教室や華道教室の運営
- 書道の師匠が開く稽古場
- 演劇やダンスの劇団・カンパニー
- 研究会や勉強会の継続的な運営
- 文学サークルや俳句の会
- 流派や一門の統率
これらは「継続的に活動する組織や集まり」です。
特定の日だけでなく、長期間にわたって活動が続くものに「主宰」を使います。
例えば、「この俳句の会は30年前から佐藤先生が主宰しています」という表現になります。
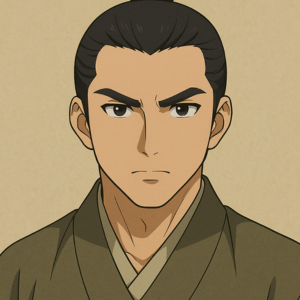
一方、文化活動や芸術分野では「主宰」がよく使われます。
対象(イベント/団体)の違い
「主催」と「主宰」では、対象となるものの性質が根本的に異なります。
この違いを理解すると、使い分けで迷うことがほぼなくなります。
比較表で見る対象の違い:
| 項目 | 主催 | 主宰 |
|---|---|---|
| 対象 | イベント・行事 | 組織・団体 |
| 期間 | 単発・短期 | 継続・長期 |
| 焦点 | 「何をするか」 | 「誰が率いるか」 |
| 例 | セミナー、展示会 | 教室、研究会 |
「主催」の対象:
主催の対象は「形のある催し物」です。
カレンダーに日付を書き込めるような、具体的なイベントに使います。
- 開催日時が明確に決まっている
- 会場や場所が特定されている
- 参加者や観客がいる
- 開始と終了がはっきりしている
例えば、「2025年10月15日開催の就職説明会(主催:○○株式会社)」のように、日時と内容が明確なものです。
「主宰」の対象:
主宰の対象は「人が集まる継続的な組織」です。
カレンダーではなく、組織図や人間関係に焦点が当たります。
- 活動が長期間続く
- メンバーや門下生がいる
- 定期的に集まりや活動がある
- 中心人物の存在が不可欠
例えば、「創立20年の書道教室(主宰:田中先生)」のように、継続的な活動と中心人物がセットになっています。
簡単に言えば、「主催」は「何」に焦点が当たり、「主宰」は「誰」に焦点が当たる言葉です。
案内文で「イベント名」を強調したいなら「主催」、「先生や代表者」を強調したいなら「主宰」と覚えておくと良いでしょう。
責任範囲の違い(開催責任/統率責任)
「主催」と「主宰」では、負う責任の性質も期間も大きく異なります。
この違いは、ビジネス文書で使い分ける際に特に重要なポイントです。
「主催」の開催責任:
主催者が負うのは「イベントを無事に開催・運営する責任」です。
具体的には以下のような責任が含まれます。
- 会場の手配と管理
- 参加者の安全確保
- プログラムの進行管理
- トラブル発生時の対応
- 予算管理と収支責任
責任の期間は「準備期間から終了まで」と限定的です。
イベントが無事に終われば、主催者としての責任も完了します。
例えば、セミナーの主催者は、セミナー当日の運営に責任を持ちますが、翌日以降は基本的に責任を負いません。
「主宰」の統率責任:
主宰者が負うのは「組織を継続的に運営・統率する責任」です。
イベントの成否だけでなく、組織全体の方向性に責任を持ちます。
- 組織の方針決定
- メンバーの指導・育成
- 活動内容の企画・実施
- 組織の存続と発展
- 伝統や理念の継承
責任の期間は「組織が続く限り」と長期的です。
主宰者は、日々の活動から将来の方向性まで、組織全体に責任を持ち続けます。
例えば、茶道教室の主宰者は、毎回のお稽古だけでなく、弟子の育成や流派の伝統継承まで責任を負います。
責任の重さの違い:
どちらの責任が重いかは一概には言えませんが、性質が異なります。
「主催」は短期集中型の責任、「主宰」は長期継続型の責任です。
そのため、公式文書で責任の所在を明確にする場合、イベントなら「主催」、組織なら「主宰」と使い分けることが重要になります。
「主催」と「主宰」のビジネス文書での使い分け
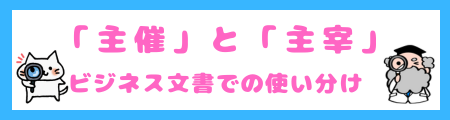
ビジネスシーンでは、「主催」と「主宰」の使い分けを間違えると、相手に誤解を与えたり、失礼な印象を与えたりする可能性があります。
特に招待状や公式文書では、正確な表現が求められます。
ここでは、実際のビジネス文書での正しい使い方と、よくある誤用例を解説します。
招待状・案内文での正しい表現
招待状や案内文は、企業や団体の顔となる重要な文書です。
ここでの言葉選びは、相手への印象を大きく左右します。
基本的にビジネスイベントでは「主催」を使うのが正解です。
招待状で使う基本パターン:
セミナーや展示会、パーティーなどの案内では、以下のような表記が一般的です。
- 「主催:株式会社○○」
- 「主催者:○○協会」
- 「主催:○○実行委員会」
例えば、新製品発表会の招待状なら「主催:株式会社ABC / 日時:2025年11月10日 / 会場:○○ホール」という形式になります。
これは、そのイベントの企画・運営責任を誰が負っているかを明確に示すためです。
「主宰」を使うケース:
ビジネス文書でも、継続的な活動や組織を紹介する場合は「主宰」を使います。
- 社内の勉強会を長年続けている代表者の紹介
- 企業内サークルや研究会の案内
- 文化教室や講座の講師紹介
例えば、「当社の経営研究会は、創業者の山田が主宰しております」のように、組織や活動の中心人物を示す際に使います。
注意したいポイント:
招待状では、複数の団体が関わることもあります。
その場合の表記例は以下の通りです。
- 主催:株式会社○○(メインの責任者)
- 共催:△△協会(共同で開催)
- 後援:××省(応援・支援)
- 協賛:□□株式会社(資金提供)
このように役割を明確に分けることで、誰がどんな責任を持っているのかが一目でわかります。
特に「主催」は最も責任が重い立場なので、間違えないように注意が必要です。
議事録や公式文書での表現
議事録や報告書などの公式文書では、事実を正確に記録することが最優先です。
「主催」と「主宰」の使い分けも、正確性が求められます。
議事録での使用例:
会議の議事録では、イベントや会議そのものについて記録する際に「主催」を使います。
- 「次回のセミナーは当部門が主催する予定」
- 「本会議は人事部主催で開催された」
- 「主催者側から開会の挨拶があった」
議事録は後から見返すことも多いため、誰が責任を持って開催したのかを明確に残すことが重要です。
報告書での使用例:
事業報告書や活動報告書でも、基本的には「主催」を使います。
- 「当社主催のイベントには300名が参加」
- 「主催事業として年間5回のセミナーを実施」
- 「主催者として会場設営から運営まで担当」
ただし、継続的な組織活動を報告する場合は「主宰」を使うこともあります。
- 「社長が主宰する経営塾は今年で10年目を迎えた」
- 「研究部長が主宰する研究会に新メンバーが加わった」
公式文書で避けるべき表現:
以下のような曖昧な表現は、公式文書では避けるべきです。
- 「開催する」だけで主催者を明記しない
- 「主催」と「主宰」を混同して使う
- 責任の所在が不明確な表現
公式文書では「誰が何に責任を持つか」を明確にすることが信頼性につながります。
特に外部に公開する文書では、正確な用語選びが企業や組織の信頼性を示すポイントになります。
誤用例とそのリスク
「主催」と「主宰」の誤用は、思わぬ誤解やトラブルを招くことがあります。
実際のビジネスシーンでよく見られる間違いと、そのリスクを知っておきましょう。
よくある誤用例:
誤用例1:イベントに「主宰」を使う
❌「当社主宰のセミナーにご参加ください」
⭕「当社主催のセミナーにご参加ください」
セミナーは一時的なイベントなので「主催」が正解です。
「主宰」を使うと、やや大げさで不自然な印象を与えます。
誤用例2:組織に「主催」を使う
❌「山田先生主催の茶道教室」
⭕「山田先生主宰の茶道教室」
継続的な教室活動には「主宰」が適切です。
「主催」を使うと、一回限りのイベントのように聞こえてしまいます。
誤用例3:個人イベントでの混同
❌「個人主宰のチャリティーコンサート」
⭕「個人主催のチャリティーコンサート」
個人が開催するイベントでも、コンサートのような催し物には「主催」を使います。
誤用が招くリスク:
言葉の誤用は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。
- 信頼性の低下: 正しい日本語を使えない企業だと思われる
- 責任の曖昧さ: トラブル時に責任の所在が不明確になる
- プロ意識の欠如: ビジネス文書への配慮が足りないと判断される
- 相手への失礼: 文化教室の先生などに「主催」を使うと、軽んじているように感じられる
チェックポイント:
文書を作成したら、以下の点を確認しましょう。
- そのイベントは一時的か、継続的か?
- 対象は催し物か、組織か?
- 中心人物を強調したいか、イベント自体を強調したいか?
迷ったときは、「イベントなら主催、組織なら主宰」というシンプルな原則に立ち返ることが大切です。
特に対外的な文書では、第三者にチェックしてもらうとより安心です。
「主催」と「主宰」の使用例・例文集
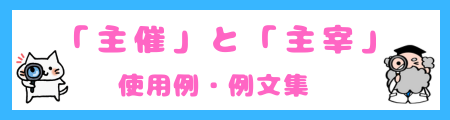
実際の使用例を見ることで、「主催」と「主宰」の使い分けがより具体的にイメージできます。
ここでは、日常やビジネスでよく使われるシーン別の例文と、間違えやすい誤用例を紹介します。
正しい例文と誤用例を比較することで、自然な使い分けができるようになります。
ここでは、実践的な例文を通して使い方を解説します。
「主催」の例文(イベントシーン)
「主催」は、コンサート、セミナー、展示会など、具体的な日時が決まっているイベントで使います。
ビジネスシーンから日常まで、幅広く使える例文を紹介します。
ビジネスイベントの例文:
- 「来月15日に開催される新製品発表会は、当社が主催いたします」
- 「このセミナーは人材開発部が主催し、全社員を対象に実施されます」
- 「展示会の主催者として、会場設営から運営まで責任を持って行います」
- 「主催企業である当社から、開会のご挨拶を申し上げます」
- 「今回の就職説明会は、○○大学と△△企業の共同主催です」
文化・スポーツイベントの例文:
- 「市民マラソン大会は、市と体育協会が主催しています」
- 「この音楽フェスティバルは、地域の商工会議所が主催しています」
- 「美術展の主催は県立美術館で、入場料は無料です」
- 「チャリティーコンサートを主催し、収益は全額寄付されます」
- 「文化祭は生徒会が主催し、各クラスが出し物を企画します」
公的行事の例文:
- 「記念式典は市制100周年実行委員会が主催します」
- 「環境フォーラムは環境省の主催で開催されました」
- 「国際会議の主催国として、各国の代表をお迎えします」
- 「防災訓練は消防署と自治会が主催で行われます」
招待状・案内文での例文:
- 「主催:株式会社ABC / 日時:2025年11月20日14時~ / 会場:○○ホール」
- 「拝啓 このたび弊社主催にて、下記のとおりセミナーを開催いたします」
- 「主催者一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております」
これらの例文に共通するのは、「特定の日時に行われる催し物」であることです。
開催日が明確で、その日が終われば一区切りつくものに「主催」を使っています。
「主宰」の例文(団体・サークルシーン)
「主宰」は、教室、研究会、劇団など、継続的に活動する組織や団体で使います。
中心人物の存在が重要なポイントです。
文化教室・習い事の例文:
- 「この茶道教室は、裏千家の師範である山田先生が主宰しています」
- 「書道教室を主宰して20年、多くの弟子を育ててきました」
- 「華道の家元が主宰する稽古場で、伝統的な技法を学びます」
- 「ピアノ教室を主宰する先生は、国際コンクールの審査員も務めています」
- 「料理研究家が主宰するクッキングスクールに通っています」
研究会・勉強会の例文:
- 「教授が主宰する研究会では、毎月最新の論文を討議します」
- 「経営者が主宰する勉強会に、若手起業家が集まります」
- 「彼女が主宰する読書会は、今年で5年目を迎えました」
- 「医師が主宰する臨床研究グループに新メンバーが加わった」
芸術・文化活動の例文:
- 「演出家が主宰する劇団は、毎年春と秋に公演を行います」
- 「詩人が主宰する文学サークルで、作品の批評会を開いています」
- 「ダンサーが主宰するカンパニーは、国内外で高い評価を得ています」
- 「俳句の会を主宰する先生のもとで、季語の使い方を学びました」
- 「画家が主宰するアトリエには、全国から生徒が集まります」
ビジネス・企業内の例文:
- 「創業者が主宰する経営塾では、次世代リーダーを育成しています」
- 「部長が主宰する社内勉強会に参加して、スキルアップを図ります」
- 「会長が主宰する朝礼会は、創業時から続く伝統です」
これらの例文では、「誰が中心となって組織を率いているか」が明確です。
活動が長期間続き、主宰者の存在が組織のアイデンティティになっている点が共通しています。
誤用例と修正例
実際によくある間違いを知ることで、正しい使い分けが身につきます。
誤用例と正しい修正例を比較して、違いを確認しましょう。
パターン1:イベントなのに「主宰」を使う誤り
❌「当社主宰の新商品発表会を開催します」
⭕「当社主催の新商品発表会を開催します」
理由: 発表会は一時的なイベントなので「主催」が正解です。
❌「地域主宰のお祭りに参加しました」
⭕「地域主催のお祭りに参加しました」
理由: お祭りは年に一度の催し物なので「主催」を使います。
❌「大学主宰のオープンキャンパスが開催されます」
⭕「大学主催のオープンキャンパスが開催されます」
理由: オープンキャンパスは特定日のイベントです。
パターン2:組織なのに「主催」を使う誤り
❌「田中先生主催の書道教室に通っています」
⭕「田中先生主宰の書道教室に通っています」
理由: 継続的な教室活動なので「主宰」が適切です。
❌「彼が主催する研究会は毎週金曜日に開かれます」
⭕「彼が主宰する研究会は毎週金曜日に開かれます」
理由: 定期的に続く研究会は組織活動なので「主宰」です。
❌「劇団を主催している演出家にインタビューしました」
⭕「劇団を主宰している演出家にインタビューしました」
理由: 劇団は継続的な組織なので「主宰」を使います。
パターン3:混同しやすい複雑な例
❌「先生が主宰する発表会に出演します」
⭕「先生が主催する発表会に出演します」
理由: 発表会自体は一時的なイベントです。ただし「先生が主宰する教室の発表会」なら文脈次第で両方あり得ます。
❌「主催者として教室を運営しています」
⭕「主宰者として教室を運営しています」
理由: 教室の継続的な運営者は「主宰者」です。
❌「このセミナーは彼が主宰するシリーズの第3回です」
⭕「このセミナーは彼が主催するシリーズの第3回です」
理由: 個々のセミナーは「主催」ですが、「セミナーシリーズを主宰する」という表現もあり得ます。文脈に注意が必要です。
判断に迷ったときの確認方法:
以下の質問に答えてみましょう。
- それは特定の日時に行われる催し物ですか? → Yes なら「主催」
- それは継続的に活動する組織や団体ですか? → Yes なら「主宰」
- 終わりがある一時的なものですか? → Yes なら「主催」
- 中心人物が率い続ける集まりですか? → Yes なら「主宰」
この確認方法を使えば、ほとんどのケースで正しい判断ができます。
「主催」と「主宰」関連語との違い

「主催」と「主宰」以外にも、イベントや組織運営に関わる似た言葉がたくさんあります。
「共催」「主管」「協賛」「後援」「協力」など、それぞれ役割や責任が異なります。
これらの言葉を正しく理解することで、案内文や報告書での表記ミスを防げます。
ここでは、混同しやすい関連語との違いを解説します。
「共催」・「主管」との違い
イベントを開催する際、複数の団体が関わることがよくあります。
その際に使われる「共催」と「主管」は、「主催」と似ているようで役割が異なります。
「共催」とは:
「共催」は、複数の団体が対等な立場で一緒にイベントを開催することを指します。
責任も費用も分担し、共同で運営します。
- 2つ以上の団体が協力して開催
- 責任と権限を分け合う
- 費用も分担することが多い
- どちらも同等の立場
「共催」の使用例:
- 「このシンポジウムは、A大学とB大学の共催です」
- 「市と商工会議所が共催する産業フェア」
- 「共催:○○協会、△△財団」
「主管」とは:
「主管」は、イベント全体の企画は別の団体が行い、実際の運営や管理を担当する立場を指します。
主催者の下で、実務を取りまとめる役割です。
- 実際の運営業務を担当
- 主催者から委託されることが多い
- 現場での管理責任を持つ
- 主催よりは限定的な責任
「主管」の使用例:
- 「主催:文部科学省 / 主管:全国大学連盟」
- 「大会の主管団体として、競技の運営を担当します」
- 「主催者の方針に基づき、主管団体が実務を行います」
3つの言葉の比較表:
| 言葉 | 責任の範囲 | 立場 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 主催 | 全体的な企画・運営責任 | 最も責任が重い | セミナー主催 |
| 共催 | 分担された企画・運営責任 | 対等な立場で協力 | 2大学共催 |
| 主管 | 実務的な運営責任 | 主催の下で実務担当 | 大会主管 |
使い分けのポイント:
招待状や案内文では、これらを組み合わせて記載することもあります。
- 「主催:○○省 / 共催:△△協会、□□団体 / 主管:◇◇実行委員会」
この場合、○○省が最も責任が重く、△△協会と□□団体が協力し、実際の運営は◇◇実行委員会が担当するという意味になります。
役割分担を明確にすることで、トラブル時の責任の所在もはっきりします。
「協賛」・「後援」との違い
イベントの案内でよく見かける「協賛」と「後援」は、「主催」とは立場が大きく異なります。
これらは直接的な運営には関わらず、支援する側の立場です。
「協賛」とは:
「協賛」は、イベントの趣旨に賛同し、主に資金面や物資面で支援することを指します。
企業がスポンサーとして参加する場合によく使われます。
- 資金や物資を提供して支援
- 企業名やロゴを掲載できることが多い
- 運営には直接関わらない
- 宣伝効果を期待する側面もある
「協賛」の使用例:
- 「協賛:株式会社○○、△△銀行、□□商事」
- 「協賛企業の皆様のご支援により開催できました」
- 「協賛金は大会運営費に充てられます」
- 「協賛企業としてパンフレットに社名を掲載」
「後援」とは:
「後援」は、イベントの趣旨を支持し、名義や広報面で支援することを指します。
官公庁や公的機関、メディアが後援につくことが多いです。
- 名義貸しや広報支援が中心
- 資金提供は基本的にしない
- イベントの信頼性を高める効果
- 公的機関が多い
「後援」の使用例:
- 「後援:文部科学省、○○県、△△市」
- 「後援:NHK、読売新聞社」
- 「後援団体として広報にご協力いただきました」
- 「後援名義の使用許可をいただきました」
4つの言葉の違い:
| 言葉 | 役割 | 責任 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 主催 | 企画・運営 | 全責任を負う | イベント全体 |
| 協賛 | 資金・物資支援 | 支援のみ | お金や物資 |
| 後援 | 名義・広報支援 | 支援のみ | 名前や宣伝 |
| 協力 | 部分的な支援 | 限定的 | 様々な形 |
記載する順序:
案内文では、一般的に以下の順序で記載します。
- 主催(最も責任が重い)
- 共催(主催に準じる)
- 主管(実務担当)
- 後援(名義支援)
- 協賛(資金支援)
- 協力(その他支援)
この順序は、責任の重さや関与度の深さを表しています。
正しい順序で記載することで、各団体の役割が明確になり、プロフェッショナルな印象を与えます。
「協力」との違い
「協力」は、上記のどれにも当てはまらない、より柔軟な支援形態を指します。
「主催」とは立場が大きく異なりますが、案内文でよく使われる言葉です。
「協力」とは:
「協力」は、イベントや活動に対して部分的に手伝いや支援をすることを指します。
資金、物資、人員、場所の提供など、支援の形は様々です。
- 支援内容が多様で柔軟
- 後援や協賛ほど正式でない場合もある
- 部分的な手伝いも含む
- 小規模な支援でも使える
「協力」の使用例:
- 「協力:○○商店街、△△ボランティア団体」
- 「地域の皆様のご協力により開催できました」
- 「会場提供にご協力いただきました」
- 「運営スタッフとしてご協力をお願いします」
- 「取材協力:□□株式会社」
「協力」が使われる具体的なケース:
以下のような様々な支援形態で「協力」という言葉が使われます。
- 会場や施設の無償提供
- ボランティアスタッフの派遣
- 機材や備品の貸し出し
- 広報活動への協力
- 専門知識や技術の提供
- 撮影や取材への協力
主催と協力の関係:
「主催」は全体の責任を負う立場、「協力」は部分的に手伝う立場です。
責任の重さが大きく異なります。
- 主催者:イベント全体に責任を持つ
- 協力者:依頼された範囲で手伝う
例えば、「主催:A団体 / 協力:B団体、C団体」という表記の場合、A団体がすべての責任を負い、B団体とC団体は部分的に支援するという意味になります。
使い分けの実例:
実際の案内文では、以下のように複数の言葉を組み合わせて使います。
「第10回環境フォーラム」
- 主催:環境保護協会
- 共催:○○市、△△大学
- 後援:環境省、××県
- 協賛:□□株式会社、◇◇銀行
- 協力:地域ボランティア連盟、◎◎商店街
このように役割を明確に分けることで、各団体の立場や責任範囲がはっきりし、トラブルを未然に防ぐことができます。
「主催」が最も重要で責任ある立場であることを理解しておきましょう。
「主催」と「主宰」に関するよくある質問
「主催」と「主宰」の使い分けについて、実際によく寄せられる質問をまとめました。
具体的なシーンでの疑問に答えることで、より実践的な理解が深まります。
迷いやすいポイントを中心に、わかりやすく解説します。
ここでは、実際の使用場面で困りやすい3つの質問に答えます。
「主宰セミナー」と書くのは間違い?
「主宰セミナー」という表現は、基本的には間違いです。
ただし、文脈によっては正しい場合もあるので、注意が必要です。
基本的には「主催セミナー」が正解:
セミナーは特定の日時に開催される催し物なので、通常は「主催」を使います。
⭕「当社主催のセミナーを開催します」
⭕「主催:○○株式会社 / テーマ:マーケティング基礎講座」
❌「主宰セミナーにご参加ください」
セミナーという言葉自体が「一時的な勉強会や講習会」を意味するため、「主催」との相性が良いのです。
例外的に「主宰」が使える場合:
ただし、以下のような文脈では「主宰」を使うこともあります。
- 「山田先生が主宰する経営塾のセミナー」
- 「彼女が主宰する研究会の特別セミナー」
この場合、「主宰」がかかっているのは「経営塾」や「研究会」という継続的な組織です。
その組織が開催するセミナーという意味なので、文法的には正しいです。
判断のポイント:
以下の質問で判断できます。
- そのセミナーは単発の催しですか? → 「主催セミナー」
- 継続的な塾や研究会の一環ですか? → 「○○が主宰する△△のセミナー」
間違えやすい表現の例:
❌「主宰セミナー開催のお知らせ」→ ⭕「主催セミナー開催のお知らせ」
❌「弊社主宰によるセミナー」→ ⭕「弊社主催によるセミナー」
⭕「先生が主宰する塾のセミナー」(組織の活動の一部として)
迷ったときは、「セミナー単体」を指すなら「主催」、「組織の活動」を指すなら「主宰」と覚えておくと安心です。
ビジネス文書で単に「セミナー」と書く場合は、ほぼ100%「主催」が正解と考えて良いでしょう。
個人が開く場合は「主催」と「主宰」どちら?
個人が何かを開く場合、「主催」と「主宰」のどちらを使うかは、その内容が一時的なイベントか継続的な活動かで判断します。
「個人だから」という理由だけでは決められません。
個人でも「主催」を使う場合:
個人が一時的なイベントを開催する場合は「主催」を使います。
- 「個人主催のチャリティーコンサートを開きます」
- 「フリーランスとして主催するセミナーに50名が参加」
- 「私が主催するパーティーにぜひお越しください」
- 「彼女が主催する写真展が来月開催されます」
これらはすべて「特定の日に行われる催し物」なので、個人であっても「主催」が正解です。
企業でも個人でも、イベントの性質が重要なのです。
個人でも「主宰」を使う場合:
個人が継続的な組織や教室を運営する場合は「主宰」を使います。
- 「個人で書道教室を主宰しています」
- 「彼が主宰する読書会に毎月参加しています」
- 「フリーの講師として英会話教室を主宰する」
- 「主宰者として10年間、俳句の会を続けてきました」
教室、サークル、研究会など、継続的に人を集めて活動する場合は「主宰」が適切です。
判断基準の整理:
| 開催内容 | 期間 | 使う言葉 | 例 |
|---|---|---|---|
| イベント | 一時的 | 主催 | コンサート、パーティー |
| 組織・教室 | 継続的 | 主宰 | 書道教室、研究会 |
個人の場合の注意点:
個人の場合、以下のような表現もよく使われます。
- 「個人主催のイベント」→ カジュアルな印象
- 「○○(個人名)主催のセミナー」→ よりフォーマルな印象
- 「○○先生主宰の教室」→ 権威や継続性を強調
個人であっても、公式文書や案内状では「主催」「主宰」を正しく使い分けることで、プロフェッショナルな印象を与えられます。
友人同士のカジュアルなイベントでは「主催」という言葉自体を使わず、「○○が開くパーティー」のような表現でも問題ありません。
「主管」と「主催」はどう違う?
「主管」と「主催」は似ているようで、責任の範囲と立場が大きく異なります。
両方が併記されることも多いので、違いをしっかり理解しておきましょう。
「主催」の役割:
「主催」は、イベント全体の企画から実施まで、すべてに責任を持つ立場です。
- イベントの企画立案
- 予算の確保と管理
- 全体的な意思決定
- 最終的な責任
例えば、「主催:文部科学省」と書かれていれば、文部科学省がそのイベント全体に責任を持つという意味です。
何か問題が起きた場合、最終的な責任は主催者が負います。
「主管」の役割:
「主管」は、主催者の方針に基づいて、実際の運営業務を担当する立場です。
- 現場での運営管理
- スケジュール調整
- 参加者対応
- 実務的な責任
例えば、「主管:○○実行委員会」と書かれていれば、実際の運営は実行委員会が行うという意味です。
主催者の指示のもとで動く立場といえます。
具体的な違いの例:
スポーツ大会を例に考えてみましょう。
- 主催:日本体育協会(大会全体の企画・責任)
- 主管:○○県体育協会(実際の運営・現場管理)
この場合、大会の開催を決定し全体に責任を持つのは日本体育協会ですが、会場の手配、選手の受付、競技の進行など、実際の運営業務は○○県体育協会が担当します。
責任の範囲の違い:
| 項目 | 主催 | 主管 |
|---|---|---|
| 企画立案 | ⭕主導的 | △補助的 |
| 予算管理 | ⭕全体責任 | △実務担当 |
| 意思決定 | ⭕最終決定権 | △実務判断のみ |
| 運営実務 | △委任可能 | ⭕直接担当 |
| 最終責任 | ⭕負う | △限定的 |
なぜ役割を分けるのか:
大規模なイベントでは、企画と実務を分けることでスムーズな運営が可能になります。
- 主催者は方針や予算など大きな判断に集中できる
- 主管団体は現場の実務に専念できる
- 地域に根ざした団体が主管を務めることで、地元との連携がスムーズになる
併記される場合の読み方:
案内文で「主催:A / 主管:B」と書かれていたら、以下のように理解できます。
- Aがイベント全体の責任者
- Bが実際の運営を担当
- 問い合わせは主管のBへ
- 公式な決定はAが行う
一般参加者にとっては、日常的な問い合わせは主管団体に、重要な要望や苦情は主催団体にするのが適切です。
役割分担を理解することで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
まとめ
ここまで「主催」と「主宰」の違いについて詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントを振り返りながら、迷ったときにすぐ判断できる基準をお伝えします。
この2つの言葉を正しく使い分けることで、ビジネス文書でも日常会話でも、より正確で信頼される表現ができるようになります。
ここでは、使い分けの核心をまとめます。
「主催」=イベントの責任者
「主催」は、イベントや催し物を企画・運営する責任者を指す言葉です。
使い分けで迷わないために、以下のポイントを押さえておきましょう。
「主催」の核心ポイント:
- 対象はイベント: コンサート、セミナー、展示会、祭りなど具体的な催し物
- 期間は一時的: 開始と終了がはっきりしている
- 責任は開催まで: イベントが終われば責任も完了
- ビジネスで頻出: 公式文書や招待状で最もよく使われる
こんな時は「主催」:
- 「来月セミナーを開きます」→ セミナー主催
- 「会社でパーティーをします」→ パーティー主催
- 「展覧会の案内状を作る」→ 展覧会主催
- 「マラソン大会の責任者」→ 大会主催
覚えやすいキーワード:
「主催」を使うべき場面は、以下のキーワードで判断できます。
- 「開催する」「催す」という動詞と相性が良い
- カレンダーに日付を書き込めるもの
- 「○月○日開催」と日時が明確
- チケットや案内状があるもの
ビジネスシーンでは、90%以上が「主催」を使う場面です。
企業が関わるイベントのほとんどは一時的な催し物なので、迷ったら「主催」を選んでおけば、まず間違いはありません。
「主宰」=組織や会を率いる人
「主宰」は、組織や団体を継続的に統率する中心人物を指す言葉です。
「主催」との違いを明確に理解しましょう。
「主宰」の核心ポイント:
- 対象は組織: 教室、研究会、劇団、サークルなど継続的な団体
- 期間は長期的: 活動が何年も続く
- 責任は継続的: 組織が続く限り統率責任がある
- 人物に焦点: 「誰が率いているか」が重要
こんな時は「主宰」:
- 「茶道教室を20年続けている」→ 教室主宰
- 「研究会のリーダーです」→ 研究会主宰
- 「劇団の代表を務める」→ 劇団主宰
- 「書道の門下生を育てる」→ 教室主宰
覚えやすいキーワード:
「主宰」を使うべき場面は、以下のキーワードで判断できます。
- 「運営する」「率いる」という動詞と相性が良い
- 「○○年目」と継続年数が意味を持つ
- 先生、師匠、家元など指導者の存在
- メンバー、門下生、弟子がいる
文化活動や伝統芸能の分野では「主宰」がよく使われます。
また、個人の権威や継続性を強調したい場合にも「主宰」が適しています。
迷ったときの判断基準
最後に、実際に使い分けで迷ったときに、すぐに判断できる簡単な基準をまとめます。
以下のチェックリストを使えば、ほとんどの場面で正しい選択ができます。
3ステップ判断法:
ステップ1: 対象を確認
- それはイベント・催し物ですか? → 「主催」
- それは組織・団体ですか? → 「主宰」
ステップ2: 期間を確認
- 一度きり、または短期間ですか? → 「主催」
- 継続的に活動していますか? → 「主宰」
ステップ3: 焦点を確認
- 「何をするか」が重要ですか? → 「主催」
- 「誰が率いるか」が重要ですか? → 「主宰」
一目でわかる比較表:
| 確認項目 | 主催 | 主宰 |
|---|---|---|
| 対象 | イベント・催し | 組織・団体 |
| 期間 | 一時的 | 継続的 |
| 焦点 | 何を(What) | 誰が(Who) |
| 責任 | 開催責任 | 統率責任 |
| 終わり | ある | ない(続く) |
| 文脈 | ビジネス多い | 文化活動多い |
実践的な判断例:
- 「セミナーを開く」→ 一時的な催し → 主催
- 「教室を開く」→ 継続的な活動 → 主宰
- 「フェスティバルの責任者」→ イベント → 主催
- 「研究会のリーダー」→ 組織 → 主宰
- 「来月のパーティー」→ 一度きり → 主催
- 「10年続く読書会」→ 継続 → 主宰
最終チェックポイント:
文章を書き終えたら、以下を確認しましょう。
- カレンダーに日付を書けるものは「主催」
- 「○○年目」と年数を言えるものは「主宰」
- ビジネス文書では9割が「主催」
- 先生や師匠が中心なら「主宰」
これらの判断基準を使えば、「主催」と「主宰」の使い分けで迷うことはほとんどなくなります。
正しい言葉を使うことで、あなたの文書はより正確で信頼性の高いものになります。
相手に誤解を与えず、プロフェッショナルな印象を与えることができるでしょう。



















