
「顛末書を書いてください」と上司に言われて、「始末書との違いは?」「どう書けばいいの?」と焦った経験はありませんか?
職場でトラブルが起きたとき、この2つの文書は似ているようで目的も書き方も大きく異なります。
間違えると、謝罪すべき場面で事務的な報告をしてしまうなど、かえって信頼を損なう恐れもあります。
私自身、企業の人事担当者への取材を通じて、多くの方がこの使い分けで悩んでいることを知りました。

福沢さん、顛末書と始末書って似すぎていて紛らわしいですわね。
私も昔、女子英学塾で書類整理をしていて混乱したことがありますの。
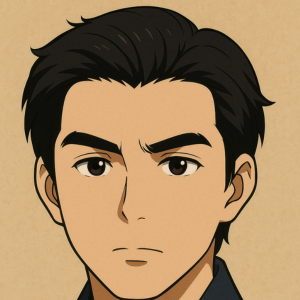
おお、梅子さんもか!
実は私も慶應義塾で学生が問題を起こした時、どっちを書かせるべきか悩んだことがあってね。
でも、これ、実は明確な違いがあるんだよ。
報告か謝罪か、この一点で決まるんだ!

なるほど!
つまり「何が起きたか説明する」のが顛末書で、「申し訳ございません」と頭を下げるのが始末書というわけですわね。
これは社会人なら絶対に知っておくべきですわ!
- 「顛末書」は事実経過の報告が目的。
- 「始末書」は謝罪と反省の意思表示が目的。
- 報告なら「顛末書」、謝罪なら「始末書」を使えばOKです。
✅ この記事でわかること
- 顛末書と始末書の5つの違い(目的・提出先・タイミングなど)
- ケース別の正しい使い分け方
- すぐ使える具体的な例文とテンプレート
- 提出後の人事評価への影響
- よくある疑問(手書きorパソコン、拒否できる?など)
この記事では、比較表や実践的な例文を使って、状況に応じた適切な文書作成方法を解説しています。
急な提出依頼にも慌てず対応できるよう、最後までご覧ください。
一目でわかる!顛末書と始末書の5つの違い
「顛末書」と「始末書」は、似ているようで実は役割や使われ方が大きく異なります。
誤解しやすい文書ですが、違いを整理して理解しておくと安心です。
ここでは両者を比較しながら5つのポイントを解説します。
目的:報告か謝罪か
「顛末書」の主な目的は「事実経過の報告」です。
発生した出来事を、何が・いつ・どこで・なぜ・どうやって起こったのかを整理して伝えるための文書です。
一方、「始末書」は「謝罪と反省」が目的です。
自身の不注意や規律違反により問題を起こした際に、心からの謝罪と再発防止策を示すために提出します。
✅ まとめ
- 顛末書=出来事の経過報告
- 始末書=謝罪と反省の意思表示
提出先:社内か社外か
「顛末書」は、基本的に 社内提出 が中心です。
上司や管理部門に対して、経過を整理し今後の対応を示すために用います。
「始末書」は、場合によって 社外提出 が必要になることもあります。
取引先に迷惑をかけた場合や、会社全体の信頼に関わる重大な問題では、社外への正式な謝罪文として提出されることがあります。
✅ まとめ
- 顛末書=社内向けの報告が中心
- 始末書=社内だけでなく社外提出の可能性もあり
タイミング:事後か即時か
「顛末書」は、事態が一段落した後に提出するのが一般的です。
落ち着いて経過を整理する必要があるため、多少の時間を置いてから求められるケースが多いです。
「始末書」は、問題が発覚したら すぐに提出を求められる 場合が多いです。
迅速な謝罪が必要だからです。
✅ まとめ
- 顛末書=事後報告(状況整理後に提出)
- 始末書=即時提出(早急な謝罪が必要)
作成者:当事者か報告者か
「顛末書」は、必ずしも当事者本人が作成するとは限りません。
部署の責任者や事故の調査担当者など、報告の役割を担う人が作成することもあります。
「始末書」は、必ず 当事者本人 が書くものです。
他人が代筆することは認められず、自筆で書くことを求められることもあります。
✅ まとめ
- 顛末書=当事者または報告担当者
- 始末書=必ず当事者本人
影響:懲戒処分の有無
「顛末書」は、基本的には事実確認と再発防止のために用いられるものであり、直接的に懲戒処分につながることは少ないです。
しかし「始末書」は、懲戒処分と密接に関わります。
始末書の提出を求められるケースは、規律違反や業務上の大きな損害が発生した場合であり、その後の人事評価や処分に影響する可能性が高いです。
✅ まとめ
- 顛末書=懲戒処分とは直接関係しにくい
- 始末書=懲戒処分や人事評価に直結する場合あり
【ケース別】顛末書と始末書どちらを提出すべき?
「顛末書」と「始末書」は、状況によってどちらを提出すべきかが変わります。
ここでは、ケースごとに適切な選び方を整理してみましょう。
顛末書を提出するケース(例:軽微なミス、事故報告)
「顛末書」は、比較的軽いミスや、事故・トラブルの経過を報告する際に使われます。
例えば「納期に遅れそうになったが、事前に調整して影響を回避した」など、最終的に大きな損害が出ていない場合が典型例です。
📌顛末書が必要になる場面
- 軽微な入力ミスや事務処理の誤り
- 事故やトラブルの経過報告
- 業務改善のための振り返り
このようなケースでは、反省よりも「事実を正確に伝えること」が重視されます。
そのため、冷静に経過を整理して報告する文書が顛末書となるのです。
始末書を提出するケース(例:重大な規律違反、損害発生)
「始末書」は、より重大な問題が発生した場合に提出を求められます。
例えば「遅刻や無断欠勤が繰り返された」「取引先に迷惑をかけ、損害を発生させた」といった場合です。
📌 始末書が必要になる場面
- 無断欠勤や勤務態度の重大な問題
- 顧客への迷惑や会社への損害を発生させた場合
- 社内規律やコンプライアンス違反
「始末書」は、単なる報告ではなく「謝罪・反省・再発防止策」を示す性質があるため、処分とセットで提出を求められるケースが多いのが特徴です。
両方の提出が必要な場合とは?
ケースによっては、「顛末書」と「始末書」の両方が必要になることもあります。
例えば「重大なトラブルを起こし、社内報告として顛末書が必要だが、同時に責任を取る形で始末書も提出する」といった場合です。
📌 両方提出する典型的なケース
- 大規模な事故やトラブルが発生したとき
- 社内外への影響が大きく、会社の信頼が損なわれたとき
- 個人の過失と組織の報告義務の両方が重視されるとき
この場合、顛末書で「事実の経過と原因」を、始末書で「当事者としての謝罪と再発防止策」をそれぞれ示すことで、会社としての責任を明確にするのです。
すぐ使える!顛末書の書き方と例文
「顛末書」は、ただ出来事を並べるのではなく、読み手に正確に状況が伝わるよう整理することが大切です。
ここでは、基本の書き方と実際に使える例文を紹介します。
記載すべき必須項目
「顛末書」には、最低限盛り込むべき情報があります。
漏れがあると信頼性が下がるため、以下の項目は必ず入れるようにしましょう。
✅ 顛末書の必須項目
- 発生日・発生場所
- 出来事の内容
- 原因や背景
- その後の対応(解決策や処置)
- 再発防止策
これらを整理することで、単なる報告書ではなく「再発を防ぐための有益な記録」として役立つ顛末書になります。
5W1Hで分かりやすく書くコツ
「顛末書」は「誰が(Who)・いつ(When)・どこで(Where)・何を(What)・なぜ(Why)・どのように(How)」の 5W1H を意識して書くと分かりやすくなります。
📌 具体的な工夫
- 時系列で整理する(例:「9時に発生 → 10時に上司に報告 → 11時に復旧完了」)
- 感情的な言葉を避け、事実を淡々と書く
- 主観ではなく客観的に説明する
こうした工夫をすると、読み手が状況をすぐ理解でき、改善に役立てやすくなります。
【社内向け】顛末書の例文
以下は、社内向けに提出する顛末書の例文です。
比較的シンプルな構成で、事実の整理に重点を置きます。
📄 例文(社内向け)
顛末書
発生日:2025年9月10日
発生場所:営業部オフィス
発生内容:顧客への請求データ入力に誤りがあり、金額が異なって記載されていた。
原因:入力作業時に確認を怠り、チェック体制が不十分だった。
対応:即日、訂正した請求書を再発行し、顧客へ謝罪のうえ再送付した。
再発防止策:今後はダブルチェックを徹底し、入力後に必ず上司が確認する体制を導入する。
以上
【社外向け】顛末書の例文
社外向けの場合は、取引先や顧客に提出するため、丁寧な文体と誠意ある表現が求められます。
社内向けよりも「謝罪の姿勢」を前面に出すことが重要です。
📄 例文(社外向け)
顛末書
株式会社〇〇〇〇
△△部 □□様
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは、弊社の不手際により御社にご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
【発生内容】
9月12日、御社に納品した製品の一部に数量の誤りがありました。
【原因】
受注データの転記作業において確認を怠り、誤った数量を入力したためです。
【対応】
即日、正しい製品を再納品し、担当者より御社へ直接謝罪いたしました。
【再発防止策】
今後はシステム入力後に二重確認を行い、同様の誤りが起こらないよう徹底いたします。
重ねてご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
敬具
【反省が伝わる】始末書の書き方と例文
「始末書」は「謝罪」と「反省」、そして「再発防止策」をしっかり伝えるための文書です。
「顛末書」とは違い、感情を排して事実だけを書くのではなく、誠意を示すことが求められます。
ここでは、基本の構成と例文を紹介します。
始末書に含めるべき内容
「始末書」は、形式が整っていればよいのではなく、誠意が伝わるかどうかが大切です。以下の項目を押さえて作成しましょう。
✅ 必須項目
- 発生した問題の内容(何をしたか)
- 謝罪の言葉(ご迷惑をおかけしたことへの反省)
- 原因の説明(なぜ起こったか)
- 再発防止策(次に同じことを繰り返さないための誓約)
- 日付・署名
これらを盛り込むことで、読み手に「反省していること」が伝わりやすくなります。
謝罪と再発防止策の示し方
「始末書」では、単なる「申し訳ありません」では不十分です。
重要なのは 「具体的な再発防止策」 を明示することです。
📌 書き方の工夫
- 謝罪は「ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と丁寧に表現する
- 原因を曖昧にせず、明確に書く(例:「確認不足」や「怠慢」など)
- 再発防止策は行動レベルで具体的に記載する(例:「二重チェックを徹底する」)
この3点を意識することで、単なる形式文書ではなく「信頼回復につながる始末書」になります。
始末書の例文(テンプレート)
以下に、すぐ使える「始末書」の基本例文を示します。
状況に合わせて修正すれば、そのまま活用できます。
📄 例文(始末書)
始末書
私はこのたび、〇月〇日において無断で遅刻をし、業務に支障をきたしました。
この行為により、職場の皆様ならびに上司に多大なご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今回の遅刻は、自己管理の甘さから起こったものであり、社会人として大変恥ずべき行為であると深く反省しております。
今後は、前日に業務に支障が出ないよう生活習慣を整え、また必ず始業30分前には出社するよう徹底いたします。
二度と同じ過ちを繰り返さないことをここに誓約いたします。
以上
令和〇年〇月〇日
所属:〇〇部
氏名:□□ □□
顛末書・始末書に関するQ&A
「顛末書」や「始末書」は、実際に提出する場面になると細かい疑問が出てくるものです。
ここでは、よくある質問をまとめて解説します。
提出を拒否することはできる?
基本的に、「顛末書」や「始末書」の提出を拒否することはできません。
会社の指示に従わないこと自体が「業務命令違反」となり、さらに重い処分を受ける可能性があります。
どうしても納得できない場合は、書き方を工夫する方法があります。
たとえば「事実の報告」を中心に書き、謝罪や反省の表現は最小限にとどめるなど、角が立たない形で提出するのが現実的です。
パソコン作成と手書きはどちらが良い?
最近は パソコン作成が主流 です。
理由は、読みやすさと保存・共有のしやすさがあるからです。
ただし、「始末書」の場合は「本人の誠意を示すために手書き」を求められることもあります。
会社のルールに従うのが基本ですが、迷ったら上司や人事に確認するのが安心です。
📌 一般的な使い分け
- 顛末書:パソコン作成でOK
- 始末書:手書きを求められるケースあり
提出後の人事評価への影響は?
「顛末書」の提出は、通常は人事評価に大きな影響を与えるものではありません。
事実整理と改善策をまとめる文書だからです。
一方、「始末書」は 懲戒処分とセットで扱われることが多く、人事評価に影響する可能性が高い です。
提出自体が「問題行為があった証拠」となるため、昇進や賞与に響くケースもあります。
報告書や反省文との違いは?
「顛末書」や「始末書」と混同されやすいのが「報告書」「反省文」です。
それぞれの違いを整理すると次のようになります。
| 文書の種類 | 主な目的 | 書き手 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 顛末書 | 出来事の経過報告 | 当事者または報告者 | 事実の整理・原因・再発防止策 |
| 始末書 | 謝罪と反省 | 当事者本人 | 謝罪・原因・再発防止策 |
| 報告書 | 上司や関係者への報告 | 担当者 | 業務の進捗や結果 |
| 反省文 | 自己の反省を表す | 当事者本人 | 謝罪と内省 |
こうして比較すると、顛末書と始末書は似ているようで目的がまったく違うことが分かります。
まとめ
「顛末書」と「始末書」は、どちらもトラブルやミスに関わる文書ですが、目的や提出先、影響の大きさが異なります。
「顛末書」は「事実の経過を報告する文書」、始末書は「謝罪と反省を伝える文書」と覚えておけば迷いません。
状況に応じて正しく使い分けることが、信頼回復や再発防止につながります。
本記事で紹介した例文や書き方のポイントを参考にすれば、急に提出を求められても落ち着いて対応できるはずです。
ぜひ実務にお役立てください。



















